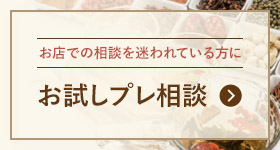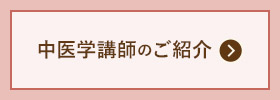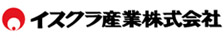来春の花粉飛散量は例年以上!
日本気象協会は、来春のスギ・ヒノキ花粉の飛散量が近畿や東海地方の一部で今春の10倍以上と予測した。同協会によると、来春の花粉飛散量はほとんどの地域で2倍以上になるようです。今夏は全国的に気温が高く日照時間も長くなり、スギとヒノキの花芽がよく成長したためで、静岡、岐阜両県、京都府周辺では飛散量は10倍以上になる恐れがあるという。ただ、今春は天候不順の影響で花粉の飛散量自体が少なかった。来春の予測を例年と比べてると、全国的には「やや多い」程度。(2010年10月16日 読売新聞)
【花粉症への備え】
中医学では、花粉症は衛気(えき)の不足が主な原因と考えます。衛気は、皮膚や気管支、鼻などの身体の体表部をくまなくめぐり、粘膜細胞を強化して防衛力を高め、バリアを張り巡らす働きがあります。アレルギー疾患だけでなく、風邪や慢性疲労、冷え症、肌荒れなども衛気のパワーが不足している事が原因と考えられています。ストレスや睡眠不足、偏食など、エネルギーを消耗する生活を続けていると、防衛力が低下して病気に対する抵抗力が落ちてしまい、風邪をひき易くなったり、疲れやすくなったりします。この冬は衛気をパワーアップして身体の防衛力を高め、来春には花粉症やその他の不快な症状を近づけない身体になるよう心がけていきたいですね。
良くつかわれる生薬
(左上:黄耆 右上:白朮 左下:防風)
中医学では体の細胞を元気にする働きを「補気(ほき)」と言いますが、生命の活力源の気を生み出す生薬の中で二大補気薬と呼ばれているのが、「黄耆」と「朝鮮人参」です。
同じ補気薬でも、活用の仕方に違いがあり、「朝鮮人参」は体内から元気づけ、黄耆は体表部や粘膜を強化し、免疫力を調整する働きがあります。外的刺激に弱い肌や粘膜を健康に保ちたいときは、 「黄耆」が用いられます。
つまり、「衛気」をパワーアップするには、黄耆が最も適しているというわけです。黄耆は、免疫力を高めるだけでなく、体の状態に応じて免疫の過剰反応を抑えてバランスを保つ働きも兼ね備えています。
衛気を補う「黄耆」を中心に、消化機能を高める「白朮(びゃくじゅつ)」 、風邪の侵入を防いで気をめぐらせる「防風(ぼうふう)」などを組み合わせた代表的な処方に「玉屏風散(ぎょくへいふうさん)」(和名=衛益顆粒(えいえきかりゅう))があります。
この名前は、邪気から守る屏風の働きが宝玉のように素晴らしいという意味から名付けられたもので、中国では花粉症や風邪、インフルエンザ、喘息などの予防に用いられています。
良くつかわれる漢方
衛益顆粒(えいえきかりゅう)、麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)、シベリア霊芝
衛気強化のポイント
肺・脾・腎の機能を高めていく事が衛気をパワーアップさせるポイントです。
ここでいう肺や脾、腎は、単に臓器そのものを指すのではなく、呼吸や消化、免疫などの機能や役割を含んでいます。
中医学では、肺は呼吸器のほかに、発汗などの体液代謝や体温調節機能を持ち、「衛気」を体表面にはりめぐらす働きがあります。
また、脾は食物から栄養を消化吸収し、エネルギーである気に変換する機能があり、「衛気」の原動力を生みだしています。腎は泌尿器系、ホルモン系、生殖器系の機能を持つほか、「腎は精を蔵す」と言われるように、気を貯蔵する働きがあります。
衛気を高めるツボ
全身をめぐる気(エネルギー)や血液が通る経絡にあるツボは、血行を促進して代謝を高め、滞った気の流れをスムーズにして体調を整える効果があります。ツボを2~3秒押えてゆっくり力を抜くのがポイントです。食後は避けて食間や食前に。
湧泉

足の指を曲げたときにできるくぼみの所。ストレスによる緊張を和らげて、全身の血行を促進する。疲労や高血圧にも効果的。