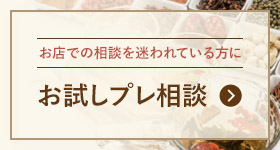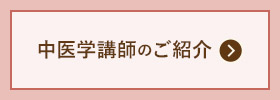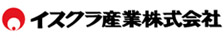「コーヒーにも紅茶や緑茶にもカフェインが入っているのに、コーヒーはだめで、紅茶、緑茶はいいの?」というご指摘がTwitter経由でありましたので、調べてみました。
まず、コーヒーと紅茶に含まれるカフェインの量の問題ですが、良く一般的にコーヒーより紅茶の方がカフェインが多いと言われていますが、それは正しくありません。
コーヒー豆と紅茶葉100gでは確かに紅茶の方がカフェインがおおいけど、一杯につかわれるコーヒーの量は約10g。それに対して紅茶は2g~5g。飲む状態、紅茶を抹茶のようにして飲まない限りは、コーヒーの方がカフェイン含有率は高い ので、コーヒーは敬遠されているようです。これは、多量の葉っぱを使わない緑茶にも同じ事がいえます。
次に、中医学的にこの三者を見ると、
コーヒーの性味は苦味で平性。帰経は心肺。効能は養心、安神、強心、利水、解酒毒、適応が眠気、二日酔いで、作用が覚醒とあります。
紅茶の性味は苦味、甘味で温性。帰経は心肺。効能は養心、安神、止渇、利水で、適応は口渇、煩熱。
緑茶の性味は苦味、甘味で涼性。帰経は心肺胃肝。効能は生津、止渇、清熱、解毒、利頭目、除煩、安神で、効能は頭痛、視力低下、倦怠、眠気、煩熱、口渇で、作用が爽快とあります。
(”現代の食卓に生かす「食物性味表]” 日本中医食養学会 編著より)
これを見比べると、紅茶と緑茶には、止渇*、生津*とありますが、コーヒーには利水*だけです。体の潤いが減ることを中医学では“津液の損傷”という言い方をしていてとても重要視しています。津液とは体の正常な水分の事で、津はサラサラしているのもので、主に身体の表面を潤し、液は粘り気があり、体内をゆっくり流れて骨や髄を潤しています。津液は互いに協力して、臓腑、筋肉、毛髪、粘膜などを潤し、関節の動きを円滑にするなどの働きを持っています。
*止渇:激しい喉の渇きを解消させる
*生津:津液を生む という意味なので生津と止渇はほぼ同意。
*利水:余分な要らない水分・余剰物質を尿として排出する方法
そして、中医学はこの津液を守ることを大変重視します。これは津液の不足は組織液の不足としてとらえることもでき、不足することで細胞や組織が正常に働かなくなってしまうからです。津液がへると、乾燥症状(口やのどの乾燥から、便秘など)からひどい場合は脱水症状(意識喪失、痙攣)が見られます。激しい下痢や嘔吐、出血過多などが原因の場合や、慢性病や生活習慣などによって発症する体内の乾燥の場合があります。体から、それがたとえ何であれ、水分(汗であれ、血であれ)が漏れだすことは命にかかわることになりかねないので、津液を守ることは大変重要なんです。そういった意味でも、利水作用だけがあり、興奮作用のあるコーヒーよりも、潤すことができ解毒できる緑茶や、潤す作用がある紅茶の方が身体には良いといえます。
今回はなかなか鋭いご指摘でした。大変勉強になりました。
またそんなご指摘、お待ちしております。
ブログ日記BLOG
コーヒーはダメで、紅茶や緑茶いいの??
2010/12/03