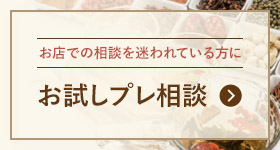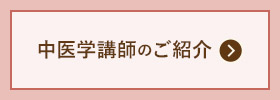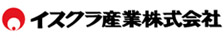あけましておめでとうございます。
櫻井です。
突然ですが、
芹、薺、御形、繁縷、仏の座、菘、蘿蔔とは、
皆さんご存知の“春の七草”、七草粥に入る植物の事なんですが、
皆さんはいくつ読めますか?
僕は、漢方を生業にしておきながら一つも読めませんでした,,汗
ちなみに読み方は、、
芹 (せり) =セリ
薺 (なずな) =ペンペン草
御形(ごぎょう)=ハハコグサ
繁縷(はこべら)=コハコベ
仏の座(ほとけのざ)=コオニタビラコ
菘 (すずな) =カブ
蘿蔔(すずしろ)=ダイコン
となります。全く漢字は難解ですね。
恥ずかしながら蘿蔔(すずしろ)なんて、
「ぶどうか??」と思ったぐらいです。
(ちなみにぶどうは葡萄と書きます)
七草、七草と昔から聞いていましたが、
それらが何を指すものかも分かっていなかった次第です。
所で、この七草の行事、これはいったいいつから始まって、
何が由来なのでしょうか?
七草の由来
春の七草とは本来、邪気を払い、無病息災を祈念する平安時代から続く行事だそうで、その頃は、餅粥で毎年1月15日に行われ、米・栗・黍(きび)・稗(ひえ)・みの・胡麻・小豆の七種の穀物だったようです。江戸時代には<<人日>>と言って、五節句のひとつとなっていたようです。ちなみに<<人日>>とは人を占う日というらしいですが、詳しいことは分かりません。。。
昔は、前日(1月6日)の夜にまな板に載せて「七草なずな 唐土の鳥が、日本の土地に、渡らぬ先に、合わせて、ばたくさばたくさ」など(地方により多少の違いがあるようです)と囃し歌を歌いながら包丁でたたき、当日の朝に粥に入れていたようです(wiki参照)
春の七草の効能
手もとの本によると、セリは余分な熱をとり、おしっこやおりもののトラブルに良いとされ、なずなは、胃腸を元気にし、むくみや胃の不快感、目の充血などにも良いようです。オギョウ(別名 ははこぐさ)は、咳を鎮め、痰を出すのに良く、ハコベラは利尿によく、産後の浄血によいとされ、ホトケノザは胃腸に良く、スズナ(かぶら)、スズシロ(だいこん)は解毒や、消化不良によいとされています。
春の七草は、お正月料理で疲れた胃腸にはぴったりのお粥といえますね。
ちなみに、、、
春の七草はご存知の通り1月7日ですが、これは旧暦の1月7日の事を指しています。となると、旧暦の正月は2月初旬ですので、この七草も2月ごろ、春先に食べごろを迎える植物たちですので、今、スーパーに並んでいる『七草粥セット』なるものは温室栽培のものや、中には多少違った植物が入っているものあるようです。
でも、緑たっぷりのお粥は胃腸に良いことは間違いありませんので、安心して七草粥を楽しんでください。
それでは、14世紀、時は南北朝時代の四辻の左大臣(よつつじのさだいじん)が源氏物語の注釈書「河海抄(かかいしょう)」の記載から良く知られる一句を、、、
『芹なずな御形はこべら仏の座すずなすずしろこれぞ七草』
四辻左大臣
最後になりましたが、今年もスタッフ全員、皆さまのご健康のために誠心誠意頑張りますので、足りぬところは多々あるとは思いますが、本年も何とぞよろしくお願いいたします。