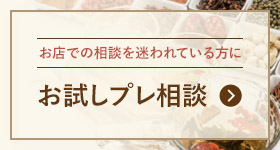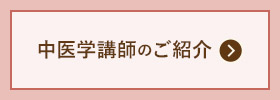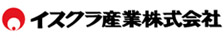あっと言う間に11月。朝晩の冷え込みも厳しくなってきましたね。
昨日の話なのですが、NHKの「あさイチ」をご覧になられた方いらっしゃいますか?
昨日は、高野山の魅力について紹介されていました。
高野山と言えば、平安時代に弘法大使・空海が開山した真言宗の総本山ですね。
この高野山で話題の和菓子と言う事で「仏手柑まんじゅう」が紹介されていました。
みなさん、「仏手柑」てご存知ですか?
柑と言う字が入っている通り、ミカン科の植物です。
でも、その形がちょっと珍しい。人が指先をすぼめた手のような形をしています。
仏に手を合わせる姿に似ている事からその名が付けられたとも言われています。
食べられる身の部分がほとんど無いので、主に観賞用としてしか使われていないため、
日本では生産している農家さんもあまりなく、メジャーでは無いですね。
ですが、この仏手柑、中国ではとても有名。
井上もこの夏に雲南省に研修に行った際に見かけて写真を撮っていたようで、
そう言えば中国からわざわざ添付してメールしてくれていました。
↓それがこちら。

ちょっとこの画像だとあまり「手」には見えないのですが・・・
ついでにもう1枚。

「buddha hand」。うむ。まさに「仏手」。
そんな仏手柑ですが、これ、実は漢方薬としても使われます。
仏手柑:ミカン科のブシュカンの成熟果皮
【性味】辛・苦・酸、温 【帰経】肝・脾・胃・肺
【効能】気の巡りを調節し、胸や胃などの張った痛みやつかえ、食欲不振などを改善
実は、養生茶としてこの仏手柑のお茶がイスクラ薬局にもあるんです。

柑橘類の実の皮を使った生薬には他にも陳皮(ミカンの皮)などがありますが、
これも気の巡りを良くする生薬ですね。
これらの生薬になるものだけでなく、柑橘類の香りと言うのはみな気の巡りを良くします。
これから寒くなってくると、体も気や血の巡りは鈍くなりがち。
日本の冬の風物詩(?!)のおこたでミカン、と言うのは、
少なからず冬の循環の悪さを改善する日本人の生活の知恵なのかもしれません。