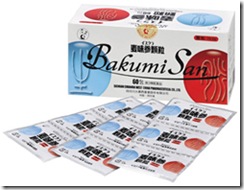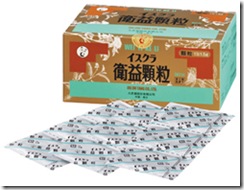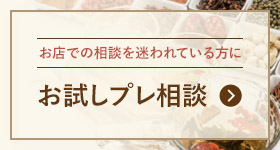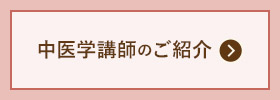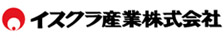(チャイナビュー No.146 漢方の知恵袋 菅沼栄先生の記事より抜粋)
まだまだ寒さの厳しい季節が続きますが、春はもうすぐそこ。花粉症の人にとってはつらい季節ですが、早めの対策を心がければこの時期をラクに乗り切ることもできます。本格的な花粉シーズンを迎える前に、”花粉に負けない身体づくり”を目指しましょう。
身体の抵抗力をアップして花粉の侵入を防ぐ
中医学では、季節ごとの特徴やその影響を考えながら身体を整えることを大切にしています。強い風の吹く「春」に気をつけたいのは「風邪(ふうじゃ)」。風邪にはほかのさまざまな邪気を連れて身体に入り込むという特徴がありますが、「花粉症」はこの風邪が花粉を運んで身体に入り込む事が原因と考えられています。
こうした邪気(風邪や花粉)の侵入を防ぐやくわりを果たしているのが、体内の「衛気(えき)」です。衛気は身体を守る「抵抗力」のようなもので、身体の表面(鼻やのどの粘膜、皮膚など)にバリアのように存在し、邪気の侵入を阻止しています。そのため、体内の衛気が不足すると花粉などの邪気が身体に入り込みやすくなり、鼻水やくしゃみ。目のかゆみといったアレルギー症状が現れるのです。
反対に、体内の衛気を十分に養って身体の抵抗力を高めることで、花粉症の症状を改善することも期待できます。花粉症に悩まされている人は、症状を抑えるのと同時に日頃から体質を整えておくことがとても大切。今年の春は、花粉の飛散量が例年より多くなると予想されています。冬のうちから早めの体質改善に取り組み、つらい症状をなるべく軽くできるよう心がけましょう。
花粉症・予防のポイントと症状別セルフケア
花粉症対策は、花粉症対策は、"根本的な体質改善"と、”症状を抑える養生"の二段構えが基本。本格的な花粉が来る前に、まずは、"花粉に負けない体質づくり”から始めましょう。
予防のポイント
「衛気」を養って身体の抵抗力をアップ!
花粉症の予防は、邪気(風邪や花粉)を寄せ付けない"抵抗力の強い身体づくり”が基本。そのためには、身体の抵抗力となる「衛気」を十分に養うことが大切です。
「肺」と「脾胃」は、呼吸や栄養の吸収を通じて「気」を生みだす大切な臓器。そのため、これらの臓器が弱っていると体内の衛気も不足しがちになり、花粉症の症状も出やすくなってしまいます。普段からカゼを引きやすい、胃腸が弱い、虚弱体質で疲れやすい、といった不調を感じている人は、肺や脾胃を健やかに保つように積極的な養生を心がけましょう。
また、ストレスや睡眠不足、食事の不摂生なども身体のバランスを崩して抵抗力を低下させる原因に。十分な睡眠、バランスのとれた食事など、生活習慣を整えることも大事です。
花粉症予防の体質改善は、季節を問わず日頃から取り組むことがポイント。まずは今年の春に向けて、今すぐ始めて見て下さい。
こんな人は要注意!
食の養生
不足した「衛気」を補い、体力のつく食材を。
- 大豆製品(豆腐、湯葉など)
- いんげん豆
- 白きくらげ
- 白ゴマ
- クコの実
- ナツメ
- グリーンピース
- カレイ
- 米
- もち米
良くつかわれるのは
- イスクラ衛益顆粒
- 補中益気湯
症状をなるべく軽くするためにも、毎日の過ごし方にちょっとした工夫や注意を。メガネやマスクを身につけたり、衣服に付いた花粉を払い落したり、こまめな対策の積み重ねで花粉がなるべく身体に入らないようにする事が大切です。
また、脂っこいたべものや辛いもの、甘いものなどの食べ過ぎは避け、新鮮な野菜をたくさん摂るようにするなど食事にも気を配りましょう。
次回は症状別セルフケアについて書きます!