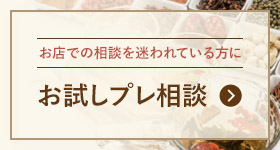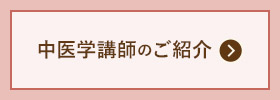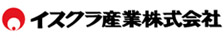最近少しずつ気温が下がり、過ごしやすくなってきたなあと感じます。
が、また台風が来ているようで、雨が降ったりやんだり豪雨になったり…。めまぐるしいですね。
こんにちは、太田です。
さて、今日はイチジクのお話。
先日ニュースサイトでイチジクのお話を読んでから、イチジクを食べたくなって生で1つ食べ、
甘みが足らなかったので、白ワインで煮詰めてコンポートにしてヨーグルトにかけていただきました。
独特の歯ざわりが美味しい果物ですよね。
イチジクは無花果と書きますが、花は実の中にあり、イチジクの故郷の野生状態ではイチジクコバチという小さなハチが受粉を助けているとのこと。
日本で栽培されるイチジクは、このハチを介さずに実がなる品種のようです。
有効成分は様々ありますが、フィシンなどの酵素が含まれており、食後に食べると消化を助けてくれます。
また、お酒を飲んだ後に食べると、二日酔いにもなりにくいとも言われています。
まさに食欲の秋にピッタリの果物なんですね~。
中医学的には、生津・潤肺・止咳などの効能があるといわれています。
秋は乾燥する季節ですので、こちらの点からもイチジクは是非食べたい果物です。
皆様もよろしければ今日のデザートにイチジクをどうぞ♪