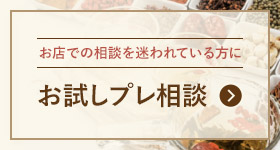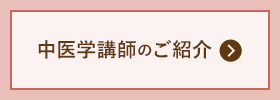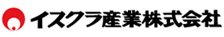「痺証」って何て読むの? 「痺証」とは???
と思われる方もいるかもしれませんね。
「痺証」は「ひしょう」と読みます。
風・寒・湿・熱といった外からの邪気が人体に侵襲して、経絡を閉塞し、気血の流れが不調になることにより、筋肉・筋骨・関節に強い痛みが発生する症状を指します。
痺れやこわばり、屈伸不利などを伴うこともあります。
簡単に関節炎と言えばわかりやすいかもしれません。
現代では、リウマチ、変形性膝関節症、坐骨神経痛、腱鞘炎、骨粗鬆症などもこの「痺証」の範疇とされています。
今年は、中国から広州中医薬大学の何偉教授をお招きしての講座でした。
講義の中では、主に変形性膝関節炎や骨粗鬆症についての説明と、臨床症例や中医対応などを丁寧にお話していただきました。

この痺証の治療や予防の原則となるのが「補腎活血!」
つまり、
1.「補腎」=老化や、骨・腰の脆弱化と密接に関係する「腎」の機能をサポートすること。アンチエイジングともいえます。
2.「活血」=血液の循環を良くして「痺証」の痛みを軽減させていくこと。
が大切なのです。
「補腎」と「活血」はどちらも中医学の得意分野です。
痺証に限らず、「補腎活血」は様々な病気に対して予防・治療の重要なカギとなり、長寿の秘訣でもあります。
実際、中野店での痺証のご相談では、痛みの原因を探り、「補腎活血」だけでなく、お一人おひとりの症状や体質に合ったお薬をご案内しています。
日本は「寿命大国」と言われて久しいですが、元気で長生きしてこそ! ですね。