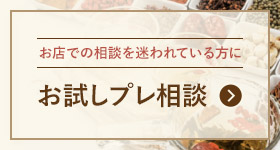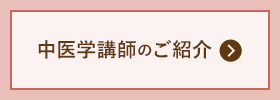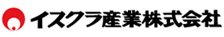白加賀という品種の青梅で梅シロップを作りました。
浸透圧の関係で、梅酒や梅シロップは氷砂糖を使うことが多いですが、もう少し柔らかい甘さにしたくて、てんさい糖で作ってみました。

中薬大辞典によれば、青梅の効能は利咽・生津(喉をスッキリさせ口渇を解消する)となっています。
梅の酸味が唾液の分泌を活発にするので、発熱や発汗などによる喉の乾きによし。
梅シロップには、血液サラサラや疲労の回復にもよい「クエン酸」が豊富に含まれているので、夏のドリンクには最適です。
炭酸水で割っていただきます。

梅といえば、中国には「望梅止渇(ぼうめいしかつ)」という話があります。
「三国志」に出てくる曹操が、歩き疲れた兵に「前方に梅林がある」と話したとか。
梅林→梅→梅は酸っぱい→条件反射で唾液分泌→口渇紛れる→引き続き頑張って行軍せよ…ということです。
条件反射で唾液が出たって、喉の乾きがなんとかなるとは思えませんが…
中国にも塩や砂糖で梅を漬ける習慣がありますが、日本の梅干しほど酸っぱくはないです。
例えば、話梅(ホワメイ)という干し梅は甘酸っぱく、お茶請けやおやつとして好まれています。
年々長くなっていく夏、梅シロップや梅干しを取り入れて乗り越えましょう!