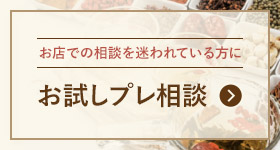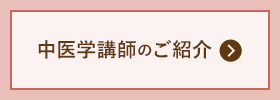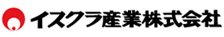今回は中医学の治療の考え方での特徴や注意点について書いていきたいと思います。
体の不調でお悩みがあり、ご家族やご友人から「私はこの漢方薬を飲んで〇〇が改善したから試してみたら?」と友人から勧められたり、「この漢方薬は〇〇に効く」という広告を見たりして、その漢方薬を試してみたけれど、あまり効かなかったとおっしゃるお客様がいらっしゃいます。
これはなぜでしょうか。

中医学には同病異治(どうびょういち)という言葉があります。
同じ病名でも、原因やその人の体質によって治療法が異なるという意味です。
例えば頭痛の場合、西洋医学では多くの場合鎮痛剤が使用されます。しかし中医学では、その人の頭痛の原因(冷え・のぼせ・血行不良・ストレス・血の不足など)と、発症時期や住んでいる地域、病気の段階、体質などを考慮して漢方薬を選びます。
ですから、あの人には効いた漢方薬が私には効果がなかった、というようなこともあるのです。
こうした病因、病位、病状などを総合的に考察し、その時に、その人が持つ本質をあわらしたものを「証(しょう)」といいます。
少しわかりにくいですね。
「自分は不眠の相談をしているのに、もらった薬が、家族がめまいで飲んでるのと同じものでいいの?」というような疑問の声をお聞きすることもあります。
これはご本人様と、めまいでご相談されたご家族様の「証」が、例えば「気血両虚(きけつりょうきょ)証」(簡単に言ってしまうと「元気・血液不足の証」)のように、一致しているからです。
つまり、同じ病気でも証が異なれば治法も異なり(同病異治(どうびょういち))、病気が異なっても証が同じなら治法も同じ(異病同治)なのです。
私たちがお受けする相談も、このような中医学の本質的な思想に基づいて行っております。
漢方薬は西洋薬と比べて副作用が少ないと言われていますが、原因や体質を考慮せずに合わない漢方薬を服用すると、症状が改善しなかったり逆に悪くなってしまうこともあります。
体の不調でお悩みがある場合は薬局スタッフにご相談してみてくださいね。