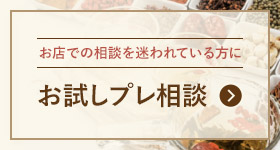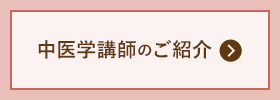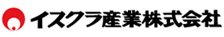今回は「血」の不足について西洋医学と中医学の考え方の違いについて書いていきたいと思います。病院では貧血と言われたことはないのに、漢方薬局で相談したら血が不足していると言われることがあります。
実は、西洋医学と中医学では「血の不足」についての考え方が少し異なります。
まず西洋医学では血液検査をして「血液の成分」に低い数値が出たら貧血といいます。最も多い鉄欠乏性貧血では、酸素を運ぶHb(ヘモグロビン)が基準値以下になるので、疲労感や倦怠感、顔面蒼白などの症状が現れます。

一方、中医学における「血(けつ)」は酸素や栄養を体の隅々に届ける働きの他、体を温める、内臓や組織を栄養する働きも持っている物質であると考えられています。これらの血の働きが低下した状態を「血虚(けっきょ)」と言います。
血液検査の数値で判断するのではなく、血の働きの低下による症状が見られれば血虚と判断します。ですから、西洋医学では貧血でなくても、中医学的には血虚である場合があるわけです。
血虚の状態だと以下のような症状が出やすくなります。
・お肌が乾燥しやすい
・髪の毛が細くなる
・毛が抜けやすい
・目が疲れやすい
・ドライアイ
・便秘(便が乾燥して固くなって出にくい)
・冷え性、
・生理不順 等
また、中医学の「血」には正常な精神活動を維持する働きもありますから、血虚になると情緒不安定になったり、睡眠の質が悪くなったり、忘れっぽくなったりすることがあります。
貧血ではないけど、いつも不調がある方は、もしかしたら血虚かもしれません。血虚の場合には血を補うお薬を使ったりして症状の改善を目指します。
おすすめの漢方薬もありますのでお気軽にご相談ください。