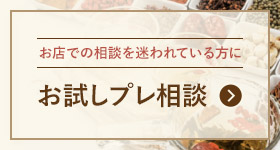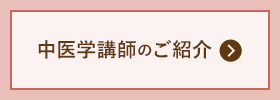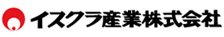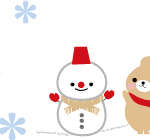
ウイルスによるカゼなど感染症とは別に、温度差で鼻水やくしゃみ、じんましんなどが出るのを「寒暖差アレルギー」といいます。
寒暖差アレルギーは、原因となるアレルゲンがあるわけではないので、正確にはアレルギーではなく、急激な温度差に血管の拡張・収縮が適応できず、症状が出ると考えられています。
寒暖差アレルギーを中医学的に考えると、「衛気(えき)」の働きの弱りと考えられます。「衛気」は、毛穴の開閉によって体温調節を行っているので、「衛気」が不足すると温度変化に対応する力が低下し、寒暖差アレルギーの症状が出やすくなると考えられます。
寒暖差アレルギーは温度差が7℃以上で発症しやすいと言われますが、「衛気」が弱いと7℃未満でも発症することがあります。
ですから、「衛気」の働きを充実させることが大切です。
また、「衛気」には、体表にバリアを張り巡らせて、異物(ウイルスや花粉など)の侵入を阻止する働きもあります。
「衛気」を補うことは、寒暖差アレルギーの予防・今流行中のウイルス性疾患の感染予防・花粉症の予防と一石三鳥になりそうですね。