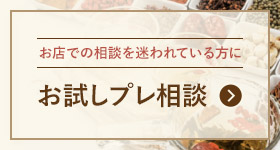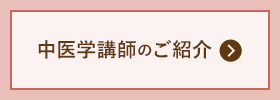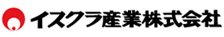まもなく11月ですが、いまだに25℃前後の気温が続いていますね。
天気予報では、11月になるとようやくヒンヤリしてくるそうです。
そこでウッカリ身体を冷やしてしまうと、「寒邪(かんじゃ)」による不調が出てきてしまいますので要注意。
「寒邪」によつる不調とは、頭痛・腹痛・生理痛などの痛み、筋肉のけいれん、トイレが近い…など。
どれも困りますね。
本格的な冬の前から、しっかりポカポカ対策していきましょう!
①飲食は温かいものを
冷たい飲食はお腹を冷やします。
お腹が冷えると消化吸収の力が弱り、全身を温める気血の不足に繋がることも。
生姜やシナモンは身体を温めてくれる食材なので、冷える日におすすめです。
②手首・足首・首元を守る
「首」は身体の中でも細い場所、寒さが身体に伝わりやすい場所です。
気温が低いときには、この三か所の「首」をしっかり守って保温しましょう。
③適度な運動
適度に運動をすることで、血流がよくなり、手先足先まで血が巡ります。
また運動することで脳内にはストレス解消ホルモンが分泌され、気分もさわやかに。
いろいろ気を付けていても、なかなか冷えが取れない方もいらっしゃいます。
中医学では、身体を温めているのは「気」の「温煦(おんく)作用」によるものとされています。
気が足りない「気虚(ききょ)」や「陽虚(ようきょ)」の方は、全身が冷えるタイプ、
気が巡らない「気滞(きたい)」の方は、手先足先が冷えやすいタイプです。
気が足りないなら「補気(ほき)」、冷えの強い方は「補陽(ほよう)」をします。
もたれない、消化にいいメニューを心がけて、ごはんやいも類、豆類、
にら、ねぎ、しょうが、らっきょう、まぐろなどをとりましょう。
腰のあたりにカイロを当てることも補陽になります。
気が巡りが悪いなら「行気(こうき)」、香味野菜や柑橘類など、香りのよいものをとりましょう。
③の適度な運動も「行気」に繋がります。
それぞれの体質によっておすすめする漢方薬も変わってきますので、
ぜひ店頭にてご相談くださいね!