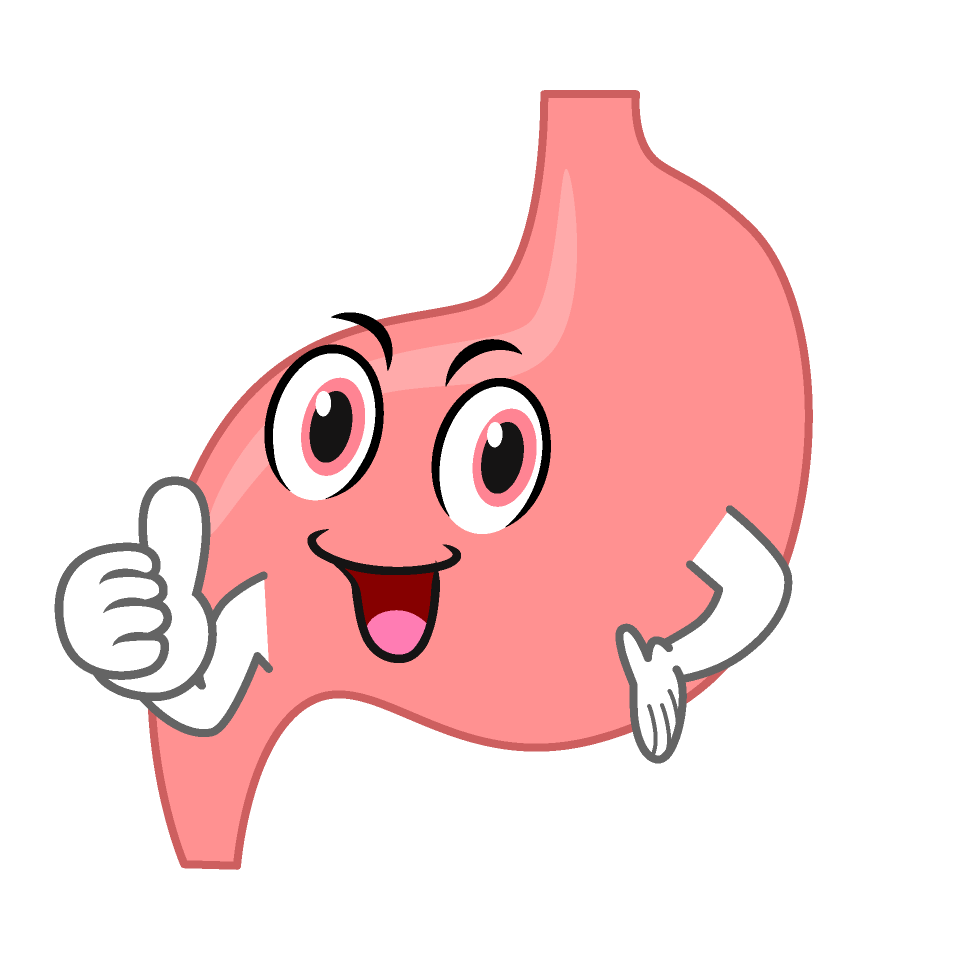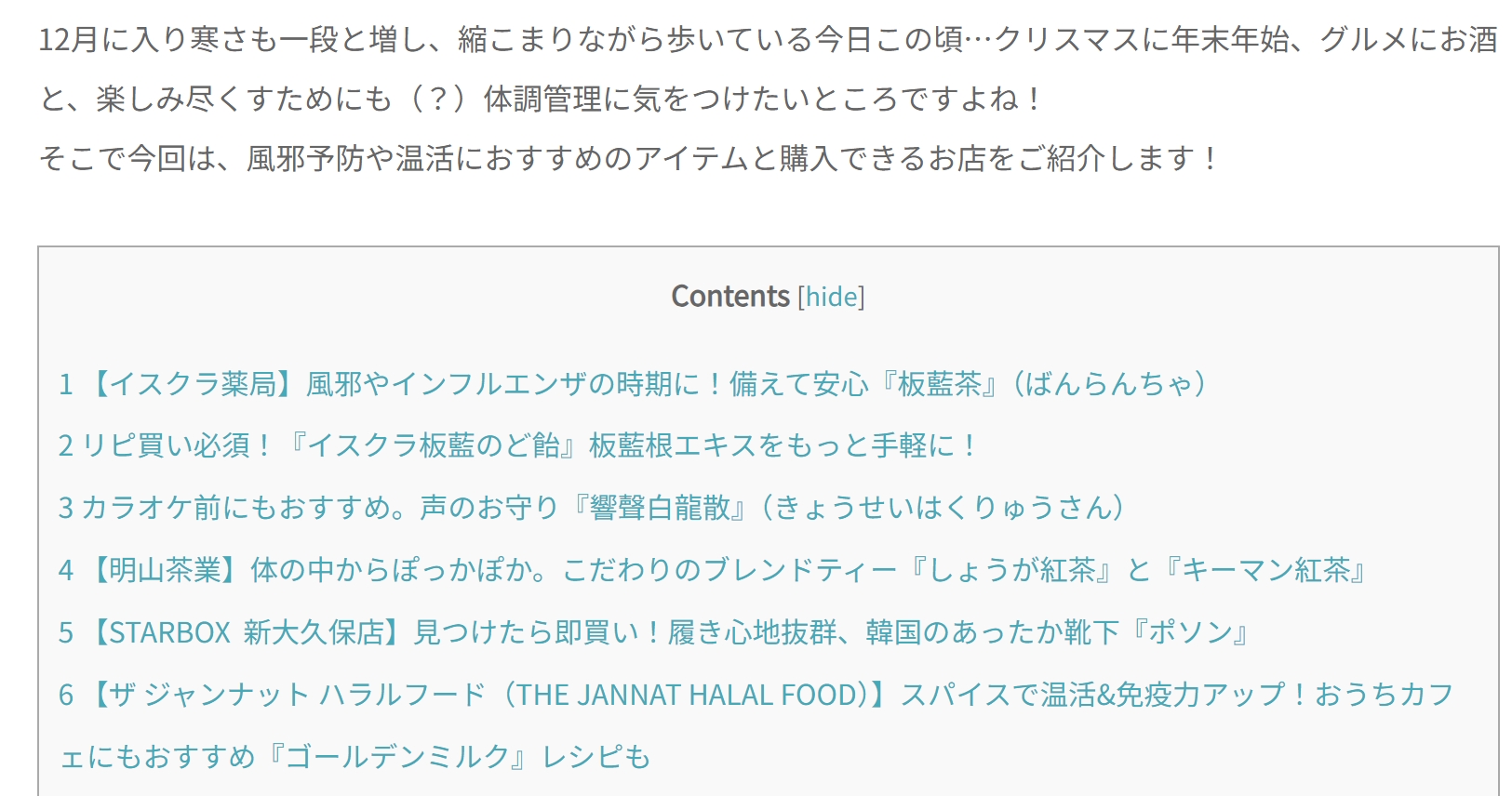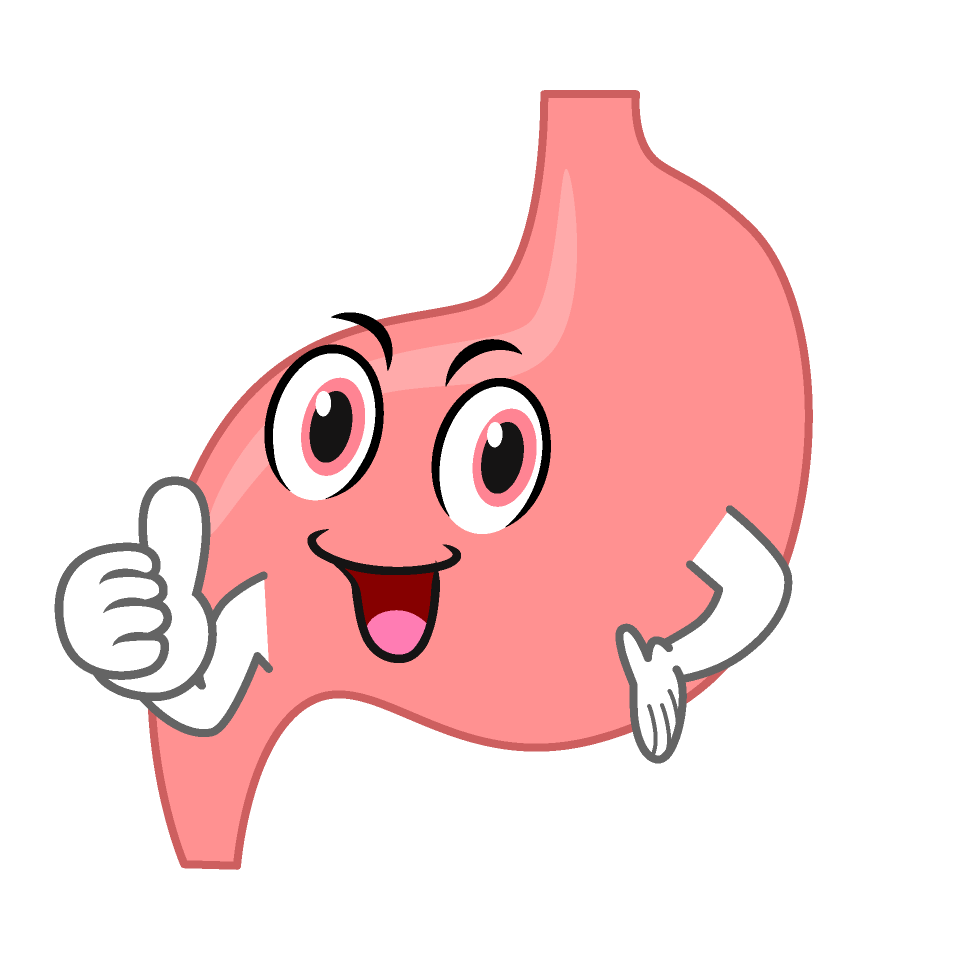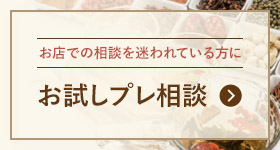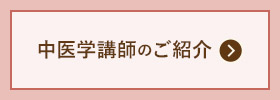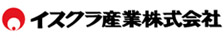秋らしい気温になり朝晩も冷えてきましたね。
気温が下がると胃腸の動きが悪くなり、胃腸の不調が出てきます。
今回、実習生の方が胃腸の不調について記事を書いてくれました。
この時期の不調対策のご参考になれば幸いです。
——————————————————————————————
実習生の丹沢です。
最近めっきり寒くなってまいりました。この時期、寒さでお腹が冷えて、下痢や便秘といった症状に悩む方が多くいらっしゃると思います。今回は、そんな胃腸(中医学で脾:ひ)について解説したいと思います。

【脾(ひ)とは】
中医学では、脾は中焦:上腹部に位置し、身体に必要なものを胃や小腸を通して消化吸収して取り込み、水穀の精微の気(飲食物を素に作る栄養素)を作り出すことで、身体の基本物質である気、血、津液の原材料を供給しています。イメージとしては、食べ物から栄養やエネルギーを作り、それを全身に送る役割を担っています。
【脾の働きと不調】
脾の働きは主に3つあります。
1.運化作用(うんかさよう)
口から入った飲食物の中から、身体にとって必要なものを取り込んだり、残ったものを大腸に運んだりと、この一連の消化、吸収の働きは脾によって管理されています。
2.昇清作用(しょうせいさよう)
脾は取り込んだ栄養を体の上の方に持ち上げる働きがあります。この機能のおかげで内臓や器官の位置を固定し、下に垂れないよう防いでいます。
3.統血作用
血が経脈を流れる際に、脈外に溢れるのを防ぐ働きがあります。この作用が低下すると、血便や血尿、女性では不正出血や月経過多が起こりやすくなります。
【脾の不調について】
脾の調子が崩れると、以下の症状が現れます。
1.運化作用の不調:食欲不振、もたれる、食後の倦怠感や眠気、軟便、下痢、むくみなど起こります。また、味がしない、口が粘っこい、唇が白いなど口や唇の症状としても現れます。水分や食べ物が代謝されずに残ると、水分代謝が悪くなり余分な水分が滞留する状態になります。
2.昇清作用の不調:気が内臓を持ち上げられなくなり、腹部下垂感、胃下垂、脱肛症状が起こったり、栄養成分が体の上のほうに送られなくなるため、食後の眠気、めまい、ふらつきなどの症状が現れます。
3.統血作用の不調:鼻血、不正出血、月経過多、皮下出血などの出血症状が現れます。
他にも、脾の変動は筋肉にその状態が現れるので、脾が失調すると、痩せるなどの症状が現れます。
【脾が不調にならないための対策】
日常生活でもこれらのことに気をつけましょう。
1.よく噛んで食べる
胃腸に負担がかかるものは消化に時間を要します。そのためによく咀嚼して、胃腸への負担を軽減してあげましょう。
2.夕食は遅い時間に食べない
一般的に夕食と就寝時間は3時間程度あけると良いと言われています。消化の途中で寝ると、消化不良で胃腸の不調に繋がるだけでなく、未消化の食べ物が睡眠の質に影響することもあります。
3.野菜を多めに食べる
特に旬の野菜を取ること、野菜は火を通して食べると胃腸への負担が減ります。カロリーを抑えられることもメリットになりますね。
4.冷たいものを取りすぎない
冷たい物の取りすぎにより、胃腸が冷えて運動が鈍くなり消化不良に繋がりやすくなります。今からの寒い季節には、お腹を冷やさないように意識しましょう。