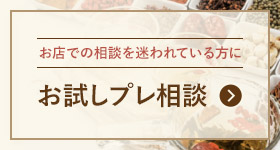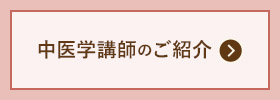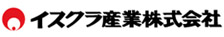今回のウェルカムティーは、気の巡りを良くする「仏手柑(ぶしゅかん)」の養生茶です。

一息ついたところで、お楽しみの本日の薬膳メニューは・・・
・地黄醤肉絲
・黒ゴマのペースト 産直野菜と
・リンゴとプルーンのシリアル
・決明子のお茶

地黄醤肉絲とは豚肉に人参、ピーマンを加えて炒めた一品です。黒く小さな塊は、体に潤いを与える熟地黄(じゅくじおう)です。地黄には生地黄(しょうじおう)と熟地黄とがあり、生地黄は清熱の効能があり、熟地黄にはお酒で蒸し日干しにする過程を繰り返しているので滋陰作用(潤いを与える作用)が強いとのことです。 春巻きの皮にお好みで人参、ピーマン、ネギでトッピングしていいただきます。
黒いペーストは、黒ごまとハチミツを混ぜたペーストです。黒ごま、ハチミツにはそれぞれ、腸を潤しながら、お通じを良くします潤腸通便作用があるとのことです。中村先生曰く、毎日大さじ2~3匙を1日2回ほど食べると良く、 お好みでトーストに付けたり、ゆでた野菜と一緒に食べても美味しいとのこと。
少し残ったら、茶碗に入れてお湯に溶かして飲むと黒ごまの香りがさらに良く美味しく楽しめるとのこと。

お楽しみのデザートは、リンゴとプルーンのシリアル です。一口サイズのリンゴにレモン汁をからませ、ハチミツ、サラダ油を混ぜ、シリアルとヨーグルト、プルーンの入った器にのせた甘くておいしい一品です。甘いデザートの後には、お口直しの決明子のお茶。はと麦も入っているので非常に飲みやすいです。
日本中医食養学会副会長・理事長の中村きよみ先生より、便秘を改善する中医学的な考え方についてご講義いただきました。何日間も排便が無く、あっても間隔が決まらない場合を一般的に「便秘」といい、慢性化してしまうと便の水分が少なくなり、コロコロとしてしまいます。
消化器官の働きは、食物からの必要な栄養を取り入れ、いらないものは外へ、排出すること。いつまでも出ないと悪いが溜まってしまい良くないとのこと。体質とも関係があり、漢方治療に際しては、実証(腸管が緊張痙攣している場合が多い)、虚証(体の筋肉が弱く便を出す力が弱い場合が多い)との見分けがとても重要とのことです。それに見合う食材もご紹介いただきました。
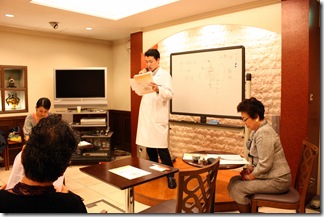
イスクラ薬局日本橋店の今井太郎先生からは、薬局での臨床から見た漢方薬の講義です。
普通に見られる漢方の便秘薬には様々な種類があり、大きく分けて「熱秘」「気秘」「虚秘」「冷秘」などがあり、それぞれの漢方薬があるそうです。お客様の体質に合わせてそれぞれを使い分けているとのこと。漢方薬はやはり弁証論治(べんしょうろんち)が大事だそうです!また、便秘は下剤で出すだけは簡単だけれども「食事・睡眠・運動や排便習慣」も大切とおっしゃっていました。
次回は女性には必見、「ダイエット」のための食養生を、7月に予定しております。
便秘,