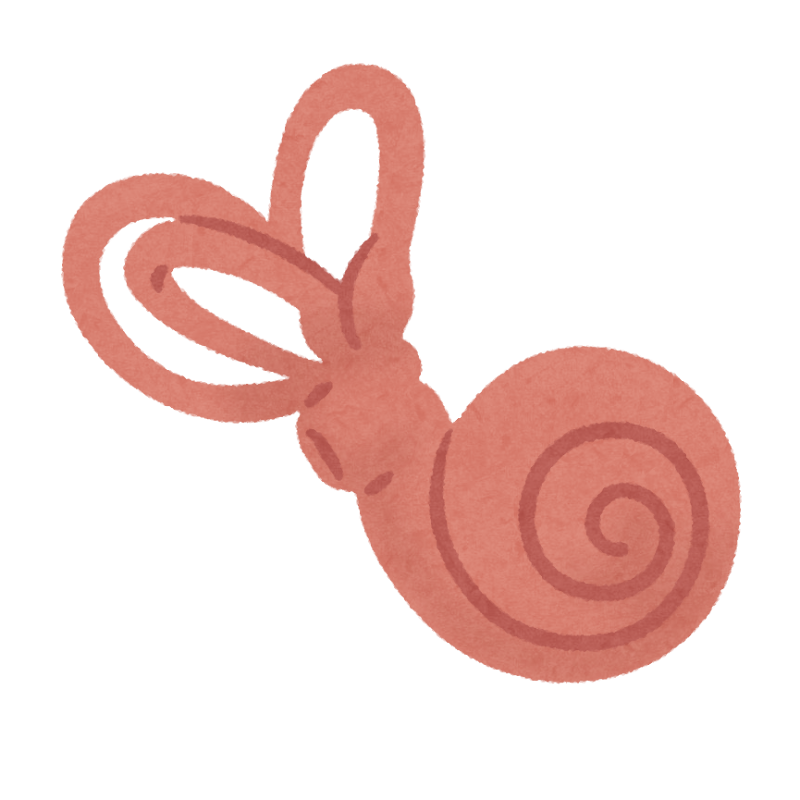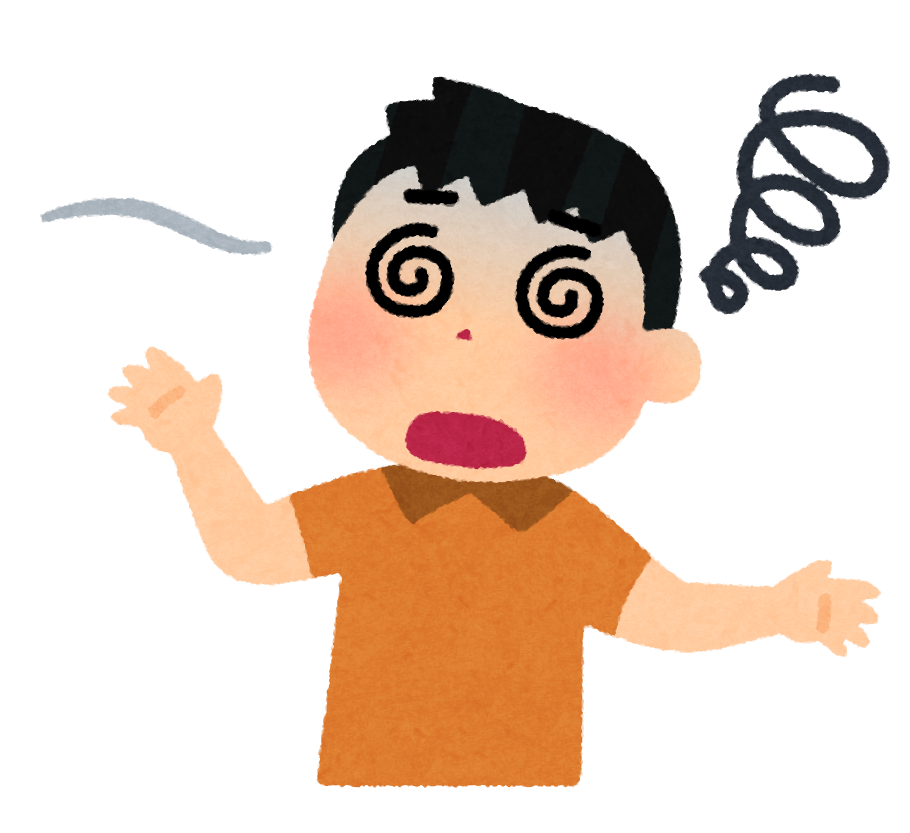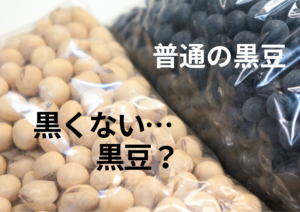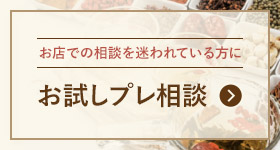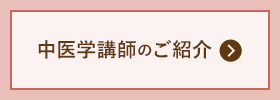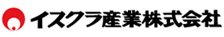こんにちは、丹沢です。
「めまい」について、前回に引き続き今回は中医学的に考えていきます。
【中医学的なめまいの分類】
中医学では、めまい(眩暈:げんうん)は主に5つのタイプがあります。
眩:目がくらむこと
暈:頭がふらふらすること
1.肝陽上亢(かんようじょうこう):ストレスや怒りで「肝」の気が上昇し、頭に熱がこもる。
≪症状の特徴≫
・眩暈
・頭痛(張るような痛み)
・顔面紅潮
・いらいらする、怒りっぽい
・舌苔が黄色い
など
2.痰濁中阻(たんだくちゅうそ):体内の水分代謝異常で「痰」が生じ、気血の流れが阻害される。
≪症状の特徴≫
・眩暈(主に回転性めまい)
・頭が重だるい、ぼんやりする
・胸や胃のつかえ感
・吐き気、嘔吐
・多痰、口の粘り
・舌苔が厚く白い
など
3.瘀血内阻(おけつないそ):外傷や脳血管障害などにより「瘀血」が生じ、気血の流れが阻害される。
≪症状の特徴≫
・眩暈(くらくらする)
・頭痛(刺すような鋭い痛み)
・顔色が暗い
・舌に紫斑や暗色の斑点
・四肢のしびれ
・言語障害(重度の場合)
など
4.気血両虚(きけつりょうきょ):疲労や栄養不足で気と血が不足し、脳への供給が足りなくなる。
→脾不昇清(ひふしょうせい):脾気が不足し、栄養を上に昇げて脳を滋養できない状態。
≪症状の特徴≫
・眩暈
・立ちくらみ
・倦怠感、無気力
・息切れ
・顔の血色がない
・動悸
・息切れ
・舌が淡白、脈が弱い
など
5.腎精不足(じんせいぶそく):加齢や慢性疾患で「腎」の力が衰えて機能が低下する。
≪症状の特徴≫
・眩暈
・慢性的
・虚無感を伴う
・腰や膝のだるさ
・記憶力低下
・夜間尿が多い
・抜け毛や白髪が多くなる
・男性は遺精
など
治療は、原因に応じて「肝を鎮める」「痰を取り除く」「気血を補う」「腎を養う」などを行います。
【まとめ】
2回に渡って、 現代医学と中医学の両方の視点から、めまいについて整理しました。
現代医学では、めまいを「障害部位」によって分類し、前庭性めまい(末梢性・中枢性)と非前庭性めまいに分けます。
一方、中医学では、体内の「気・血・津液」のバランスや臓腑の働きに着目し、肝陽上亢・痰濁中阻・瘀血内阻・気血両虚・腎精不足といったタイプに分類します。
この2つの視点を並べてみると、現代医学と中医学とのつながりや共通点、相違点がわかりやすくなりますよね。
また、めまいは単なる「耳の問題」ではなく、全身の状態や生活習慣、精神状態とも深く関係していることがわかります。
ストレスや食生活、加齢などがめまいに影響するため、予防や改善には「体質に合わせたケア」が重要ですね。