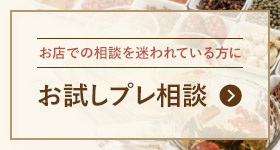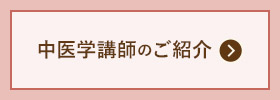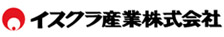この新聞が皆様のお手元に届く頃には、
だいぶ鳴き声も落ち着いている頃でしょうか。
ミーンミンミンミン・・・
という特徴的な声がどこからか聞こえてくると、夏が来た!
という実感が強くなる気がします。
さて、蝉の種類ですが、ミンミンゼミ、アブラゼミ、
ツクツクボウシ、クマゼミ、ニイニイゼミ、ヒグラシ・・・など、
日本には約30 種類の蝉が生息しているといわれています。
西日本と東日本、都市部と森林部、山地と低地では種類が異なり、
鳴き方も鳴く時間帯も実にさまざま。
例えば、ミンミンゼミやクマゼミは午前中、アブラゼミやツクツクボウシは午後、
ヒグラシは朝や夕方、ニイニイゼミは早朝から夕暮れに鳴くようです。
蝉は漢方薬の原料としても有名です。
蝉の羽化後の抜け殻(蝉退;せんたい)を使い、
日本ではアブラゼミやクマゼミの抜け殻を使うことが多いようです。
散風熱、透疹、止痒、退翳明目(たいえいめいもく)、解痙の働きがある蝉退は、
消風散という処方に使われています。
主に、蕁麻疹や痒みのある皮膚湿疹、あせもなどの皮膚症状に使う漢方薬。
中医学的には、“ 風邪(ふうじゃ)”に対して使います。
風邪の特徴は、よく動き変化しやすい、症状が急に現れたり急に治まったりすること。
そう言えば蕁麻疹の症状によく似ていますね。
蝉は幼虫期間として一生のほとんどを地下で過ごし、
成虫になって地上生活する期間はほんのわずかです。
短命のイメージがありますが、実は成虫期間が短いだけで、
昆虫の世界では寿命は長い方ともいわれています。
わずかな期間地上に出て、一生懸命に鳴く姿を見る度に今日一日頑張ろう!
という気分になります。