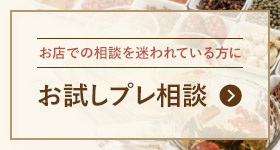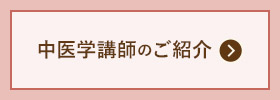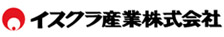さて、突然ですが、
芹、薺、御形、繁縷、仏の座、菘、蘿蔔
これらの読み方が分かりますか?
これらは、“春の七草”といって、七草粥に入れる植物なんですが、いくつ読めましたでしょうか。ちなみに私は、漢方を生業にしておきながら一つも読めませんでした!
ちなみに読み方は、
芹 (せり) =セリ
薺 (なずな) =ペンペン草
御形(ごぎょう)=ハハコグサ
繁縷(はこべら)=コハコベ
仏の座(ほとけのざ)=コオニタビラコ
菘 (すずな) =カブ
蘿蔔(すずしろ)=ダイコン
となります。恥ずかしながら蘿蔔(すずしろ)なんて、「"ぶどう"かな??」なんて思ったぐらいです(ちなみにぶどうは『葡萄』と書きます)。「春の七草」とか「七草粥」などとは昔からよく耳にしましたが、それらが何を指しているのは、このブログを書くために調べて初めて知りました。
ということで、今日はこの、『七草の行事』について、書いてみたいと思います。七草は、いったいいつから始まって、何が由来なのでしょうか?そして、『七草』たちにはどんな力があるのでしょうか。
某大型スーパーで鉢ごと売っていた「七草」です。
七草の由来
『春の七草』は、日本に古くからある、年初めに雪の下から芽を出した若草をつむ「若菜摘み」がその原点と考えられています。そこに、中国の「七種菜羹」という7種類の野菜を入れた羹(あつもの、とろみのある汁物)を食べて邪気を払い、無病息災を祈るという習慣がかさなり、定着していったようです。
昔は、前日(1月6日)の夜にまな板に載せて「七草なずな 唐土の鳥が、日本の土地に、渡らぬ先に、合わせて、ストトントン」(地方により多少の違いがあり)と囃し歌を歌いながら包丁でたたき、7日の朝に粥に入れて炊いていたようです(wiki参照)。この歌から見ても、中国(唐)の習慣と日本の風習とまじわりできた習慣じゃなかろうか?という想像ができますね。
春の七草の効能
手もとの資料によると、
セリは余分な熱をとり、おしっこやおりもののトラブルに良いとされ、
ナズナは、胃腸を元気にし、むくみや胃の不快感、目の充血などにも良いようです。
オギョウ(別名 ははこぐさ)は、咳を鎮め、痰を出すのに良く、
ハコベラは利尿によく、産後の浄血によいとされ、
ホトケノザは胃腸に良く、
スズナ(かぶら)やスズシロ(だいこん)は解毒や、消化不良によいとされています。
春の七草は、お正月料理で疲れた胃腸にはぴったりのお粥といえますね。
ちなみに、、、
春の七草はご存知の通り1月7日ですが、これは旧暦の1月7日の事を指しています。となると、旧暦の正月は2月初旬ですので、七草粥は本来、2月初旬に食べられていたようです。実際にこれら『七草』も、2月ごろ、春先に食べごろを迎える植物たちですので、今スーパーに並んでいる『七草粥セット』なるものは温室栽培のものや、中には多少違った植物が入っているものあるようです。
元々は邪気を払い無病息災を祈るための粥でしたが、正月のごちそうで疲れた胃腸を癒すため、溜まった毒を除くためという意味合いもあります。私、年末年始は実家に帰っていたのですが、肉、魚、魚介と食事がとにかくタンパク質だらけで、とっても美味しくて嬉しいのですが、胃腸にはかなりの負担になってしまったと思います。緑たっぷりのおかゆは解毒の力に優れていますし、おかゆ自体も疲れた胃腸を回復させる絶好の養生食ですし、正月太りも改善してくれる(かもしれない)ので、是非七草粥を楽しんでください。
春の七草と言えばこの歌、時は南北朝時代の四辻の左大臣(よつつじのさだいじん)が源氏物語の注釈書「河海抄(かかいしょう)」の記載から良く知られる一句をご紹介します。
『芹なずな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草』
『春の七草』はこのように歌になったことで世に広く知れ渡ったといわれています。
皆様も是非、この先人時の知恵を活かし、ご養生くださいませ。