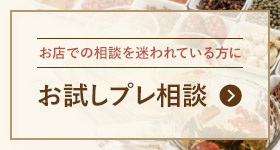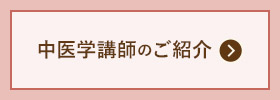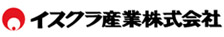今年の鏡開きは1月11日でしたが、皆さん、お餅は食べられましたか?
関東で餅と言えば角餅、関西は丸餅という決まりというか、風習というか、そういうものがあるのですが、皆さんのお家はいかがでしょうか。私の実家は今北海道にあり、餅は各餅のですが、父は奈良、母は大阪出身で、私も小さいころは奈良に住んでいましたので、小さいころのお餅の記憶は丸い丸餅でした。関西以外でも鏡餅は勿論丸いお餅ですね。
私の生まれた奈良の大和高田というところでは、子供が生まれると近所にお餅を配る風習があり、男の子だとおでこに赤い字で「大」、女の子は「小」と書いて、お披露目するのですが、餅は大きいのをいくつかと、小さいのを沢山つくってもらい、その餅(大きいもののみ)に、大もしくは小と食紅で書いたものを用意していました。
祝い事には餅がつきものですが、それは何でなんでしょうか。
餅つき
お正月や年末にお餅つきをやった方も多いと思います。親戚や近所の方々など、沢山集まってつくお餅は楽しいし、美味しいですよね。
餅の歴史は古く、古墳時代(6世紀前後)の遺跡から蒸し器の様なものが見つかっており、このころから食物を蒸して食べる「蒸し料理」が出現したとされ、そのうち米も蒸すようになって、「餅」も食べられるようになったのではと考えられています。平安時代ごろからは朝廷が推奨した稲作信仰とも相まって、さらに餅文化は広がりを見せます。餅を作るには、ある程度量がないと難しいので、大人数が集まるときの行事となっていったようです。そういった経緯から年中行事や神事などと相まって、餅は「祝いもの」として扱われるようになってきたようです。世界的に見ると、中国の一部(広東省、福建省、江西省など)、台湾の一部の民族、そしてラオスの一部の民族でも、餅つきの文化は今でも残っているそうです。
餅文化は、朝廷があった京都を中心として、近畿地方で古くから根づいており、その後東にも広がったと考えられています。その辺に関西の丸もち、関東の角もちの違いになった原因がありそうですね。
餅は元気の元!ただし胃腸が弱い人には不向き!
ところでこのお餅、「力うどん」なんかもあるように、「元気が出る食べ物」という認識が一般的かと思います。中医学から見ても、その見識は間違っておらず、明代(1578年ごろ)に書かれた薬物についての書物、『本草綱目』(ほんぞうこうもく)にも、「益気暖中」(えっきだんちゅう)といって、胃腸を温めて元気をつける食べ物と記載されています。手元の資料でも、餅は、「脾(消化器系)の働きを高め、胃を温める効果があり、慢性的な疲れの改善に有効」と書かれています。さらにもち米は温性で、身体を温める力があるので、冷え性や冷えからくる下痢にも有効です。
ただし、餅は粘りけが強く、消化吸収が遅いので、食べ過ぎには注意しましょう。胃腸機能低下時や老人、子供などでは胃腸への負担が大きくなってしまうこともあるので、食べ過ぎには十分注意してください。
餅
【性味】 温性、甘・苦
【帰経】 肺、脾
【効能】補中益気・温中止痢・止消渇・止汗
【注意】粘っこくて消化しにくいので、小児や病人はひかえめに。常食すると動悸や皮膚に炎症を起こしやすく、眠気がしやすくなる。酒と一緒にたべると、酔いが解消しにくくなる。(本草綱目)
餅は美味しいけど、気をつけよう
今年の鏡開きは1月11日でした。鏡開きは、お供えしたお餅を神様に感謝しながら食べ、その年の無病息災を祈るという風習です。鏡開きを木槌で行うのは、「餅を切る」という行為が「切腹」を連想させ縁起が悪いということから来ているそうです。しかし、昨今の鏡餅や餅は、真空パックで包装されているので、11日を過ぎても昔のお餅のようにカチカチにならず、木槌では割れないですね。
後、カビが生えた餅もあまりみることが無くなりましたね。亡くなったおばあちゃんは、カビの部分だけ取って雑煮にしてよく食べていたもんですが、カビの根は見えない所にも伸びていて、食べてすぐお腹を壊したり中毒症状を起こすわけではないんですが、カビ毒というのは発がん性も確認されているので、できれば食べないほうが好ましいです。
ちなみにカビの毒は、熱に強く、焼いても煮ても無毒化されないそうですので、やっぱり食べないほうが良いですね。昔の人は食べ物をとっても大事にしてたので、餅を捨てるなんて概念ははなっから持ち合わせていないようでした。それにずっと食べてきたおばあちゃんはガンにはならず90歳ぐらいまで生きて大往生でしたしね。
ということで、身体を元気にするお餅ですが、胃腸が弱っているときや、お子さん、お年寄りはお気をつけお食べください。特にお年寄りは、毎年正月に喉に詰めてなくなる事故があります。そういった事故を防ぐためにも、お餅は小さく切って食べるようにしてくださいね。