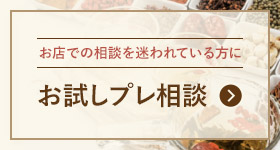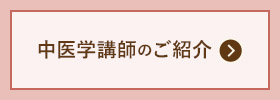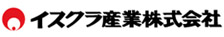30代になると、生理周期が短くなるなどの生理不順を感じる女性が増えてきます。これには様々な要因が関わっており、体質や生活習慣による影響も大きいです。 もし数日月経が早くなっても他に不快な症状がなく、一周期だけの症状でしたら心配することはありませんが、何周期も続き、出血量が多いなどの症状が現れたら、子宮筋腫などの婦人科疾患の可能性もありますので、その際は婦人科の受診をお勧めします。 漢方薬は、体のバ …
続きを読む漢方百科最新記事一覧
- New Topics
- 役に立つ中医学の知恵などをご紹介!
30代で生理周期が短くなった場合に適切な漢方薬を紹介
生理前のニキビ改善に効果的な漢方薬を紹介!肌荒れに悩んでいる方へ
毎月の生理前になると、ニキビや肌荒れに悩まされる女性は少なくありません。ホルモンバランスの変化が原因となることが多く、なかなか改善しにくいのが現状です。 そのような中で、漢方薬は体質改善を図り、根本からニキビとそれにまつわる諸症状を和らげる助けとなることがあります。本記事では、生理前のニキビ改善に効果的な漢方薬について詳しく解説していきます。 生理前にニキビができやすい理由 実はニキビは、肌の表面 …
続きを読む夏バテに効果的な漢方薬を紹介!改善・予防法も
夏バテは、暑さや湿気などの気候条件が原因で、身体の機能が低下しやすくなる状態です。特に夏季に多く見られ、疲れや倦怠感、食欲不振などの症状が現れます。 実は漢方薬は、夏バテの改善や予防に効果的な選択肢の一つです。本記事では、夏バテの主な原因や症状、そして夏バテに効果的な漢方薬について詳しく解説します。 夏バテの主な原因と症状 まずは夏バテの主な原因とその症状を解説します。 原因 夏バテの主な原因には …
続きを読む紫外線が原因の湿疹とは?症状・対策を解説
紫外線は日常生活において身近な存在ですが、その影響は皮膚に深刻な問題を引き起こすことがあります。特に紫外線が原因となって湿疹が発生することがあります。 この記事では、紫外線が原因の湿疹について詳しく解説し、その特徴、原因、対策について紹介します。 紫外線が原因の湿疹の特徴 紫外線が原因の湿疹は、皮膚炎の一種であり、日光による刺激が皮膚の過敏な反応を引き起こして発症する場合があります。ここでは、紫外 …
続きを読む老廃物が溜まりやすい人の特徴って?効果的な対処法も解説
老廃物が溜まりやすい人の特徴やその対処法について知りたい方々へ、この記事では詳細に解説していきます。 老廃物の概念から、なぜそれが溜まりやすいか、そして効果的な対策まで幅広くカバーしています。健やかな生活を送りたい方や老廃物が気になる方は、ぜひ参考にしてください。 老廃物とは何? 老廃物とは、身体内で生じた不要な成分や代謝物のことを指します。生体内での代謝活動や細胞の生産・修復などによって生じた物 …
続きを読む熱中症の正しい予防法を解説!おすすめの飲み物・食べ物も紹介
夏の暑さが増すにつれて、熱中症の危険が増します。正しい知識と適切な対策を取ることで、熱中症を予防することができます。 本記事では、熱中症の定義や症状、そして効果的な予防法について解説します。また、熱中症予防に効果的な飲み物や食べ物も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 そもそも熱中症とは? 熱中症は、体内の熱調節メカニズムが失われ、身体が高温多湿な環境によって過熱されることで引き起こされる疾患 …
続きを読む自律神経が乱れている時の症状って?原因や整える方法も
自律神経が乱れると、身体や精神にさまざまな症状が現れることがあります。ストレスや不規則な生活、運動不足などが原因となり、自律神経のバランスが崩れることがあります。 本記事では、自律神経が乱れている時の主な症状や原因、そして整える方法について解説します。 自律神経が乱れている時の症状 自律神経が乱れていると、身体的な症状と精神的な症状が現れることがあります。 身体的症状 【心臓と循環系】 自律神経の …
続きを読む春は鬱病になりやすいの?原因や効果的な対策を解説
春になると暖かい陽気や新しい生命の息吹が感じられる一方で、一部の人々にとっては鬱病の症状が現れる時期でもあります。 この記事では、春に鬱病がなぜ起こりやすいのか、その原因や効果的な対策について詳しく解説していきます。 春は鬱病になりやすい? 春が鬱病になりやすい季節とされる理由には複数の要因が関係しています。以下にその一部を解説します。 季節性の影響: 春は冬から急激な気温の上昇や日照時間の増加な …
続きを読む胃腸が弱っている時の主な症状を解説!改善方法も
GW中にごちそうを食べ過ぎてしまい、今も胃腸のコンディションが悪い方も多いかと思います。 この記事では、胃腸が弱っている時の主な症状、そして改善方法について詳しくご紹介します。 胃腸が弱っている時の主な症状 胃腸が弱っている時にあらわれる主な症状を以下にご紹介します。主なものとして、食欲不振、胃もたれ、腹痛、下痢、便秘、吐き気、嘔吐、食事後の消化不良感などがあります。 食欲不振 食欲不振は、食べ物 …
続きを読む胃腸の症状に効果的な漢方薬を紹介!胸やけ・食欲不振など
病院に行くほどではないけれども、気になる胃腸のトラブル。 胃腸が健やかであれば、毎日美味しく食べて快適に過ごすことができます。その場しのぎではなく、根本的な対策を考えてみましょう! この記事では、胃腸トラブルの主な原因、胃腸の症状に効果的な漢方をご紹介します。 胃腸トラブルの主な原因 胃腸トラブルの原因はさまざまであり、個人や状況によって異なる可能性があります。以下は一般的な胃腸トラブルの主な原因 …
続きを読む