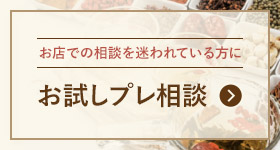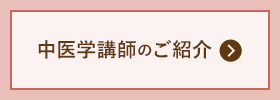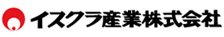こんにちは、丹沢です。
皆様、「夏季うつ」という言葉を聞いたことはありますか?
夏季うつは、梅雨から夏の時期にかけて起こる季節性の心身の不調です。
今回は、夏季うつについて中医学的な視点を交えてお話しします。
【主な症状】
• やる気が出ない(気虚)、気分の落ち込みといった精神的な不調
• 食欲不振(脾気虚)
• 不眠
夏季うつは、夏バテとは異なり体力が回復してもこれらの精神的な不調が改善しにくいのが特徴です。
【主な原因】
• 暑さ(暑邪)や湿気(湿邪)によるストレス
• 日照時間の増加に伴う生活リズムの乱れ
【中医学的な原因の解説と対策】
中医学では、夏季うつの原因を「脾(ひ)」と「心(しん)」の機能低下と考えます。
●脾の機能低下
暑さ(暑邪)や湿気(湿邪)、冷たい飲食の摂りすぎ(陽気の損傷)によって、気の生成がうまくいかなくなります。
その結果、元気がなくなり、疲れやすさやだるさといった症状が現れます。
また、汗をかくことで水分やミネラルとともに「気」も漏れ出し、さらに体力が低下します。
●心の機能低下
夏は「心」が活発になる季節ですが、同時にダメージを受けやすい時期でもあります。
「汗は心の液」とも言われ、汗をかきすぎると「血」が消耗し(汗血同源)、「心」に負担がかかります。
これにより、「心は精神を主る」とされているため、不安・不眠・多夢といった精神症状や動悸・物忘れ・眩暈といった症状も出やすくなります。
●対策
これらの症状に対しては、「心血」や「脾気」を補う漢方薬の服用が効果的とされています。
気になる方は、体質にもよりますので必ずご相談ください。
最後に、中医学では「心身一如(しんしんいちにょ)」という考え方があり、心(こころ)と身体は一体であり、互いに強く影響し合うとされています。
つまり、心と身体の両方を整えることで、夏の季節も健やかに過ごすことができます。
シンシン(星星)と共に、心身ともに健康に過ごしましょう!