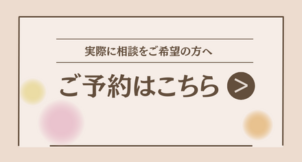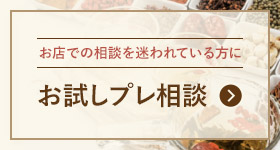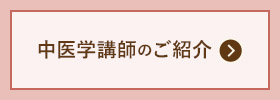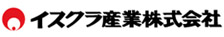高血圧症とは?
血圧が正常よりも高い状態を高血圧と言いますが、何回繰り返し測定しても最高血圧(収縮期血圧)140mmHg以上、または最低血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上となると、高血圧症と診断されます。注意すべきことは、高血圧症では自覚症状がほとんどあらわれないケースがあることです。「静かな殺し屋」と言われるゆえんです。
高血圧の状態が長期間続くと当然のことながら常に血管に圧力がかかり、その結果血管が厚く、硬くなります。いわゆる動脈硬化であり、これが脳卒中(脳出血、脳梗塞)、心筋梗塞、腎硬化症、腎不全など、合併症の原因となります。また心臓も高血圧に対応しようとするため、心肥大、心不全に発展することもあります。つまり高血圧状態をそのままにしておくとこれらの合併症になる可能性が高くなるので、血圧を正常に戻すことが必要となります。高血圧は、合併症への導火線になるところが恐ろしいのです。
高血圧症には、大きく分けて本態性高血圧と二次性高血圧(別の病気が原因となるもの)があります。ほとんどのケースは、原因がはっきりしない本態性高血圧ですので、ここでは本態性高血圧についての説明をします。これは、生活習慣や遺伝的要因が関与しているため生活習慣病のひとつといえます。原因としては、例えば、塩分過剰摂取、脂肪過剰摂取(肥満)、飲酒過剰、ストレス、喫煙、運動不足、過労、感情の激しい変化などが考えられます。これらの原因により、心臓が送り出す血流量の増加、血管弾力性の低下、血管内が狭くなり血流低下、血液粘性度の増加などが起こり、結果的に高血圧が生ずると考えられています。
高血圧の中医学的考え方
 上記のように、高血圧は様々な要因がからみあっていて、原因を明確にするのは困難なことが多いのが普通です。 中国医学では、原因が積み重なった結果、高血圧に結びつく代表的な状態として以下のようなものが考えられています。
上記のように、高血圧は様々な要因がからみあっていて、原因を明確にするのは困難なことが多いのが普通です。 中国医学では、原因が積み重なった結果、高血圧に結びつく代表的な状態として以下のようなものが考えられています。1.血瘀(けつお):
血液循環障害のことを言います。
血管にコレステロールや老廃物がたまるなどして、血液の正常な運行がさえぎられ、停滞を起こすために生じる状態をいい、高血圧の直接的原因となります。
2.痰湿汚濁(たんしつおだく):
水分代謝が悪くなり、必要のない水分や老廃物がたまってしまう状態をいいます。
塩分の過剰摂取により水分も多く摂取してしまい、むくみが生じるのはこの代表例といえます。余分な水分が滞留することにより、組織細胞に不必要な圧力がかかることになります。
3.肝火上炎(かんかじょうえん):
精神的なストレスにより気がうっ積する状態が続き、イライラ怒りっぽい状態になることをいいます。
中国医学で「肝」は気の巡りと深く関連があるとされており、気が滞ることにより血流も悪くなり、高血圧を導きます。高血圧以外にも、頭痛・めまい・強い耳鳴り・顔面紅潮・目の充血などもあらわれたりします。
4.陰虚内熱(いんきょないねつ):
加齢・ストレス・肉体疲労・慢性病などが原因となり、体内の陰(体内の潤い成分=水のイメージ)、特に「肝」と「腎」の陰が消耗した結果、相対的に陽(火のイメージ)が優勢になり、内熱が発生する状態をいいます。
目の疲れ・弱い持続性の耳鳴り・足腰のだるさ・手足のほてり・寝汗などがよくみられます。
実際には体質などにも左右されるため、ある病態が進行して上記のような症状に至ることもありますし、上記の状態がさらに進んだバリエーションも考えられます。また、これらのいくつかが組み合わされることもあるので様々な病態のパターンがありますが、代表的には上記のようにまとめられるでしょう。
(次回は治療の実際例・予防などについて解説します)
高血圧,