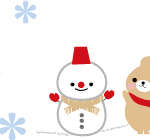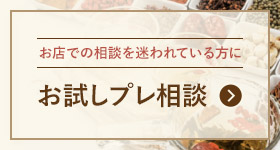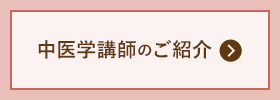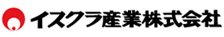こんにちは。実習生の志賀です。
中野店では約1ヶ月半お世話になっています。
春の陽気が気持ちよく外に出れば梅やハクモクレンなど季節の花々が芽吹き、花を咲かせています。
桜もそろそろ開花しそうですね。
私の家の近くではもう咲いているところもあります。
暖かな日差しと、のびのびとした草木を眺めていると心もじんわりほぐれます。
春は中医学では肝(カン)の季節といわれています。
肝は私たちの気持ちのコントロールをしたり、血を貯め必要なところに巡らせる役割があります。
肝が弱ってしまうと、
・めまい
・イライラ
・気分の落ち込み
・ドライアイ
・まぶたの痙攣
・月経のトラブル
などの症状が出やすいです。
どの様な時に肝が弱るかというと、ストレス、目の酷使、睡眠不足、血の不足などが挙げられます。
揺れ動く心や身体に気付いたら、生活や食事を少し工夫すると、過ごしやすくなるかもしれません。
日常に取り入れやすい生活養生と、食養生を少しご紹介しますね。
<生活養生>
肝はのびのびとしていることを好みます。
なので肝が元気である為には、身体も心ものびのびとすることが大切です。
少しの時間で構いません、
ゆっくり深呼吸しながらお散歩してみませんか?
太陽の暖かいエネルギーを背中でたっぷり感じながら陽気をチャージ。
歩くことで気血のめぐりも良くなりいい事ばかりです。
服装もぎゅっと締め付け過ぎずに、ゆったりとしたものがおすすめです。
<食養生>
・なんだが心がどんよりしていたら―
肝を元気付けてくれる酸味のある食材がおすすめです。
レモン、みかん、グレープフルーツなどの柑橘類、お酢など。
パクチー、三つ葉などの香味野菜も良いですね。
・イライラが鎮まらないそんな時は―
苦味のある食材がおすすめです。
春が旬のふきのとう、タラの芽、ウド、菜の花など。
春の気持ちよさを存分に楽しむために、少しずつ取り入れてみてくださいね。
春に起こりやすい不調をあげてみましたが、不調が出る原因は1つではありません。
季節の変化と、その時の体質が合わさることで不調症状が出でくる場合もあります。
そんな時は中野店に相談にいらしてください。
私は実習が終わってしまいますが、中野店の先輩方は細やかな気遣いが素晴らしく、かけて下さる一言があたたかく励まされました。
私も先輩方のようにお客様に寄り添った接客ができるようにこの経験を活かして頑張ります。
ありがとうございました!