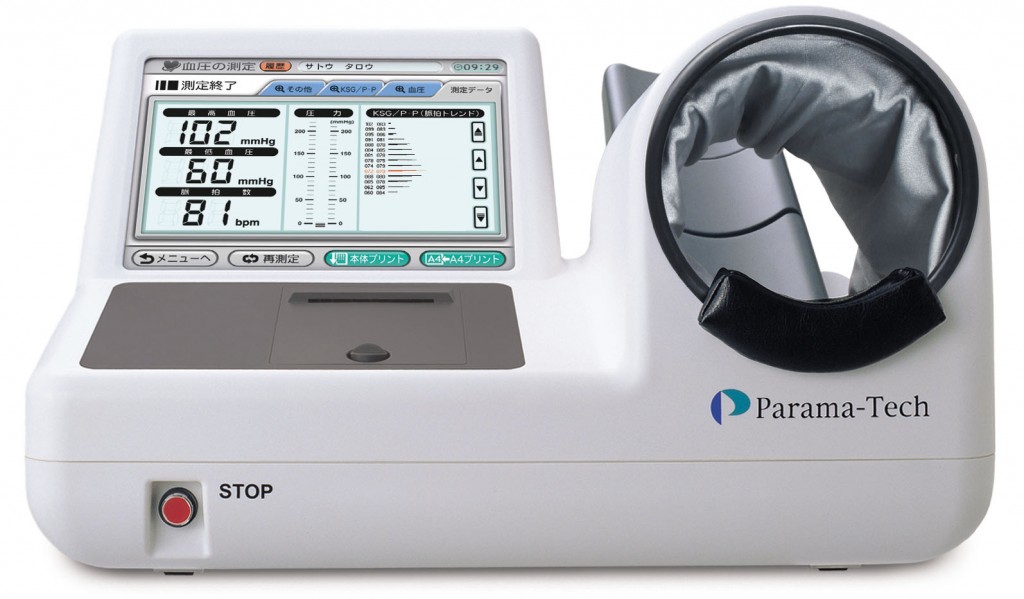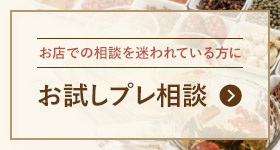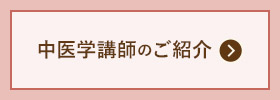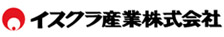こんにちは櫻井です。
ずっと続いた雨が開けたら、秋、来ましたね。今年は確かに暑かったですが、なんだか残暑も厳しくなく、拍子抜けした感があります。最近は朝夕は若干肌寒くなってきましたね。お店でも咳や喉の痛みのお悩みが増える頃です。ということで、去年からこのブログを御覧頂いている方にはもうおなじみ、梨の季節がやってまいりました^^
では今年も、肺によく、咳に良い【梨のはちみつを使った薬膳デザート】をご紹介します。
【梨とはちみつの潤肺デザート 氷糖燉梨子】
① ヘタの部分を蓋になるように切っておく。
② 実の部分の芯をスプーンでくりぬき、はちみつ(大1)とお水(大1)、生姜スライスを1かけ入れる。
③ ①の蓋をして、お皿に入れて蒸し器で40~50分蒸す。柔らかくなり皮にヒビがはいってきたら完成。
*カゼの初期で若干肌寒さを感じる場合は、生姜がいいです。味付けにシナモンや棗、レーズンを入れてもおいしいです。シナモンは大熱といって温める力が強いので、喉トラブル時は避けて、それ以外ではスパイス程度に極小量にしましょう。
*蜂蜜の代わりに氷砂糖(3つぐらい)も良いです。本来の薬膳は氷砂糖でつくります。氷砂糖には余分な炎症の熱を沈める力があります。喉のトラブル解消としての効果を重視するなら、氷砂糖がオススメ。
**氷砂糖の代わりに【板藍のど飴】を入れてみると更に良いと思います!
潤いたっぷりでこれは喉によいですよ~~
あつあつで食べてくださいね。ジュースもしっかり飲みましょう。これはジュースというより咳止めシロップです。のどにとってもよいですよ。私も早速、家に帰って作ってみました。切ってくりぬいてはちみつと水を入れて蒸すだけ!すっごく簡単!
梨とはちみつの中医学的効能
梨
【性味/帰経】
寒、甘、微酸/肺、胃
【働き】
生津潤燥:潤いを生み、渇きを癒す。
清熱化痰:余分な熱をとり、痰をなくす。
除消渇:渇きを改善する。糖尿様の症状(渇き)を改善する。
【注意】
胃腸機能低下時や軟便、下痢傾向の方、妊娠中の方、小児、高齢者では、冷やす性質の梨は生のままたくさん食べないようにしましょう。
はちみつ
【性味/帰経】
平、甘/肺、脾、大腸
【働き】
補中:胃腸を元気にする。
潤燥:保湿作用で乾燥を防ぐ。
止痛:痛み(主に胃腸)を止める
解毒:毒を消す
【注意】
胃腸機能低下時や軟便、下痢傾向は控えてください。
Honey / Siona Karen
氷砂糖
【性味/帰経】
平性~涼性/脾肺
【働き】
補肺潤燥:鼻、気管支、皮膚などに潤いを与える
化痰止咳:咳を止めて痰を無くす
降濁解毒:解毒する

Demerara sugar crystals / Ervins Strauhmanis
薬膳とはちょっと離れてしまいますが、洋ナシをオーブンで焼いたものもおいしいですよ。
【洋梨とはちみつ洋ナシ・洋風バージョン】
用意するもの
洋ナシ:4つ、ブランデー:60ml、はちみつ:大匙3杯、水:大匙3杯、無塩バター:大匙2杯 賽の目切り、シナモン:1本、クローブ:4つ。
①洋ナシは縦に半分に切って芯をとる。
②オーブンを400℃に熱しておく。
③オーブン皿に切った面を下にしておく。
④オーブン皿に、ブランデー、無塩バター、シナモンスティックとクローブを加える
⑤400℃のオーブンで5-10分焼く。

Baked Pears with Honeyed cinnamon and brandy / CGehlen
去年紹介したら沢山の方から作った報告を頂きました。温かい梨というのは、なんとも不思議な味と触感になりますが、これが意外と美味しいんです。ぜひお試しください。