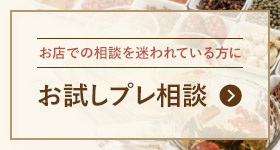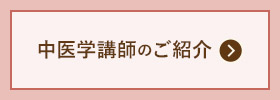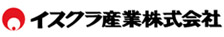こんにちは、柳沢です。
先週の日曜日に、『プレミアム不妊症講座』で13時~17時まで、不妊症の勉強会に参加してきました。メイン講師は中野店に勤務されている。河野康文先生です。河野先生は、西洋医と東洋医の両方のライセンスをもっていらっしゃるすごい先生で、不妊症に対する漢方の使い方で、中国で行われていた*周期調節法’(月経周期にあわせてお薬を調整する方法)を1980年代に日本に広めた第一人者の先生。東京以外からも東北エリアなど様々な場所から講義を受けに来られていました。(*周期調節法とは、月経期、卵胞期、排卵期、高温期の4つにわけて漢方を飲み分けるという方法です)

今回の内容はメインは二分法に関してです。(月経周期を月経期とそれ以外と考えて服用する方法)河野先生の多くの臨床経験から、現在実践されている方法です。
4つにわける周期調節法を行ってた河野先生ですが、長いご経験の中で、低温期、高温期がはっきりしない方に関しては、この方法はやりにくい場合がある、またお客様も薬の飲みわけが難しい、などといったことがあり、現在は月経期とそれ以外で漢方を飲み分ける二分法というシンプルな方法を実践し、良い結果に繋がっているということで、この二分法に関して私たちに教えて下さいました。
漢方のことはもちろんですが、西洋医学的なこと、また不妊漢方相談で私たち漢方薬局ができること、など、多岐にわたる内容です。妊孕性(もともと妊娠力があるか)の見方、血の巡りを良くすることの重要性、そして補腎薬など漢方薬の効果的な使い方、症例検討など盛りだくさんでした!一部抜粋してご紹介します。
1 妊孕性に関して
よく、妊娠は年齢に関係するといわれています。その通り、年齢はとても重要な因子です。しかし、妊孕性を(妊娠のしやすさ)をみていくのは年齢だけではなく、
●身長、体重からBMIをみる(18.5~25以内か)
●月経のサイクルをみる
●不妊の期間はどのくらいか、妊娠したことはあるのか
なども非常に重要。
2 瘀血薬に関して
不妊に悩む患者さんを中国のある病院で観察した所、100%内性器の瘀血(血の巡りの悪い状態)が認められたそうです。ですので、瘀血性の疾患がある方は要注意。(子宮筋腫、卵巣膿腫、子宮内膜症、PCOS、生理痛など)また、婦人科の瘀血には特徴があって、むくみがある(特に排卵誘発剤など使用中の方)ため、湿をとりながら血行を良くする対策をすることが重要。
3 補腎薬の使い方
不妊症の場合、一般的な腎虚(耳鳴り、白髪、目のかすみ、腰痛など老化に伴う症状)などがないことが多いが、妊娠しにくいタイプは生殖能力が低いことが多いので、しっかり補腎精(精力を補う)は重要。
今回の講座のメインである、月経の周期を2つにわけていく、二分法に関しては以前に河野先生に教えていただき、実践していた内容でしたが、またこうして講義として聞くと再度勉強になりました。
私は、実際のカウンセリングでは、4つにわけた周期調節法、2つにわけた二分法、わけない方法など、その方の状況(お体の状況、ご予算等)にあわせてご紹介していますが、やはり周期があまりわからない方が多いので、4つにわけた周期調節法でなく二分法や二分法に近い内容でお薬をご紹介することが多いです。
漢方の使い方も様々なやり方があるので、日々勉強し、これからも一番良いであろう方法を目の前にこられたお客様にご紹介したいと思っております。