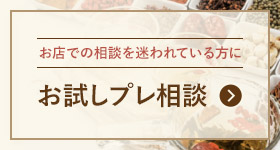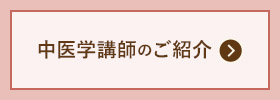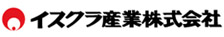前立腺肥大症は、50代から60代以上の男性に多くみられる病気です。30代から、認められ、60代では10人中7人まで見られます。
続きを読む気になる病気
- 中医学的な処方で改善に導きましょう。
前立腺肥大と漢方
後鼻漏(こうびろう)と漢方
後鼻漏とは、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、アレルギー性鼻炎、風邪などに伴う細菌性鼻炎などが原因で、鼻水が病的に過剰分泌された状態です。過剰分泌された鼻水が、咽の方へまわって落ちてゆく場合を「後鼻漏」といいます。
ちなみに、鼻の前を鼻水が流れる場合は前鼻漏といい、本人の自覚症状がはっきりしています。これに対し、後鼻漏は痰と混同されやすく、長引く咳の原因になることも少なくありません。
動脈硬化(2)
前回は、動脈硬化は瘀血が原因とご紹介しました。 今回は瘀血に至る原因についてご紹介します。原因別に以下の6タイプに分けられます。 瘀血の対策は活血化瘀薬が有効と前回お話しましたが、タイプ別に併用する代表的なものもご紹介します。 ①元気不足の<気虚タイプ> 主な症状:息切れ、動悸、疲れやすく元気がない 原因:虚弱体質、過労、心臓のポンプ作用の低下 活血化瘀薬と併用するもの:薬用人参、西洋 …
続きを読む動脈硬化(1)
動脈硬化血管の老化現象で、年齢とともに内壁に汚れが溜まったり血管自体の弾力性がなくなり硬くなる症状です。症状が進行する血液が固まりやすくな血栓が出来やすくなります血栓が冠状動脈でつまると心筋梗塞、脳動脈でつまると脳梗塞が起きます血管の弾力が無くなるため血管が破れやすく血しやすくなります。血圧が原因の…
続きを読む副鼻腔炎と漢方
「蓄膿症」という病気は? 細菌やウイルスの感染により副鼻腔の粘膜に炎症がおこり、鼻腔と副鼻腔をつなぐ孔(あな)が塞がれることで副鼻腔に膿(うみ)が溜まった状態を急性副鼻腔炎といいます。 急性副鼻腔炎を放置してしまったり、何度も繰り返すと慢性副鼻腔炎、つまり、蓄膿症になってしまいます。近年、花粉やハウ…
続きを読む膀胱炎について
「膀胱炎」という病気は? 膀胱炎は尿路感染症(腎臓・尿管・膀胱・尿道などの感染症)の1つで、膀胱の中に細菌が感染、増殖して炎症を起こした状態をいいます。原因となる細菌は、ほとんどが大腸菌で、その他にセラチア、ブドウ球菌などです。 女性に多いのはナゼ? 女性に膀胱炎が多いのは、一言でいうと体の構造に原…
続きを読む眼精疲労
インターネットの普及で家庭にも一台パソコンがある時代になりました。家にパソコンがないという人でも、 職場や学校で一度は触れたことのある人は少なくないはず。マウスを「カチッ」とクリックするだけで、 様々な情報を手に入れることができます。子供の頃にテレビゲームに夢中になったように、 画面を見つめていると…
続きを読む口内炎について
口内炎とは口内や舌の粘膜にできる様々な炎症のこと。症状の違いによって分類され、代表的なものにびらん性口内炎・潰瘍性口内炎・アフタ性口内炎があります。 発生の原因としては食べ物や矯正装置など物理的刺激による損傷のほか、細菌やウィルスの感染など口中の原因によるものと、慢性の胃腸虚弱・免疫力の低下・ビタミ…
続きを読む水虫の原因は?かかと水虫も治す漢方とは?
気温が上がってきたとたんに足が痒くてたまらなくなる水虫。暑くてジメジメした季節になると水虫に悩まされる方が増えますね。 昔は中年男性の病気と思われていましたが、最近では革靴、ブーツなどの蒸れやすい靴、パンストの普及などによって、女性にも多く見られるようになりました。また、ペットなどからの感染も増え、…
続きを読むストレス社会の救世主!? 「抑肝散(よくかんさん)」とは?
抑肝散の原典の『保嬰撮要』(16世紀)は乳幼児に対する治療について記されたもので、乳幼児のひきつけや夜泣き・歯ぎしりなどにつかわれたものでした。また、チック症・てんかん、パーキンソンなどによる痙攣、イライラ・不眠・精神不安等の心因性の疾患にも用いられる応用範囲の広い漢方薬です。現在では、認知症の行動・心理症状の改善やQOL向上のために用いられ、その薬理作用の研究も進んでいます。 Burnout & …
続きを読む