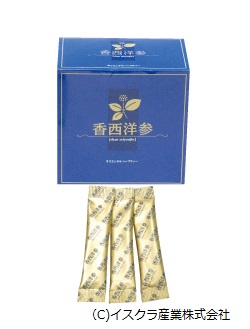こんにちは!車田です
先日、関東は梅雨入り。と発表がありましたね。
皆さん、梅雨は好きですか??
…好きな日本人はそんなに多くないのではないでしょうか?
なぜ、日本人は胃腸が弱い人が多いのか
この時期、体のむくみがいつもより気になったり、食欲がなくなったり、お腹を下しやすくなったり…
そんな症状でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
実はこれ、日本が島国であることとも関係します。

体の水分代謝を担っている臓腑は3つ。脾(ひ:胃腸などの消化器系)・肺・腎です。
特に脾は、体にとって必要な『きれいな水』と不要な『きたない水』の仕分けをしています。
そして、この臓腑は湿気が大の苦手。
湿のせいで脾の機能がダウンすると、ますます湿をためやすくなります。
日本は島国、周りを海に囲まれているため、ただ息をしているだけで湿気を吸い込む量が大陸の方々より多いのです。
日本人に胃腸の弱い人が多いことと、日本が島国であることとは無関係ではないのです。
他の例でいうと、何気なく使う言葉で『ひ弱』というものがあります。もろくて弱々しいさま。という意味ですが、子供でいうと発育不良の状態だったり、子供でなくても筋肉がなく弱々しい体型に対して使うことがあります。
脾(ひ)は肌肉(きにく)を司る臓腑ですので、脾が弱ると運動しても筋肉がつきにくくなります。
ひ弱=脾弱といえると、考えられます。
◎良い点としては、大陸の人々と比べると、お肌がもっちりと透明感のある質感になること。
☓悪い点は大雑把にいうと汚い水が溜まりやすくなること。
胃腸が弱い方のタイプ別お助け漢方
体内に湿(しつ:汚い水の一種)が溜まる要因はお分かりいただけたかと思いますが、その対策としてどんなことが出来るかをお話し致します。
湿が溜まる状態にはいくつかのタイプがあります。
タイプ別にこの時期おすすめの漢方アイテムをご紹介いたします。
タイプ① 胃腸が冷えやすく弱っている
もともと下痢しやすいとか、胃腸が弱いタイプはこの時期腸を今以上に弱らせないためのお助けアイテムとしておすすめしたいのが…
✜『健脾散』(けんぴさん)

タイプ② 普段からゲップが多く逆流性食道炎っぽい
腸というより、胃のほうにトラブルがある場合。ゲップやムカつき、食道の炎症などがある方におすすめ。
あとは、普段からいろんなこと我慢しやすい方にも◎
✜『健胃顆粒』(けんいかりゅう)

タイプ③ 悪夢を見るタイプ
消化器系の中でも胆嚢のほうに影響が出ている場合はこちら。
中医学で『胆』とは勇気と決断力を司る臓腑。
メニューを見て何を食べるかすぐに決められないという小さなことでも、胆の弱りを感じさせます。
このタイプは悪夢を見ることも多く、眠りの質が悪いのも特徴。
✜『温胆湯』(うんたんとう)

タイプ④ 体外から湿が大量に入ってきた時に
これは、梅雨の時期に起こりがちなことですが、湿邪(しつじゃ)に侵された時を指します。
梅雨は、ただ息をしているだけで口から吸い込む湿の量が増える時期です。
さらに、ノロウイルスなどの感染症や腹風邪をひきやすい時期でもあります。
そんなときにおすすめ。
また、海外へお出かけの際に、体に合わない食事をしてしまったときにも使えます。
海外旅行時必携のお助け漢方です。
✜『勝湿顆粒』(しょうしつかりゅう)

併せて使って欲しいアイテム
今回ご紹介した漢方薬と併せて使っていただきたいおすすめアイテムとしては、北見の天然ハッカ油!
ハッカ油は様々な使い方ができますので、これを機会に上手に梅雨対策にご活用下さい\(^o^)/