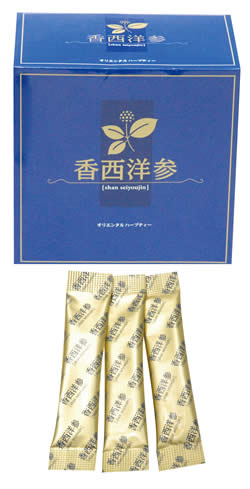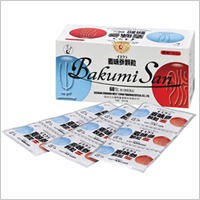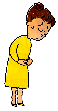☆発物(はつぶつ)のお話☆
皮膚の症状でご相談にいらっしゃったお客様には、必ず最近食べたもの、好きでよく食べるもの、悪化した時期に良く食べていたものなど、「食べたもの」のお話を詳しくお伺いします。
皮膚の対策では、食べもの、スキンケア、漢方薬が三拍子そろうことで回復に向かうのですが、その中でも身体の構成要素をつくりだす『食べもの』はとても重要です。
食べているものを知ることで、今、体がどういった状態にあるのかを知ることができます。さらにどういった食べ物に反応するのかを知ることで、より詳しく体質を見極められます。そして、食べ物のなかには食べると皮膚の症状を発生または悪化させるものがあり、古来から中医学では『皮膚病の禁忌』となっている食べ物の事を指して『発物(はつぶつ)』と言って、注意を促しています。そして、それらを避けるように食生活に気を付けることがとても重要です。
『発物』による病気の特徴として、発熱、かゆみ、ただれ、のどの痛み、痰、脹痛(張って痛む)、便秘、下痢などがあります。そして、どういった症状がでているか、どういった体質かによって食べるものを選ぶこともとても重要です。
例えば、冷えがあったり、軟便または下痢があるような体質が寒の状態であれば寒性(体を冷やす)の発物を避けるようアドバイスします。または、体質が熱でほてりや熱感、炎症症状が強い、便秘があるなどがあれば、熱性の発物を避けるようアドバイスをするといった具合です。では、実際にどういった食べ物に気を付ければよいのでしょうか。
☆発物の例☆
動物性のタンパク質
魚介類、牛肉、羊肉、あひる、カモ肉、牛乳、卵など
野菜・穀物類
ねぎ、たまねぎ、とうがらし、こしょう、セロリ、大豆、そら豆などの一部の豆類、そば、小麦など
くだもの
バナナ、パイナップル、マンゴー、柑橘類、銀杏、パパイヤなど熱を誘引する発物 しょうが、こしょう、とうがらし、にんにく、ねぎ、羊肉、牛肉、にら、桃、油っぽいもの、タバコなど
風(体の上部に症状を起こすのが特徴。そのた遊走性のかゆみなど)を誘引する発物
魚介類(特にエビ、カニ)、アヒル、カモ肉、ガチョウ肉、たまご、香菜、きのこ、たけのこ、マンゴーなど
湿熱(腫れ、浸出液・ジュクジュク湿疹)を誘引する発物
魚介類、もち米、ビール、酒、甘酒、たけのこ、きのこ、ねぎ、内臓肉、油っぽいもの
寒滞と冷え(冷えによる血行障害、胃腸障害など)を誘引する発物
スイカ、梨、柿、冬瓜、白菜、ニガウリなど
出血(皮膚出血、皮下出血、腫れ、かゆみなど)を誘引する発物
こしょう、玉ねぎ、そら豆、酒など
気滞(腫れて痛む、ストレス、胃部膨満感など)を誘引する発物
羊肉、もち米、そら豆、大豆など
**現代の化学添加物も皮膚病を悪化させる性質があるので発物に属すると考えられています。
皮膚でお悩みの方は、症状、体質を見極め、生活養生、食養生、スキンケアを加えた総合的な漢方対策を施すことが大切です。
上記にあてはまるものがあった方、是非それらをやめてみることから始めてみてくださいね。