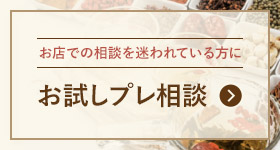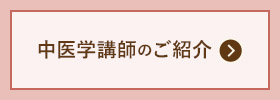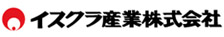「冷え」と漢方について
よく耳にする『冷え性』とは御存じの通り、病名ではなく『症状』です。西洋医学では、寒・熱という概念はありません。そのため、病院へ行っても体質や年齢、自律神経の失調などが原因ととらえられることが多く、有効な治療法が確立していません。
一方、中医学では、寒・熱は体質を知る上で重要な判断材料となります。体に冷えがあるかないかで、選ばれる漢方薬も異なります。冷えはまさに体質改善を目指す中医学の得意分野と言えます。
なぜ冷えるのでしょうか?
人の体は、常に酵素の働きで代謝が行われ生命活動が維持されています。この酵素の代謝が安定的に行われるためには、常に酵素にとっての最適温度37度が維持されなければなりません。つまり、内臓のある体の中心部温度を常に37度に保つために、様々な環境の変化に応じて体温を調節しているのです。
体温調節は主に皮膚、血管、骨格筋で行われています。脳や神経系の指令のもと、皮膚は発汗による熱放出、血管は収縮による体内温度の伝達の調整、骨格筋は不随意的なふるえ(寒くなるとぶるっと筋肉がふるえる)による熱産生を行って体温を維持します。
寒い時、体はなるべく心臓や肝臓などの重要な臓器を冷やさないように働いています。手足の末端や皮膚表面の血管を収縮させ、血液を重要臓器の集まる中心部に集め熱の拡散を防ぎます。このため、手や足の先の温度が低くなり冷えを感じるのです。この寒さにさらされる状態が続くことで冷えを感じやすくなります。
冷えの原因
女性は男性よりも冷えを感じる人が多いのは事実です。この理由として、男性より熱を生み出す筋肉量が少なく基礎代謝が低い、一度冷えると温まりにくい性質である皮下脂肪が多い、貧血や低血圧傾向、月経の状態によっては腹部の血流が滞りやすいことなどが考えられます。また、体の水分量が多い、アレルギー体質、自律神経失調症、婦人科疾患があるなども体を冷やす素因となります。
また、無理なダイエット、冷たい飲食物の過食、喫煙、きつい下着、ミニスカート、強いストレス、ヒールの高い靴など、日頃の生活習慣が冷えの状態を悪化させていることも少なくありません。ただでさえ冷えているのに知らず知らずのうちに冷えを一層ひどくしている・・・あなたは思い当たることありませんか?
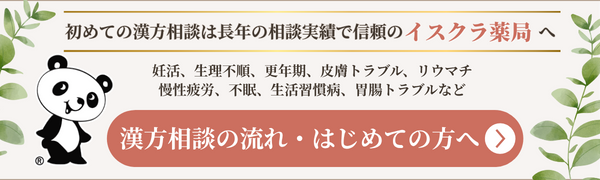
冷えに対する中医学の考え方
中医学的に考えると、冷えの主な原因は、血液の巡りが良くない『瘀血』、良質な血液や体のエネルギーとなる気の不足した『気血両虚』、ストレスなどで気の流れが停滞した『気滞』、体を温める「陽」のエネルギーが不足した『陽虚』が考えられます。
タイプ別冷え性とおすすめ漢方
瘀血(おけつ)タイプ
普段から、肩こりや頭痛、生理痛などのある方は、血流循環がスムーズでないことが多く瘀血傾向にあると考えます。お顔のくすみや消えにくいしみ、目の下のくま、唇の色が暗いなどのお悩みもこのタイプです。漢方で血を巡らせながら体を温めていく対策をとります。
おすすめ漢方:イスクラ冠元顆粒(かんげんかりゅう)、イスクラ婦宝当帰膠B(ふほうとうきこうびー)、桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)、当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)、温経湯(うんけいとう)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など


おすすめ食材:エシャレット、ザーサイ、獅子唐辛子、玉ねぎ、菜の花、にら、バジル、パセリ、ミョウガ、ローズマリー、山査子、桃、栗(渋皮付き)、赤貝、いわし、カタクチイワシ、鮭、鯖、ニシン、黒砂糖、酒粕、酢、ターメリック、甘酒、金木犀、玫瑰花、紹興酒、日本酒、焼酎など
気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ
貧血や立ちくらみ、疲れやだるさを感じやすい、生理の時の経血の量が少ない傾向にある方は、体の栄養源である血液が少なく、元気に体を維持するための気も不足した気血両虚と言えます。
特に‘血’は女性にとって最も大切な栄養源。毎月月経で失うことも考えると、常に十分補充しておくことが理想的です。気血を養う漢方を使って対策を行います。
おすすめ漢方:イスクラ婦宝当帰膠B(ふほうとうきこうびー)、イスクラ参茸補血丸(さんじょうほけつがん)、イスクラ補中丸(ほちゅうがん)、十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)、当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

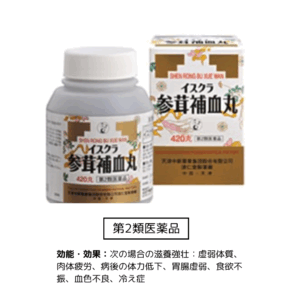

おすすめ食材:よもぎ、棗(乾燥)、ライチ、龍眼、赤貝、穴子、あんこう、いわし、鮭、鯖、タチウオ、ニシン、ブリ、マグロ、クジラ肉、鶏や豚のレバー、米麹、もち米、納豆、浅葱、エシャレット、蕪、南瓜、にんにくの茎、さくらんぼ、棗(乾燥)、エビ、カタクチイワシ、マス、牛すじ、鶏肉、羊肉、水飴、酒粕、味噌、甘酒など
気滞(きたい)タイプ
ストレスを感じやすい、イライラしやすい、お腹の張りや便秘、生理前の胸張りなどがある方は、気の巡りが滞った気滞が考えられます。気と血は車の両輪のように、互いに連動した動きをするため、気の流れが停滞すると血の流れにも影響がでてきます。そのため、血行不良による手足の先の冷えが生じます。
ストレスや情緒不安な状態は肝の経絡を滞らせ気滞となります。この様な場合、気の循環を整えることが冷えの対処法となります。
おすすめ漢方:イスクラ逍遙顆粒(しょうようかりゅう)、四逆散(しぎゃくさん)
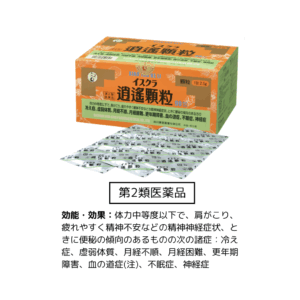
おすすめ食材:フェンネル(茎、葉、種)、紫蘇、玉ねぎ、チャービル(セルフィーユ)、にんにくの茎、ノビル、バジル、ミョウガ、金柑、ゆず(皮)、ライチ、カジキマグロ、カルダモン、クミン、ターメリック、陳皮、ナツメグ、八角、金木犀、玫瑰花、ラベンダー、紹興酒、日本酒、ワインなど
陽虚(ようきょ)タイプ
疲れやすい、風邪をひきやすい、背中の辺りがいつも寒く感じる、下痢や胃腸を崩しやすい、むくみやすい、腰痛などのある方は、体を温める腎陽の力が不足した陽虚(腎陽虚)と考えられます。病気などで体内の陽気を損なうこともあります。このような陽気が不足した方の場合、外からの寒(外寒)が体に入りやすく、体の中に内寒も生じやすくなるため、余計に冷えを強く感じるようになります。
内寒により、胃腸機能が低下し、食べた物が胃に停滞すると‘湿’(体に不要な水分)が生じやすくなります。湿は寒と結びつきやすく、気血の流れを塞ぎさらに冷えを増強させるといった悪循環が生じることもあります。胃腸を温め、体を温める陽気の力を強めることが必要です。
おすすめ漢方:イスクラ参馬補腎丸(じんばほじんがん)、イスクラ参茸補血丸(さんじょうほけつがん)、四逆湯(しぎゃくとう)

おすすめ食材:フェンネル(茎、葉、種)、エシャレット、からし菜、ザーサイ、紫蘇、生姜、ディル、ニラ、ネギ、よもぎ、辛子、クミン、クローブ、胡椒、花椒、シナモン、唐辛子、八角、金木犀、紹興酒、日本酒、焼酎、赤貝、エビ、マグロ、クローブ、シナモン、八角、ウィスキーなど
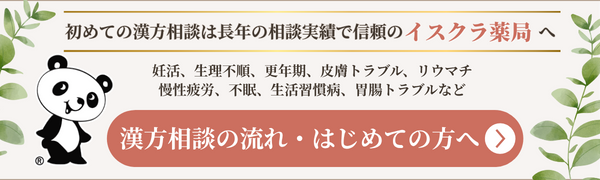
冷え性のまとめ
私達の生活の中には、便利で簡単なものが溢れています。その一方で、生活習慣病で悩む人が年々増加しています。‘冷えは万病の本’という言葉通り、生活習慣病の原因に冷えが関わっていることは少なくありません。日頃の食養生や運動、良質の睡眠、ストレスの解消など日頃の生活を見直してみること、その上でご自分にあった漢方薬をご服用いただくことをお勧めいたします。冷えのお悩み、どうぞイスクラ薬局までお気軽にご相談くださいませ♡
冷え,冷え性
,