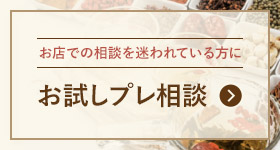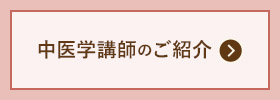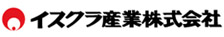今回はそんなお悩み症状別にお勧めの漢方や正しい飲み方などをご紹介いたします。

女性特有の症状には漢方薬がおすすめ
女性の一生に関わる「腎」の働き
中医学では、女性の体が7の倍数で変化し、7×2 =14歳で初潮を、 7×7=49歳で閉経を迎えると考えます。この変化は「腎」の機能によるものです。「腎」とは、腎臓だけではなく成長・発育・生殖・老化に関わるホルモン分泌や泌尿器系、自律神経系、免疫系の機能を担います。14歳前後で、腎の機能が一定レベルに達すれば、初潮を迎えることができ、 49歳前後で腎の機能が衰えて、閉経となるのです。そしてホルモン分泌や泌尿器系、自律神経系、免疫系の機能のトラブル、つまり腎の機能に関わるお悩みには、漢方では「補腎」という方法があります。
月経周期は陰陽のリズムによって成り立っている
女性の月経周期は、「蓄える時期 (蔵)」の卵胞期と黄体期、「排出する時期(瀉)」の排卵期と月経期からなっています。蓄える時期には、腎のしっかりと蓄える(封蔵)作用と脾の漏れないように守る (固摂)作用により、卵胞を成熟させ、子宮内膜に栄養を蓄えて柔らかい状態にさせます。排出する時期は、肝の疏泄(伸びやかな代謝リズム調節)の働きによって、しっかりと排卵し、月経血などをきれいに残さず排出します。
中医学では人体を陰と陽の二元論で説明することがあります。女性の生理では卵胞ホルモンを陰と考え、 黄体ホルモンを陽と考えます。月経期から陰である卵胞ホルモンが増え始め、卵胞期にさらに分泌が増えて、その分泌が最大になって排卵、つまり陰が極まって、陰が陽に転化します。黄体期には陽である黄体ホルモンの分泌が増え始め、最大に達したときに月経となり、つまり月経期に陽が極まって、陽が陰に転化します。
このように月経周期を中医学では陰陽の変化に伴って進行、転化すると考えます。そしてこの陰陽のリズムが乱れることにより、様々な不調が現れます。漢方にはこの陰陽のバランスの不調を整える方法があります。
月経周期にともなう心身の変化
女性生理の器官系は、各部の巧みな連携と共同によって、初潮から閉経までおよそ400回、 25~35日の一定周期で、妊娠を準備するプロセスを繰り返します。このプロセスには月経のほか、それぞれの期間に特有の生理的な現象がともないます。
月経期(3~7日間)から始まる約2週間の周期前半(月経期と卵胞期、つまり陰の時期)は、卵子とその着床環境を新たに準備する段階です。これに呼応して受精の準備を促進する意味で、本能的な感情・欲求は月経終了後に高まるリズムに設定されています。また排卵が近づくと、卵管まで精子の進入を許容する目的で、子宮の入り口をふさいでいた粘液の粘度を低下させ、その量を増やす結果として生理的帯下(おりもの)が起こります。
その後の周期後半(排卵期と黄体期、つまり陽の時期) には、受精卵の着床・養育に備えるため、子宮内膜に再生された分泌腺が活動を開始します。これを助けるため全身の代謝が高められ、体温が0.3~0.5℃ほど上昇します。
次の月経前の1週間ほどは、ときにホルモン分泌・自律神経系の調節・抑制がきかず、イライラ、ゆううつ、不安、不眠、のぼせ、めまい、乳房の張り、胃腸の不調、むくみ、頭痛、肩こりなど、心とからだの両面に不調を起こすことがありますが、通常は月経の開始とともに解消します。
このような心とからだの変化は、症状として軽く、本来の正しい時期に起こるかぎり心配はありません。しかし、症状が重く不快感が強いとき、起こる時期が違うとき、帯下が多かったり色や臭いがあるとき、月経痛・月経不順・不正な出血があるとき、感情・欲求がコントロールできないときは、放置すべきではありません。漢方には、それぞれの症状にきめ細かに対処し、正常化を助ける方法があります。
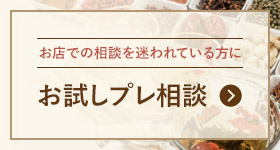
女性の生理と栄養
胃腸を中心とした消化器系が活発に働いて飲食物がよく消化され、栄養素が体内に効率よく吸収されることは、人体のすべての内臓・器官の活動を維持するための前提条件です。
女性生理の器官系についても例外ではありません。しかし、あまりにも当然すぎるためか、このことはむしろ軽視されがちです。
実際に、栄養素の吸収が制限されれば、各器官系への栄養供給が悪くなり、その役割を果たす力が弱まり、構造を支える力の弱まりも現れます。
当然女性生理の器官系にも、月経血の色がうすい、量が少ない、月経期が短い・遅れる・ダラダラ長引く、不正な時期に反復して出血する、高温期への移行がゆるやかなど、不足と弱まりの症状が現れます。 この状態に漢方では気を補う人参(ウコギ科オタネニンジンの根)、 黄耆(マメ科オウギの根)などの補気薬を用います。補気薬は消化器系(脾胃)の働きを活発にして、全身の組織の栄養状態と体力を改善する一環として、女性生理の器官系を健全な状態に回復させます。
女性生理の器官系には、卵巣と子宮を中心とした生殖器系、これをコントロールするホルモン分泌・自律神経系、血液の流れる循環系などが含まれます。補気薬は、筋肉、粘膜、血液などを構成する細胞・組織におけるエネルギーと物質の代謝を改善することで、子宮や血管の構造と運動をささえる筋肉の緊張性を高め、血管と血流をしっかりさせ、無用な出血を防ぎます。また、卵巣と子宮内膜の周期変化を生む過程を力強く進めていく働きがあります。
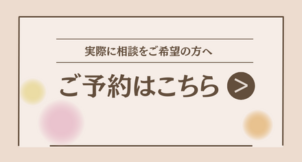
【悩み・症状別】女性におすすめの漢方薬
下記に女性特有のお悩み・症状別におすすめの漢方薬の一例をご紹介します。あくまでほんの一例ですので、実際に漢方服用を検討される際は、漢方薬局で詳細ご相談されて下さいね♡
生理不順
逍遥顆粒、婦宝当帰膠、加味逍遥散、芎帰調血飲第一加減、桂枝茯苓丸、温清飲など
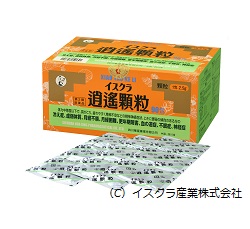
生理痛
冠元顆粒、加味逍遥散、婦宝当帰膠、当帰建中湯、五積散、通導散など

冷え
参茸補血丸、参馬補腎丸、逍遥顆粒、双料参茸丸、婦宝当帰膠、十全大補湯、人参養栄湯、温経湯、苓姜朮甘湯など

便秘
開気丸、清営顆粒、麻子仁丸、大黄牡丹皮湯、潤腸湯、桃核承気湯、調胃承気湯、大黄甘草湯、通導散など

更年期障害
頂調顆粒、逍遥顆粒、婦宝当帰膠、温清飲、加味逍遥散、柴胡桂枝乾姜湯、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、五積散、通導散、温経湯、三黄瀉心湯など

むくみ
杞菊地黄丸、瀉火補腎丸、八仙丸、蘭州金匱腎気丸、精華牛車腎気丸、防風通聖散、柴苓湯、茵蔯五苓散など

漢方薬の正しい飲み方
尚、漢方薬も西洋薬と同様適切な飲み方があります。飲み方に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。「漢方薬の適切な飲み方|飲みやすくする方法も」
女性特有の症状に漢方薬を試してみては
以上、女性特有の症状には漢方薬がお勧めであることを解説させて頂きました。月経に伴う心身の変化、又閉経後の心身の変化に伴う様々なお悩みに、漢方ではお一人お一人にのご体調ご体質に合わせてきめ細かく対応することが出来ます。女性のお悩み、どうぞイスクラ薬局までお気軽にご相談くださいませ♡まずはメール相談をご希望でしたらお試しプレ相談、ご予約でしたらお電話もしくはご予約フォームから承ります♡