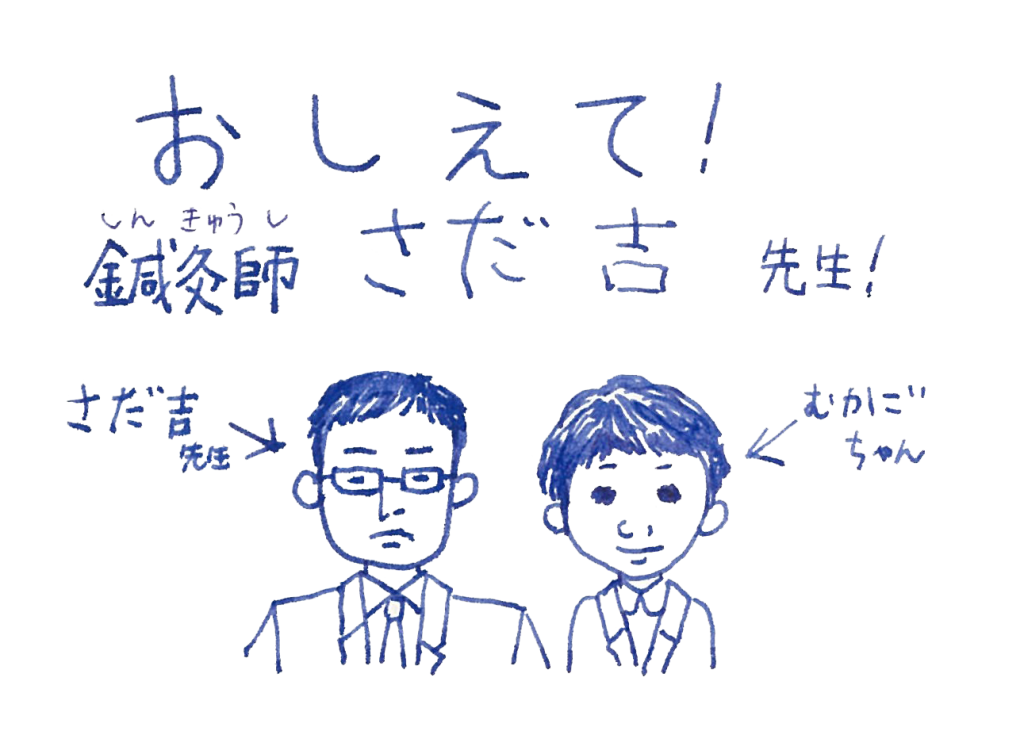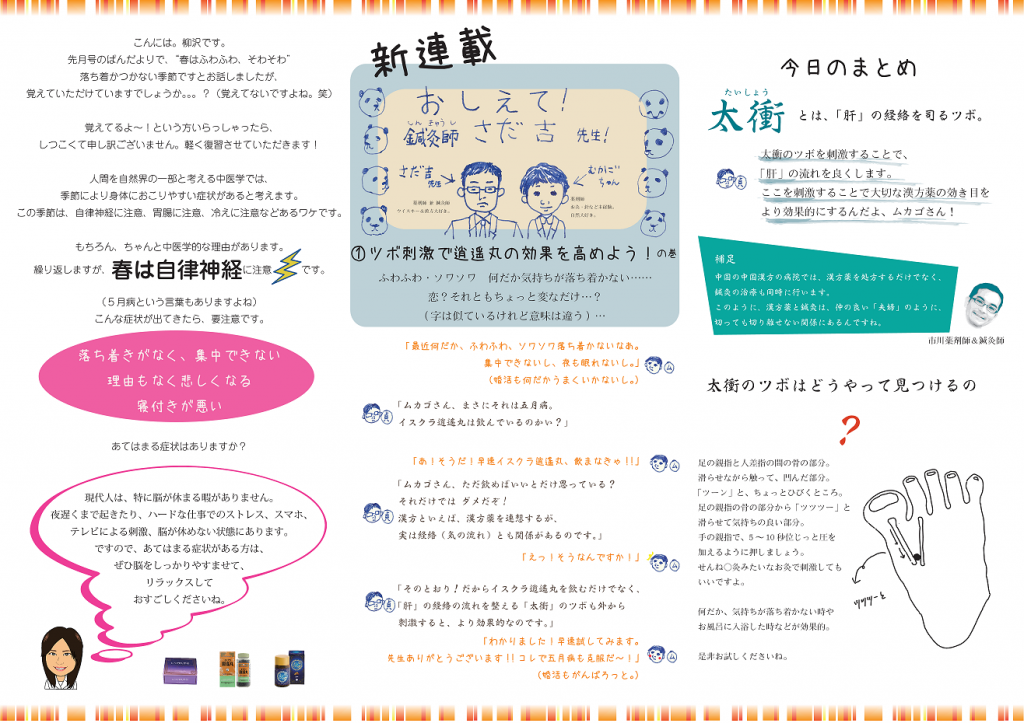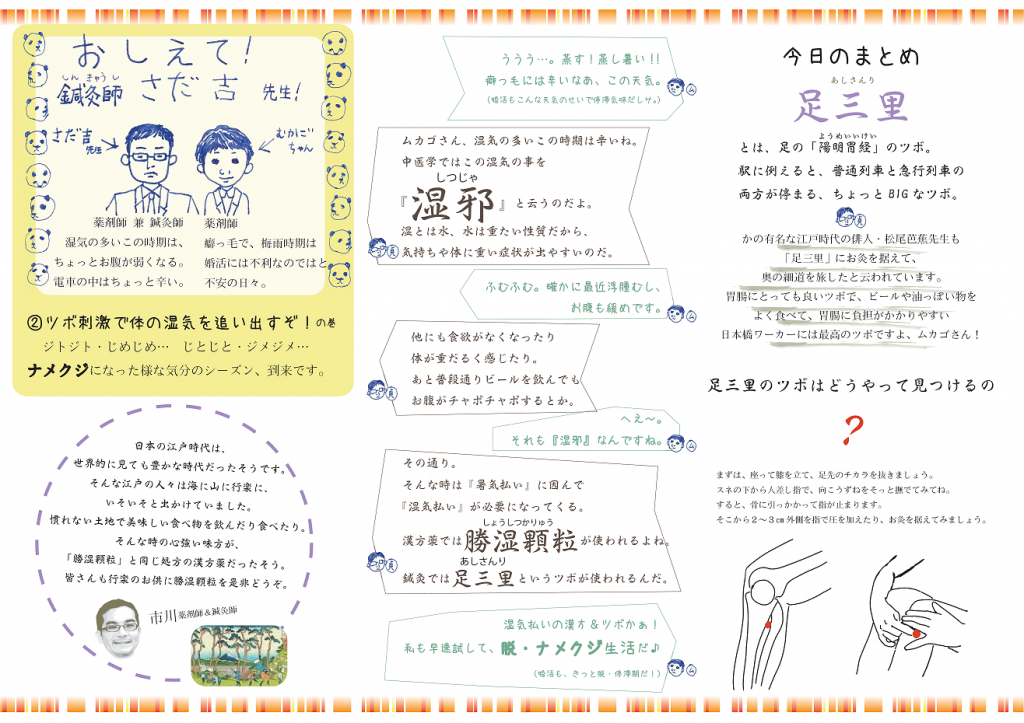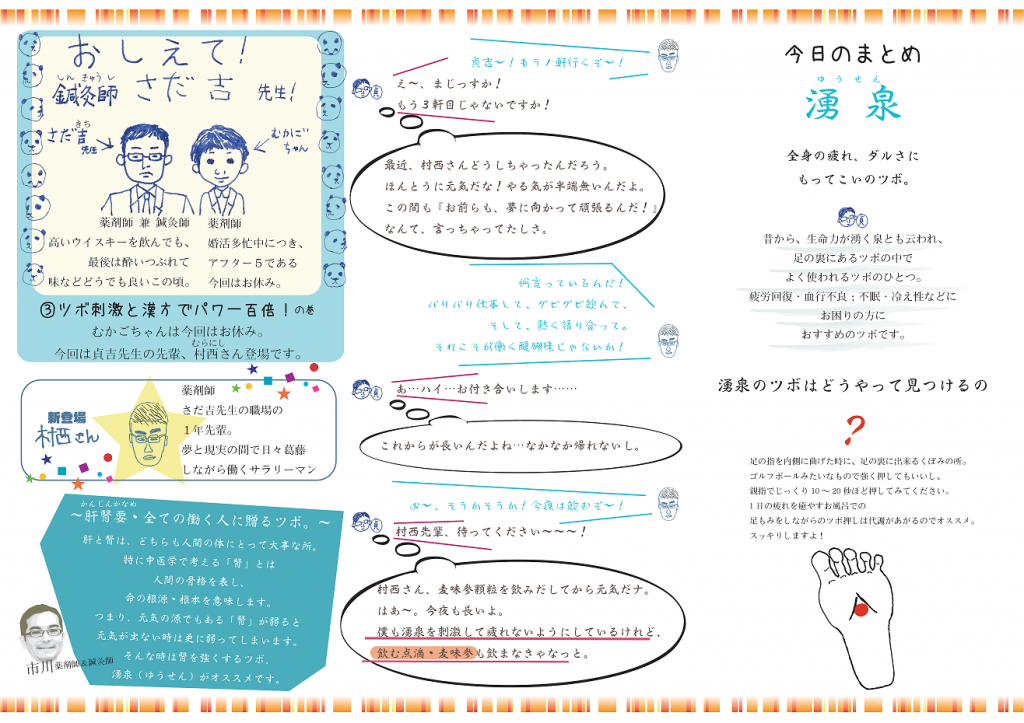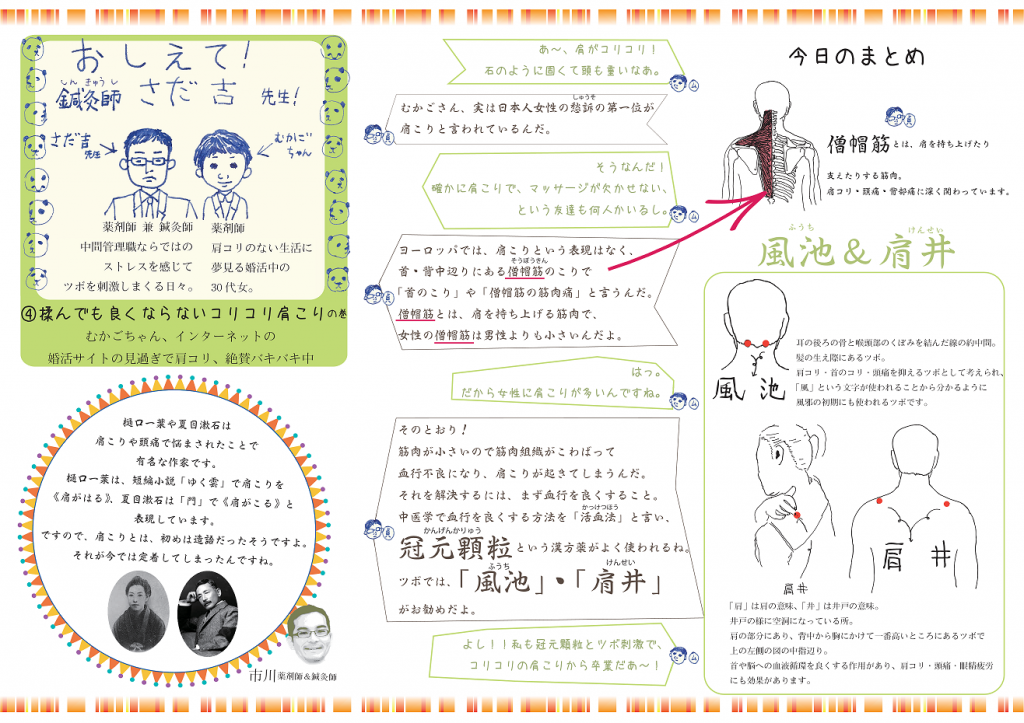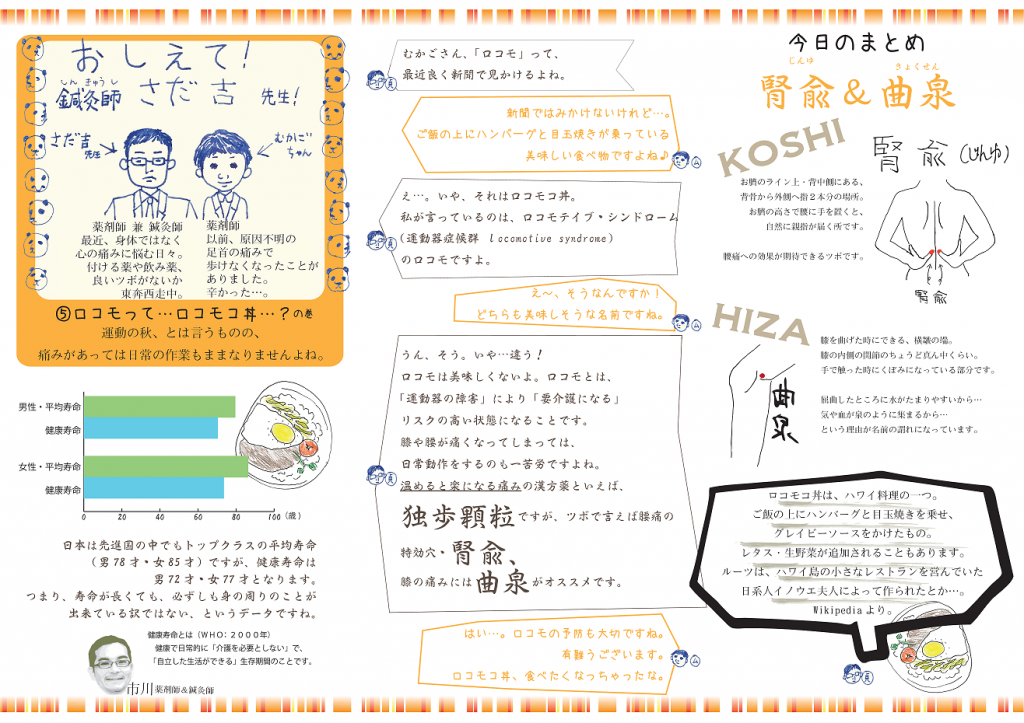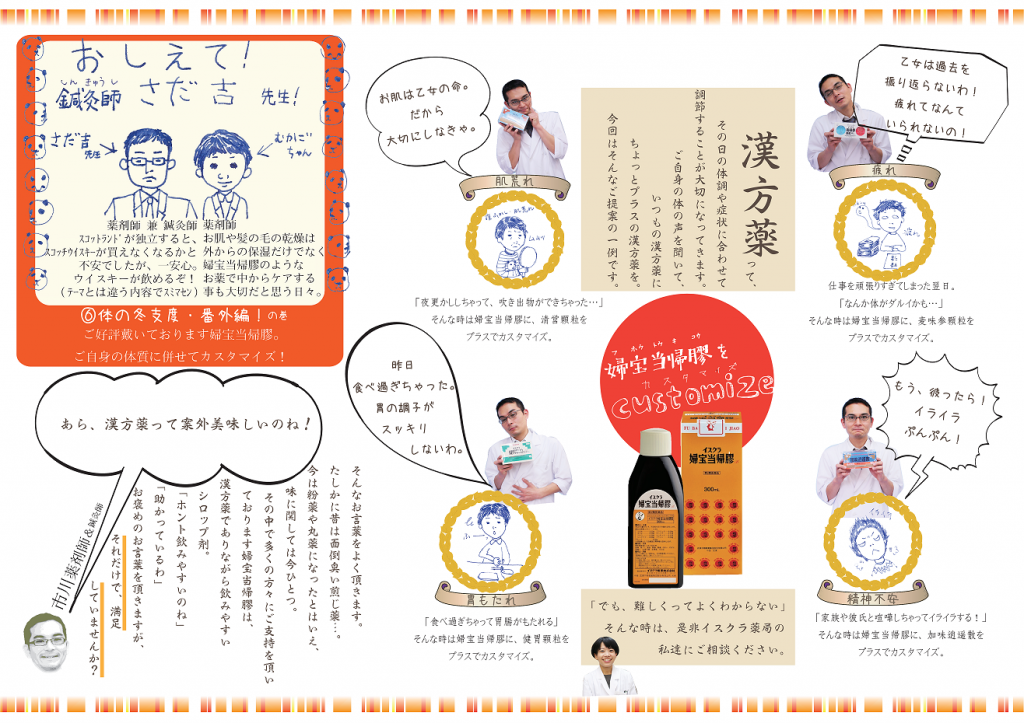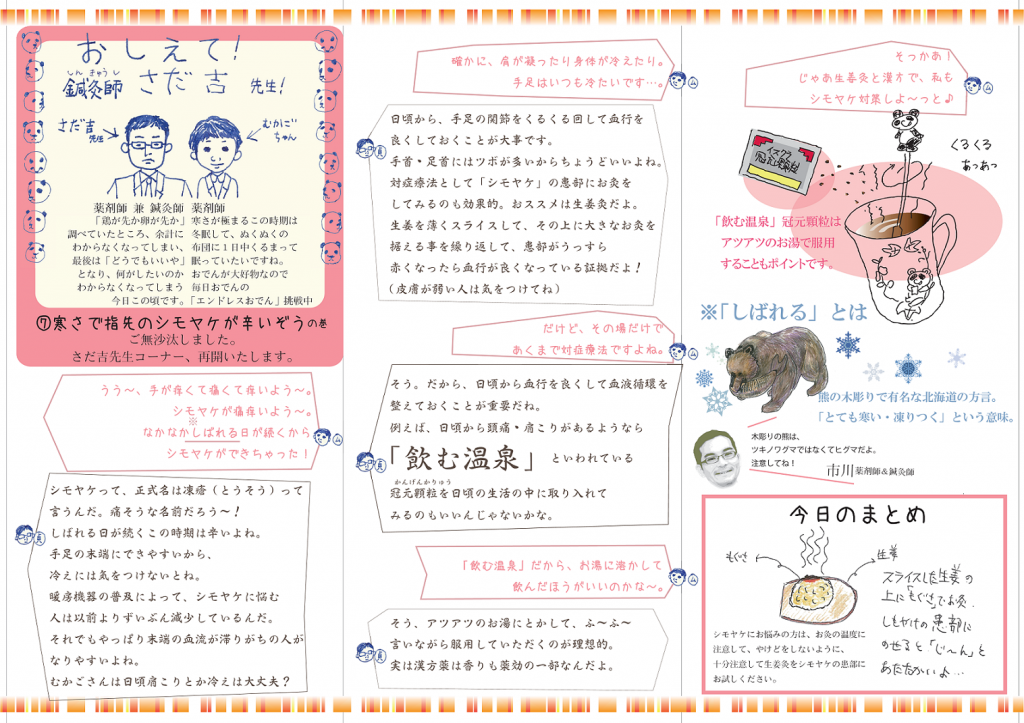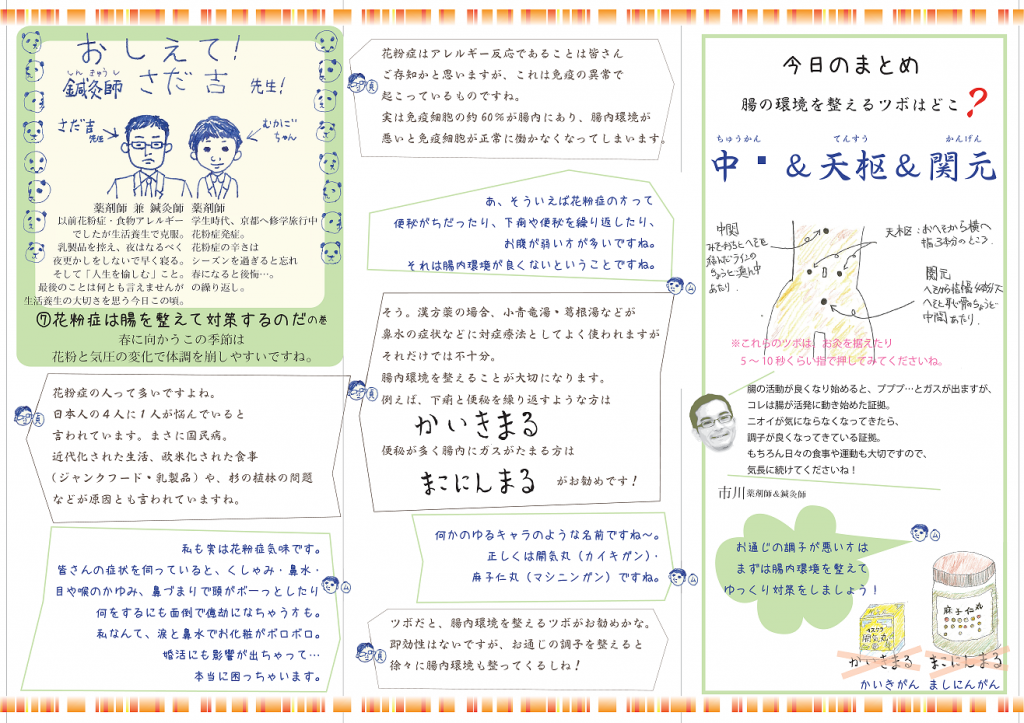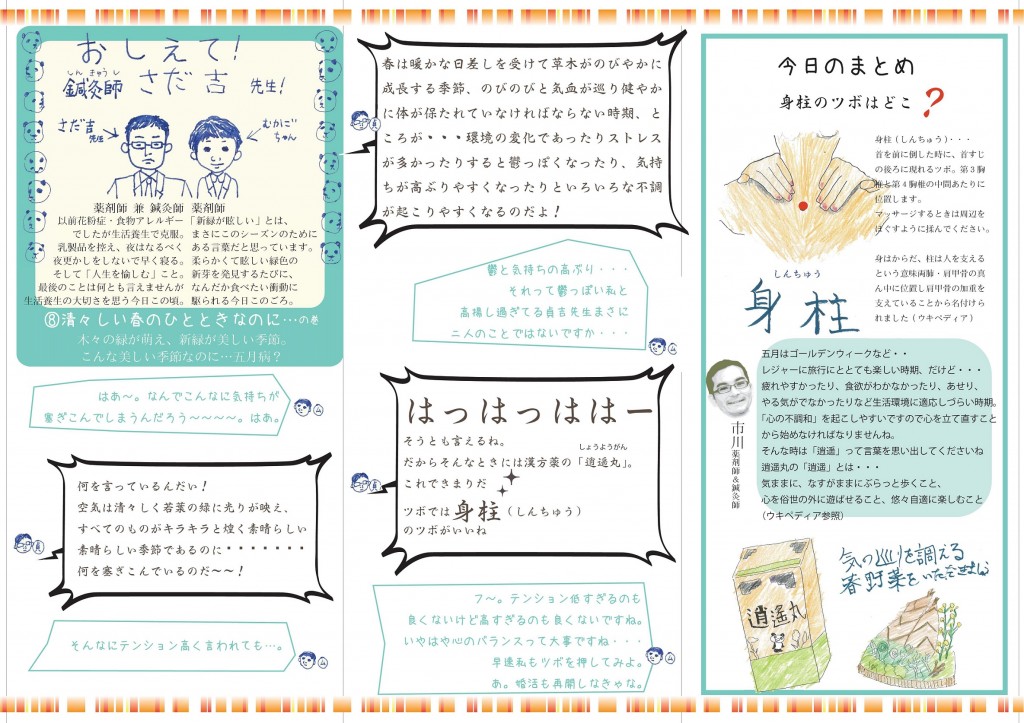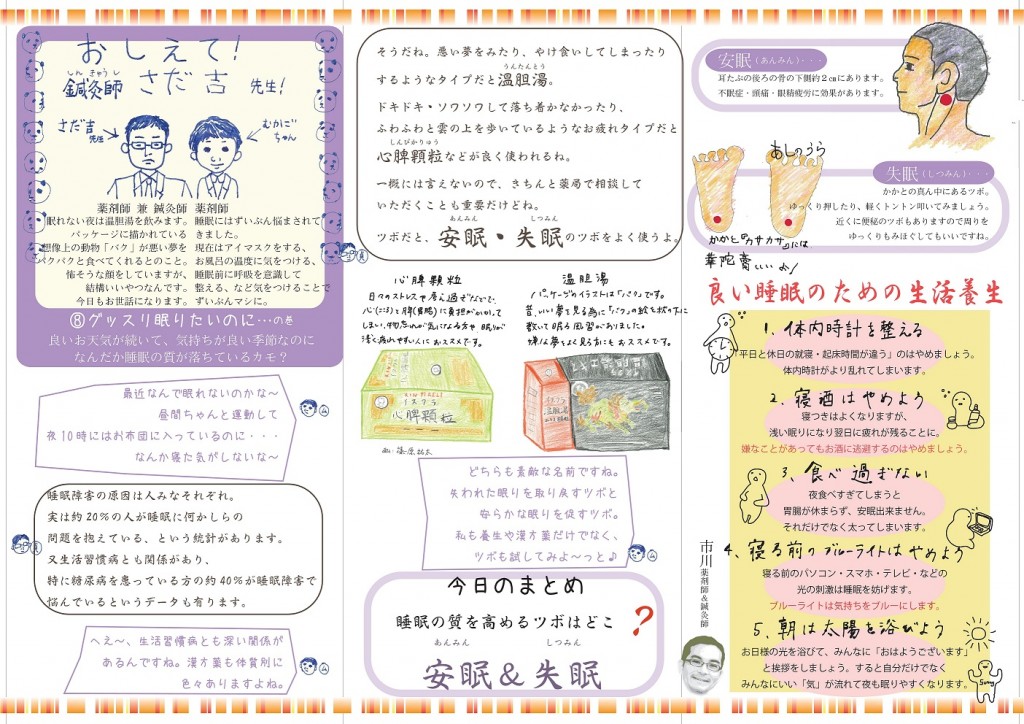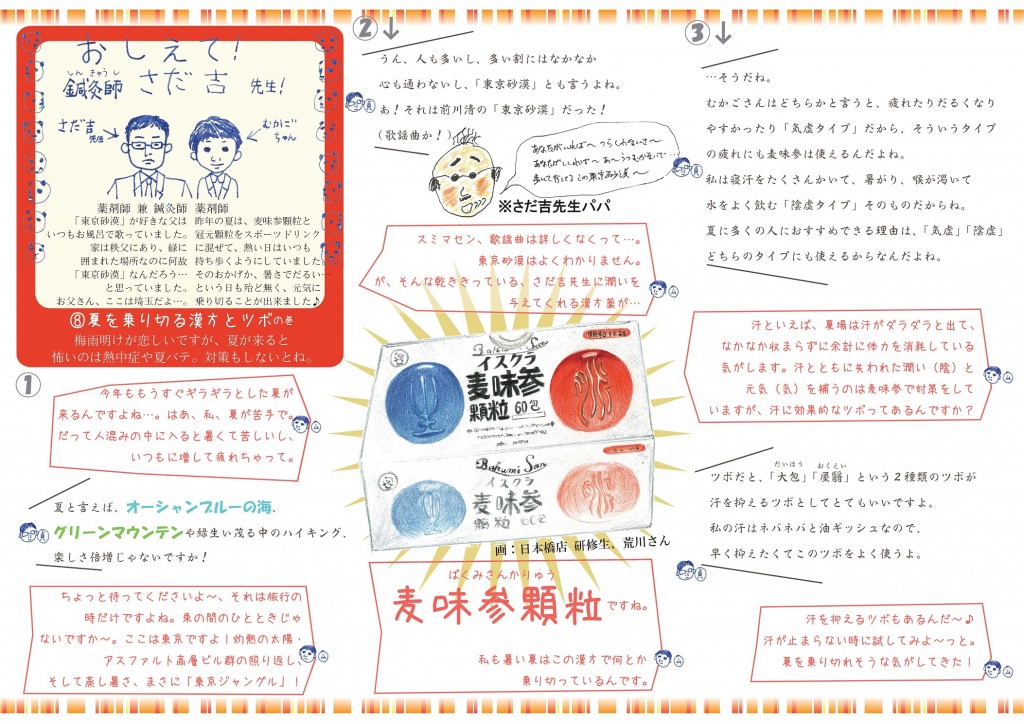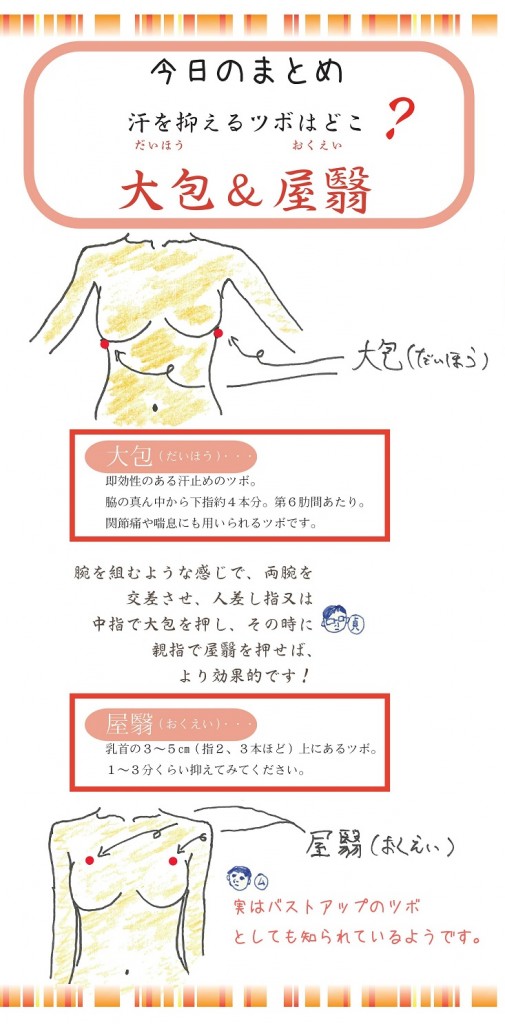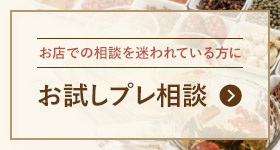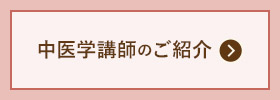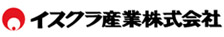こんにちは、柳沢です。
先日、新潟県の長岡市に行って来ましたが、気になっていたタニタカフェに行くことができました♪
~長岡市のホームページより抜粋~(長岡市ホームページはこちら。)
長岡市では、平成25年度に産学官が連携した「多世代健康モデル研究会」を立ち上げ、誰もが健康に暮らせるまちづくりについて検討を進めてきました。
11月、多世代健康まちづくり事業の一つとして、健康の3要素「食」「運動」「休養」を良質でバランスよく実践できる健康づくりの拠点・「タニタカフェ」が市民センター内にオープンします。家庭用計量器メーカーでタニタ食堂を展開する株式会社タニタがプロデュース。同社がカフェスタイルの健康拠点をオープンさせるのは全国で初となります。(運営は一般社団法人地域活性化・健康事業コンソーシアム) このまちなかの拠点から、子どもから高齢者まで、「多世代健康まちづくり」を推進します。
カフェでは体組成計で健康度をチェックし、管理栄養士等のアドバイスや、リラックスコーナーがあったり、(なんと足湯やハンモックが!) 大型ディスプレイなどにより、くつろぎながらタニタの健康レシピや市の健康関連情報を提供する場所があります。
足湯に入りましたが、猛暑日でしたので、気持ちがよかったです(^^♪
街中に気軽に入れる“健康を意識できる場所”があって素敵だなと思いました!
でかけると、その場所の健康ショップや場所を調べて訪れている私。また行った際は報告レポートしますね♪♪