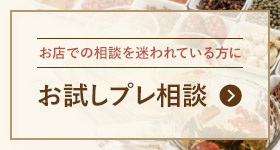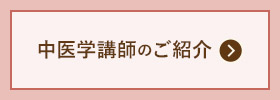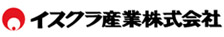月曜日担当: 劉 文昭 (りゅう ぶんしょう)
Q. まずは先生の経歴をお聞きしてよろしいですか?
A. 1983年に北京中医薬大学医学部を卒業し、 1990年に中国中医研究院大学院を卒業、 循環内科修士生を取得し、すぐに中国研究院広安門病院心臓内科勤務、助教授になりました。
1997年に早稲田大学と広安門病院の国際交流のために、早稲田大学の心理学部に客員研究員として来日し、中医の論文を発表し、薬局での相談や、執筆活動をしていました。
Q. では、日本に来て10年目ということになりますね。先生から見て日本のすばらしいところはどこでしょうか?
A. 一つは衛生面ですね。もう一つは、日本人は仕事に一生懸命ですね。とてもまじめで、忠誠心があり、仕事に対する姿勢が非常に素晴らしいと思います。
Q. では、初めて日本にきて驚いたことはなんですか?
A. 日本の女性です。冬に無防備すぎますね。季節感のない格好や、冷たい物の飲み過ぎで、 若い時に体を冷やしすぎです。生理痛や子宮筋腫が多いわけです。中国の女性は冬は皆ズボンですよ。しかも、何枚もはきます。
Q. 日本の女性ももう少し、冷やさないという意識をもたないといけませんね。中国では、冷たいもの、生ものはあまりとらないと聞きましたが?
A. そのとおりです。冷たいものはあまりとりませんし、氷を入れるなんてもってのほかですよ。
Q. 先生は心臓内科に勤務されたということは専門は主に心臓病ですか?
A. 元々は心臓病や、それに関わる高血圧や糖尿病、更年期、狭心症などを専門にしていましたが、今はアトピーや婦人科も専門としています。
Q. 現代の日本人には生活習慣病が多いですよね。
A. 一つはストレスです。もう一つは今の食事は濃いですね。肉、えびなど中性脂肪やコレステロールの溜まりやすい食事を食べ過ぎです。昔は貧しいので、米、野菜、などを中心とした食生活でした。
もう一つは若いうちに無理をする人が増えています。夜寝るのが遅い、過度の性生活など、 昔にくらべ開放的になっているのも腎を弱らせ、糖尿病などを引き起こす原因と考えられます。
Q. 若いから無理がきくのではなく、若いうちから体を消耗させない意識が大切なのですね。ところで、日本では漢方は「ほんとうに効くの?」と思ってる方はまだまだ多いと思うのですが?
A. 日本の人は、漢方を知っているものだと思ってましたが、日本に来てみたら一部の人のみですよね。 病気になったらすぐ病院へ行き、治らなかったら、漢方薬局へという方が多いですよね。ただ、中医学は説明すれば必ず納得してくれます。病院の検査では全く異常がないのに自覚症状があるというような病気や慢性病、体質がからんだ病気には漢方がとても向いているのです。
Q. 中国ではやはり漢方は身近なものなのですよね?
A. 子供のころから全部漢方ですよ!市民も漢方、中医学をよく知っています。 急性の疾患は病院へ行きますが、ほとんど漢方です。中医の病院はいつもデパートのように人でいっぱいですよ!
Q. 子供でも漢方は平気なのですか?
A. まんじゅうの中に入れたりしますよ。
Q. なるほどまんじゅうですか。漢方は自然のものですから、中国の人は食べ物に対する意識も高いのではないでしょうか?
A. そうですね。食べ物の性質をよく理解し、夏や暑い南の地方では熱をとるもの、冬や北の地方では体を温める性質のものや補うものを入れ、肉を煮るときに黄耆や山椒、枸杞子など、漢方で使う生薬もよく使います。
Q. 食養生の意識が高いようですね。最後に、先生はとてもスリムなのですが、そのスタイルを保つために心がけていることは何ですか?
A. 食事のコントロールですね。食物の種類をとにかく多く、三食違うものをバランスよく食べ、脂肪の多いものは食べないですね。過食もしませんし、胃腸を強めるために漢方も飲んでいます。あとは適度な運動を常に心がけていますね。夜も11時前には寝ます。今は日本にいるので無理ですけど、 中国の人は昼寝をするんですよ。大切なことです。
先生を見て、先生のお話を聞き、改めて生活の見直しの重要さを実感しました。一つ一つ丁寧に答えてくださるところに先生の人柄を感じ、楽しく話されるのでのでついつい時間を忘れてしまいました。どうもありがとうございました