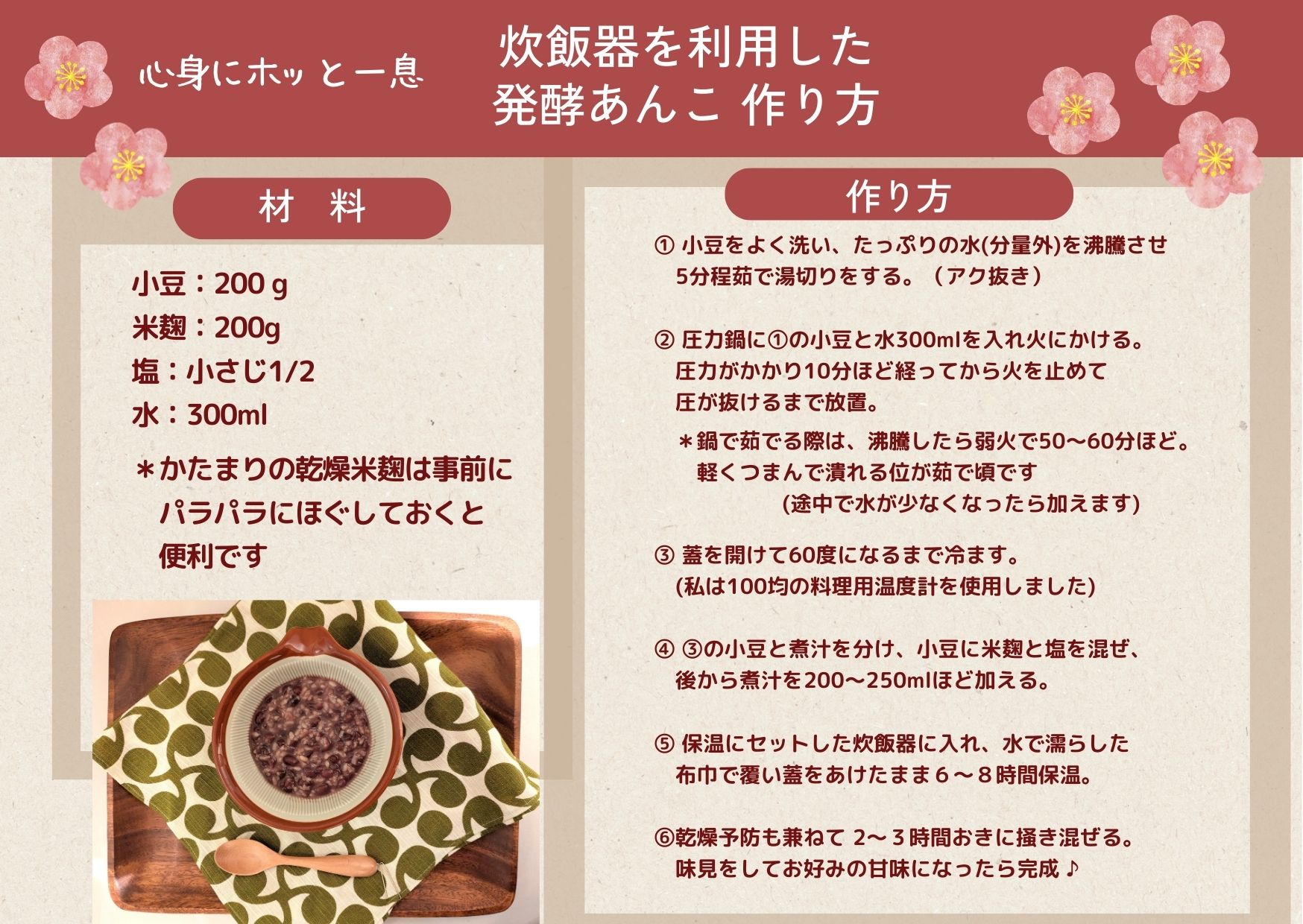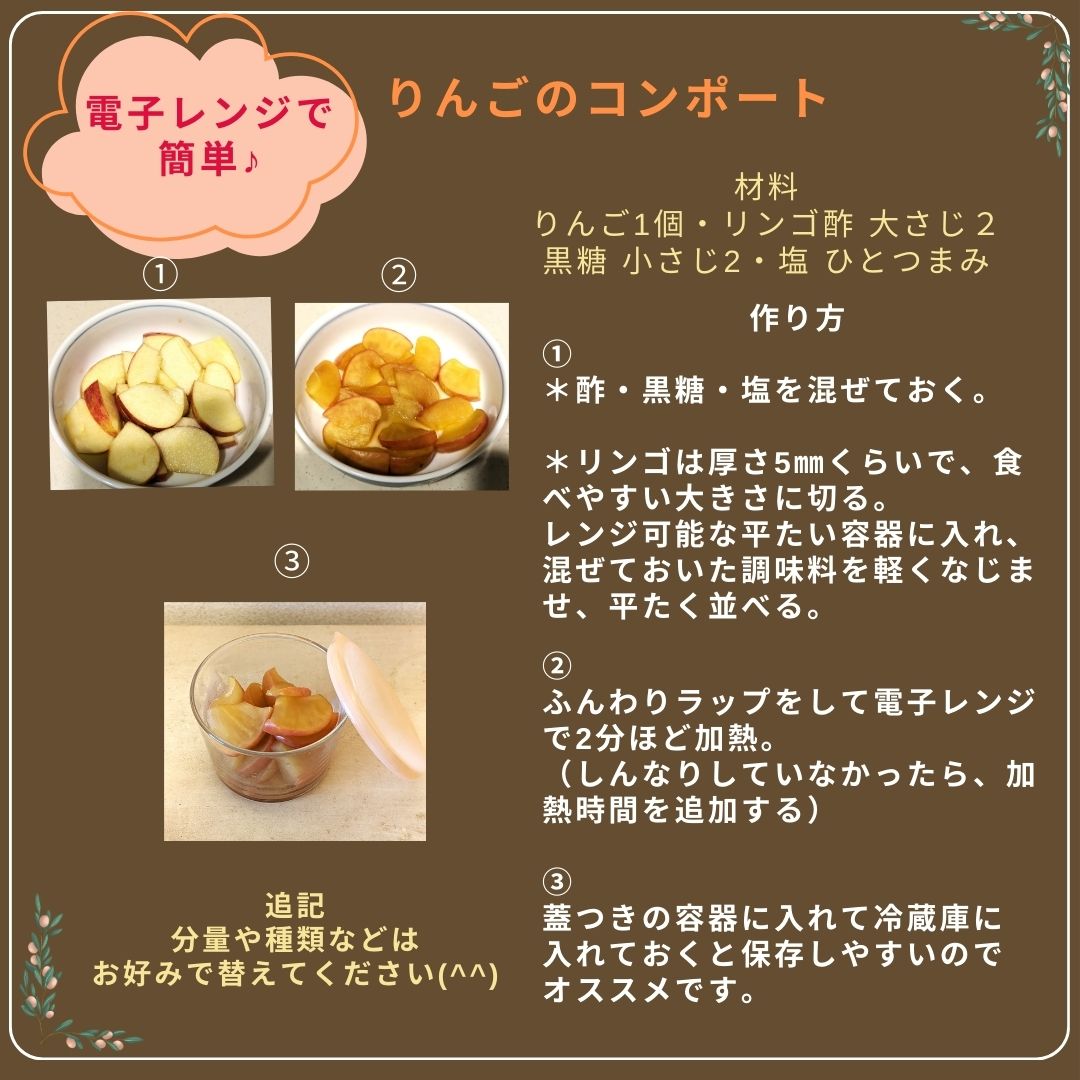こんにちは、金村です。
まだ暑い日が続いていますが、朝晩は涼しくなり、少し秋らしさを感じることができるようになりました。収穫の秋を迎え、美味しいものを食べ過ぎてしまうこの頃です。
今年から、野菜の中でも特に好きな茄子を栽培しています。

「秋茄子は嫁に食わすな」ということわざには、お嫁さんに食べさせたくない程美味しいという説や、茄子は涼性で冷やすため、お嫁さんに食べさせてはいけないという説があります。
秋茄子が美味しいと言われる理由は、夏場と違ってゆっくり成長するため中身がぎっしり詰まっていることや、温度差が大きい秋の気候が茄子の旨味と甘味を凝縮させるからだそうです。
茄子の栽培には、たくさんの水を必要とし、水が不足すると実ができなかったり、病気にかかりやすくなります。
茄子を栽培するのは初めてなのですが、最初の店で購入した二つの苗が少し弱っていたこともあり、その後別の店で更に二つ購入し、四つの苗を育てることになりました。成長するにつれて、弱っていた苗も元気に成長し、7月にはどの株からも茄子を収穫でき、ぬか漬けや麻婆茄子などにして美味しくいただきました。
ですが、喜んでいたのも束の間、8月半ばから葉の一部が少しガサガサして色が抜けたようになっていました。その後、あっという間に4株中2株の葉全体が白~黄色っぽくなり、枯れてしまいました。(その二株はやはり弱っていた苗です)
小さくてもムシできない
白~黄色くなっている葉をよく見てみると白い糸がかかっていました。白い糸はハダニによるものでした。
ハダニは蜘蛛の仲間で、肉眼では見つけづらい小さな害虫で、風に乗って移動してきます。様々な植物に寄生し、繁殖力がとても高いため、放っておくと株全体に広がり、近くの植物にも寄生します。
暑さで葉っぱも日焼けしたのね、くらいに考えて早めにきちんと対策しなかったことが残念でなりません。秋茄子を諦めきれない私は、生き残った二株に期待し、せっせと水やりと追肥をしています。
薬膳的効能
茄子は、甘味で涼性です。血の巡りを良くする、熱を冷まし熱により出血しやすい状態を改善する、腫れやむくみを改善し痛みを止める、といった効能があります。
民間療法では、茄子の蔕(へた)は黒焼にし、粉にして塩と混ぜて歯磨きをすると歯槽膿漏予防や口内炎などによいと言われています。
害虫対策にストチュウ水
今回は、茄子などの野菜を育てる際に農薬を使わず害虫を予防できるストチュウ水を紹介します。
ストチュウ水とは植物の成長を促進し、病害虫から保護するために使用されます。
<原液の作り方>
★用意するもの
①酢 ②焼酎(アルコール度数25度がおすすめ) ➂木酢液 ④空のペットボトル
酢:焼酎:木酢液=1:1:1になるように、今回は150mLずつで500mLのペットボトルに入れて混ぜ合わせ、常温で保管します。
<使用方法>
水やりの際に、原液を300倍程度に薄めて使用します。ペットボトルのキャップ1杯(約7mL)なので、6~7Lジョウロで、キャップ3杯が目安です。害虫予防であれば、週2回程度ストチュウ水での水やりがおすすめです。
葉面散布では、葉から水を与えながら、ストチュウ水の有効成分を吸収させたり、葉につく病害虫の予防ができます。ハダニは主に葉の裏に寄生しますので、葉の裏面はしっかりと散布しましょう。