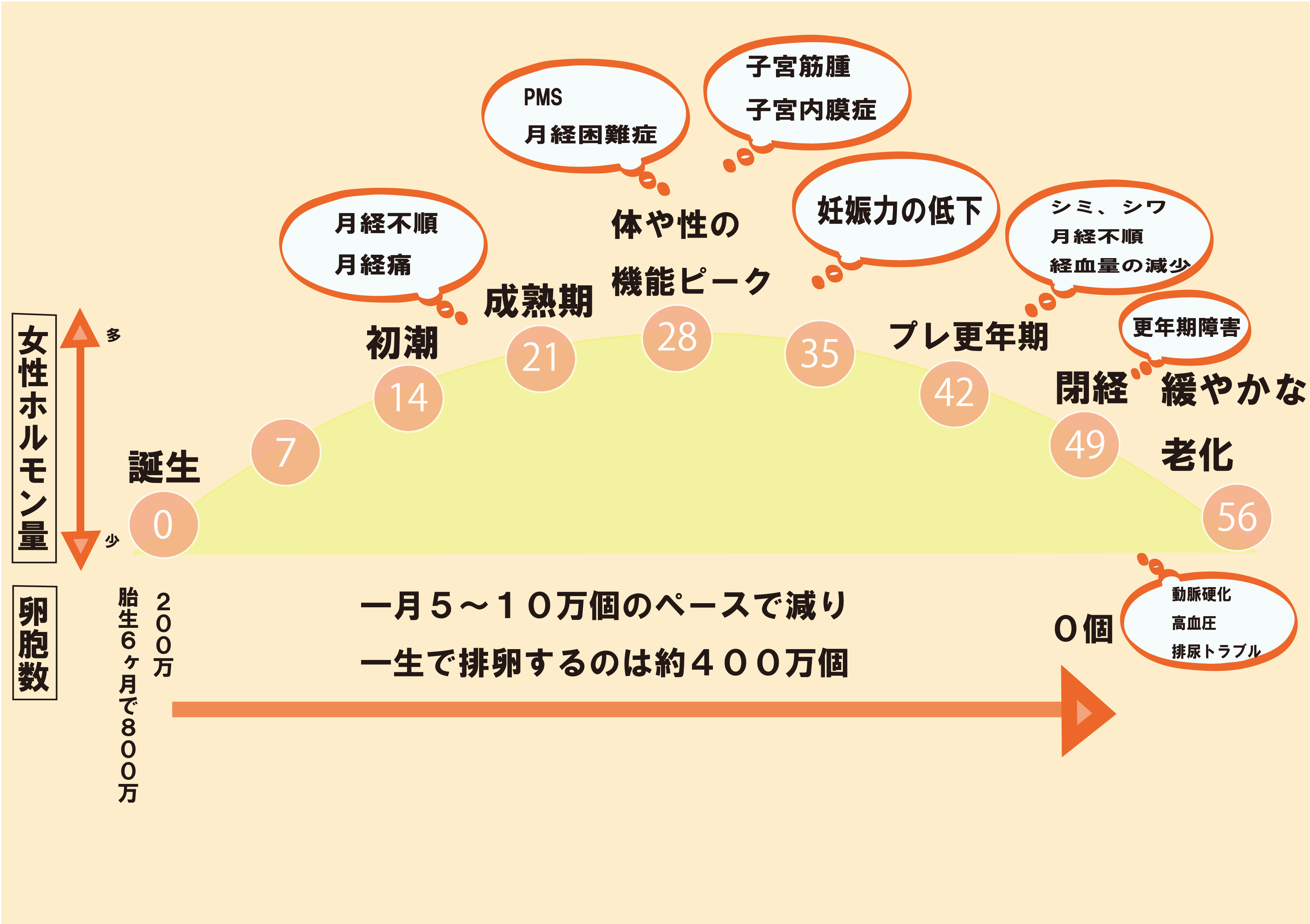こんちにはー(*´∀`*)
花粉症をやわらげるツボの話がtwitterにて話題となりました!!
そんなわけで、花粉症に使えるツボをまとめ、さらに詳しく説明しますね。
花粉症の方はぜひぜひ実践してくださいね♪
【鼻水を止めるツボの話】
花粉症で鼻水が止まらない、ティッシュが何枚あっても足りない人必見!!
太淵(たいえん)を押してみましょう。
普段から優しく押すことで肺が強くなり鼻水を止める、風邪の予防、などの効果が期待できますよ(*´∀`*) pic.twitter.com/9SWVdCLz0l— ぴ~てん@イスクラ薬局六本木店 (@iskra6pongi) 2018年3月9日
こちらは太淵(たいえん)というツボです。
中医学には気血を全身に輸送する経絡(けいらく)という特殊なルートがあると考えられています。
経絡の中の全ての気は太淵に集まります。したがって、病状を判断する為に触ることもあるツボです(脈診といいます)
太淵は優しく押すことで【肺を強くし気を増やす】作用があります。
肺は水を降ろす機能(粛降)がありますので、
肺を強くすることで、水を降ろす機能が強化され、鼻水を止める
ということです。
【花粉症の目の痒み、鼻詰まりに効くツボ】 花粉症で目がカユカユ、鼻が詰まっている人は風池(ふうち)を押してみましょう。 風池は中医学的に花粉症の原因となる風邪(ふうじゃ)をとり、余分な熱を抑えるツボです!! 花粉症の目の痒みと鼻詰まりにもってこいのツボなです!是非お試しくださいね。 pic.twitter.com/yfDU3PIFaI — ぴ~てん@イスクラ薬局六本木店 (@iskra6pongi) 2018年3月16日
こちらは風池(ふうち)というツボです。
「風池」の「風」は、風病(花粉症、風邪、急なめまいや痙攣など)を指し、「池」は大きく池のように凹んでいることから「風池」と命名されました。500年以上使われている実績と歴史の長いツボです。
風池は体内に侵入した「風」を探すツボとされております。 中医学的に花粉は「風」とされていますので、体内の風を探す=体内の花粉を探す、と考えられます。
そして首より上の熱の症状を抑える効果もあります。
目の痒みの原因は「熱」であるので、熱を抑えることで痒みもやわらぎます。
さらに外部から侵入してくる悪いやつ(花粉、風邪など)から身を守ってくれる作用まであります。
この3つの作用があり、尚且押すことで効果も発揮しやすいので 風池は花粉症を抑えるのにうってつけのツボなのです!! 周りに花粉症にお困りの方がいましたら、押してあげましょうね(*´ω`*)
【肺を元気にして鼻詰まり頭痛を緩和するツボ】
花粉症で鼻づまり、頭痛にお困りの方は列缺(れっけつ)を押してみましょう。
列缺は鼻づまり頭痛を緩和し、さらに中医学的に花粉(外邪)から体を守る衛気(えき)を強くしてくれるツボです(*´ω`*)
前回の風池(ふうち)と合わせるとより良いですよ! pic.twitter.com/H5heQzbcU6— ぴ~てん@イスクラ薬局六本木店 (@iskra6pongi) 2018年3月23日
こちらは列缺(れっけつ)というツボです。
列缺は太淵と同じく肺を強くするツボです。
ですが、太淵との違いは頭痛に効く、気の巡りを良くする、という効果が期待できる点です。
花粉症で鼻が詰まりすぎて頭痛が発生した
花粉症になってからイライラする!!という方にピッタリのツボです。
以上です。
今年花粉症で困った方はツボもいいですが、やっぱり冬から漢方で体調を整える、のが一番効果があると思っています。
ですので、来年花粉症で苦しみたくない方は、今年の冬から漢方薬局に相談に行きましょうね!
過去のツボ記事はこちら↓
冷え性に使えるツボまとめ ちょこっとツボ講座 by ぴー店長
#2 ストレスを和らげるツボ