こんにちは、太田です。
今回の台風は9日に温帯低気圧に変わったものの、東京もひどく雨が降ったり止んだり、を繰り返しています。こんな時は身体もスッキリしたいですね。今日はそんな時にお勧めしたいハトムギスープをご紹介します。
すぐにスープを召し上がりたい方は、まずは良く洗ったハトムギを水につけておき、下ゆでしてからスープに入れてください。茹でたハトムギは冷凍保存も可能です。
ずぼらな私は、
良く洗ったハトムギ(一日分約20gが目安)
玉ねぎ丸ごと(小ぶりで火の通り易そうなもの)
出汁・お塩・ローリエを厚手のお鍋に入れて蓋をしてグツグツ。

玉ねぎに火が通ったのを確認し、味を調整しながら適宜お水や出汁を追加して再度加熱、ぐつぐつと言いはじめたら火を止め蓋をして一晩放置。
すると翌朝にはぷっくりと膨らんだハトムギと、芯まで火の通った美味しい玉ねぎスープができあがり。
ハトムギ(薏苡仁)の性質は涼で、胃腸を整え体の余分な水分を出してくれるはたらきが期待できます。
この長雨で、身体がだるい、むくみが気になる方は是非ハトムギをお食事にとりいれてみてはいかがでしょう。
ハトムギを使った、おいしいレシピが出来たら是非教えてください。
ブログ日記BLOG
中医学 の記事一覧
雨ばかりの時は、ハトムギスープを
2015/09/10
六本木の素敵な3人組による、Kanpo的おしゃべり・バックナンバー
こんにちは。イスクラ薬局六本木店太田です。
六本木店で毎月発行しているお便り、「ぱんだより」では漢方に絡めた「季節の良くある症状」をテーマに、3人の登場人物がおしゃべりをしています。(実はそれぞれにモデルの実在人物がいることはここだけの秘密です。)
今回は、このおしゃべりの内容をまとめてみましたので、もしよろしければご覧くださいませ。
①みんなが漢方に興味を持ったきっかけは?
②花粉症シーズン到来!
③春のよくある症状
④日焼け止め、飲んでる?
⑥早くも夏バテ?
⑦瘀血って?
①みんなが漢方に興味を持ったきっかけは?
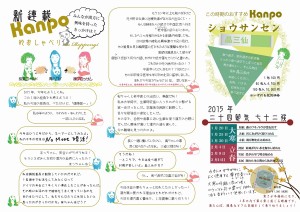
②花粉症シーズン到来!
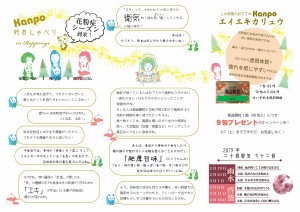
③春のよくある症状
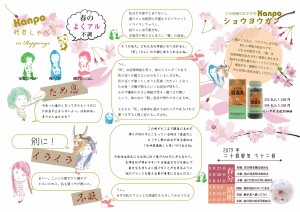
④日焼け止め、飲んでる?

⑤身体の除湿?
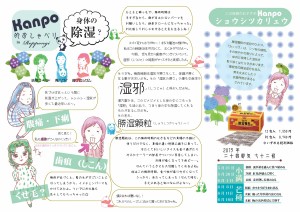
⑥早くも夏バテ?
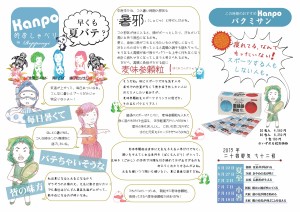
⑦瘀血って?
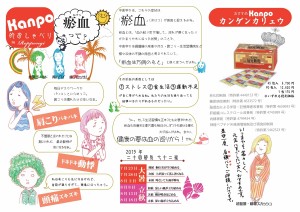
2015/08/08
暑い夏にお勧めのニンジン!
こんにちは、太田です。
7/10、7/11と2日続けて梅雨の雨から解放され、気持ちの良い晴れのお天気でしたね。私も早速洗濯機を回しまして、久しぶりにお日様の力で乾いた寝具でお部屋の中がさっぱりとして気持ちが良かったです。
雨が降っている間は肌寒く感じていたのに、太陽が顔を見せて晴れるとともに一気に暑さがやって来る。湿気で身体にダメージを受けていたかと思えば暑さで更にダメージを受け…。身体もこの季節の時期の変化についていくのは何かと大変です。
夏の疲れに例年おすすめしているのが、麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)という漢方薬。こちらのブログをご覧になっている方でも飲んだことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

麦味参顆粒は麦門冬と五味子の組合わせで身体に潤いを、人参(別名:朝鮮人参・高麗人参)で元気を補う処方です。暑くて汗を沢山かくような方には汗とともに体外へ流れ出た潤いと元気をチャージしてくれる、とても優秀なお薬です。
更に、今回は特に暑い日に元気が出ない時にお勧めしたいニンジンをご紹介致します。その名も「西洋人参」。微温の性質を持つ「朝鮮人参」に比べ、西洋人参の性質は涼。つまり、身体の余分な熱を冷ましてくれる性質があり、さらに元気と身体の潤いも補うことができるニンジンなのです。まさに一石二鳥ならぬ、一石三鳥なニンジン。
熱くて暑くてたまらん!という方は是非、西洋人参の力もお試しいただくとよろしいかもしれませんね。
是非一度店頭にてご相談ください。

2015/07/13
初夏の楽しみ♪
こんにちは。気温・湿度があがると溶けてしまいそうになるため、夏も元気に過ごせるよう今からせっせと養生に励む田宮です。
先日、祖父の家に遊びに行ってきました。祖父の家には色々な草木が植わっています。植物好きな家族の希望により、数年前には桑の木が加わりました。5月頃からこの木にたくさんの桑の実が色づいてきます。
桑の実はこのまま食べても甘酸っぱくて美味しいです。でも祖父宅では毎年黒く実った実を取っては冷凍、取っては冷凍を繰り返してたくさん集まったら、ぐつぐつ煮込んでジャムを作ります。これがまた濃厚でパンに塗って食べるのとやみつきです♪まだまだジャムにするには実の量が足らないので、食べたいのを我慢して収穫の日々です^^;
待ち遠しいですね~。
さて、この桑の実は生薬としても使われており、「桑椹子(そうじんし)」という名前で呼ばれています。しかし日本で普段使う漢方薬の処方の中には、残念ながら桑椹子は出てこないんです。もっぱらジャムやお酒などで食することが多いようです。
【桑椹子】
【性味】甘・寒 【帰経】心・肝・腎
【中医学的効能】滋陰補血・生発烏髪・生津・潤腸通便
身体にも髪にも良い桑の実、機会がありましたら皆さんも食べてみてください。
2015/06/23
夏も近づく八十八夜♪ 漢方薬にも「お茶」が含まれる処方があるんです。
今年は5月6日が立夏ですが、もうすでに初夏の陽気の日が続いており、これから梅雨がやってくるのが信じられませんね。太田です。
そしてその立夏の一歩手前の本日、5月2日は、立春から数えて八十八日目、「八十八夜」です。昔からこの日に摘まれたお茶を飲むと長生きする、と言い伝えられており、縁起物として珍重されてきました。そのため、現在でも緑茶の産地では茶摘みのイベントが行われているようです。
さて、お茶と一口に言っても色々なお茶がありますが、煎茶・玉露・抹茶・玄米茶・ほうじ茶…これらすべて「緑茶」に分類されます。お茶の色だけを考えると、なんだか不思議な感じがしますね。中国では、緑・白・黄・青・紅・黒茶…と発酵度によってさまざまなお茶の種類があります。
その中でもツバキ科TheaceaeのチャCamellia sinensis O.KUNTZEの若葉を「茶葉(ちゃよう)」と呼び、性質は涼性、上部の熱を冷ます、渇きを止める、消化を助ける、利尿、といった事が期待できます。
この茶葉を使用している漢方処方が感冒時の頭痛に用いられる「川芎茶調散」(せんきゅうちゃちょうさん)、イスクラの製品ですと「頂調顆粒」(ちょうちょうかりゅう)です。
普段嗜好品として気軽に飲んでいる、あの「お茶」が漢方薬に含まれている…と考えると、やはり医食同源、普段の食事も気をつけながら過ごしたいなと思うのです。
以前の六本木店のブログにもお茶の記事がありましたので、こちら「頭スッキリ、血圧、コレステロール、ダイエットにも!素晴らしい「お茶」の力」も是非ご覧ください。
さてさて、イスクラ薬局六本木店も明日、3日日曜日から6日水曜日までお休みをいただきます。みなさま、どうぞ食べ過ぎや飲みすぎ、はしゃぎ過ぎに注意して楽しい連休をお過ごしくださいね♪
2015/05/02








