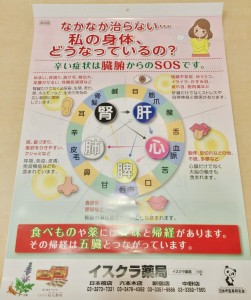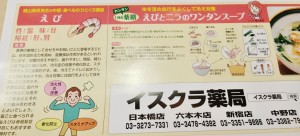昨日は久しぶりの雨で乾燥していた空気が少し保湿され、お昼過ぎ頃はとても心地よかったですが、また一気に冷えましたね。これからどんどん寒くなるようですね。こんにちは、櫻井です。皆様カゼなどひいておりませんか?
今日はそろそろ店頭に並びだした「イチゴ」のお話をしたいと思います。イチゴと言えば、もともとは野イチゴのことで、これは石器時代からヨーロッパやアジアで食べられていました。私たちが目にするような一般的なイチゴが栽培され始めたのはおよそ200年ほど前、オランダで開発されたものがそのルーツです。日本には江戸末期にオランダから長崎へと伝えられ、当時イチゴと言えば当時は野イチゴのことだったので、それと区別するために「オランダいちご」と呼ばれていたそうです。しかし、そころにはまだ一般的に定着するようには至っていません。その後明治32年、1899年に福羽博士が新宿御苑で『福羽』という品種を開発してから日本での本格的な栽培が始まりました。

Winter strawberry (Rubus buergeri) / coniferconifer
イチゴの赤い部分は果実じゃない!
私たちが通常食べている部分は実は果実ではなく、あれは「花たく」という花の部分が発達したものであって、本来の果実は表面の粒粒の一つ一つなんです。あの中に小さな種が入っているので、赤い部分は果実のベッドだったんです。甘味があるので、果物と思われていますが、野菜と分類される説もあり、農林水産省も「イチゴは野菜」という判断をしています。イチゴを丸く形よく生長させるには、すべての雌しべを受粉させる必要があり、受粉していない雌しべがあると形がいびつになってしまうそうです。たまに見かける不格好なイチゴはそんな理由からだそうなんです。
イチゴの栄養
イチゴはそのほとんど90%ほどが水分で、その他糖質が10%ほど。タンパク質、食物繊維がそれぞれ1%、総カロリーは100gで約35kcalです。イチゴはなんといってもビタミンCが豊富なことで有名ですね。100g中に約80mgと、食品の中でもトップクラスです。7~8粒食べれば一日に必要なビタミンC量(100㎎)をまかなえる計算です。ビタミンCの美容効果はもう説明する必要はありませんね。コラーゲンの生成を助けて、皮膚の張りと潤いを保ちます。これからの時期は、おやつにイチゴを食べるて美肌対策をしていきましょう。ビタミンCには美肌効果だけでなく、抗酸化作用や免疫力を高める力もあるので、美肌だけでなく健康面でもおすすめです。そのほか、βカロチン、カルシウム、カリウム、アントシアニン、ペクチンなども含まれ、興味深いところでは、キシリトールを100g中300㎎も含んでおり、虫歯予防にも効果的と言われています。
イチゴの驚くべき力!
最近の研究では、イチゴエキスがアルコールによる胃粘膜の傷を小さくすることを動物実験で実証したというデータもあります。良く昔は、「お酒を飲む前に牛乳を飲めば胃粘膜を保護してくれる」なんて思われていましたが、あれをイチゴがほんとにやってくれるそうです。まだ実験段階で証明されてたという話ですが、胃の保護のために、「お酒の前にイチゴ」は案外効果的かもしれません。ちなみに、イチゴがアルコールの分解を助けてくれるとかそういう話ではないので、あしからず。
もう一点興味深い研究があります。それは、イチゴには花粉症などのアレルギー症状を抑えてくれる効果があるらしいのです。ネットでも「楽になった!」という声がちらほら見かけられます。イチゴが手軽に入りやすくなるのはちょうど冬から春にかけてなので、体調を整え花粉対策のために身体を準備していくにはぴったりの時期ですね。しかしこのデータが得られたのは、一日15粒から20粒のイチゴを毎日1週間たべた結果だそうで、ひどい時期だけを狙えばそのぐらいは食べれそうですが、毎日となると、なんかほかのところの調子を崩しそうです。
ヘビースモーカーはイチゴをしっかり食べることをお勧めします。とある研究ではたばこ一本につきビタミンCは20mg失われていくというデータもあります。喫煙者にとってビタミンCの補給は必須です。イチゴならおいしく補給できて、ビタミンCがメラニンの発生を抑えてくれるので、シミやそばかす対策にも効果的です。
水洗いは手早く。ヘタは食べる寸前にとる。
ビタミンCは熱に弱いので、生でそのまま食べるのが一番です。また、痛みやすく、痛んでしまうと栄養価も落ちてしまうのでなるべく早く食べましょう。ヘタを取って洗うと水っぽくなってしまい、さらにビタミンCも水に溶け出てしまいやすくなります。ヘタは付けたまま手早く洗い、食べるときにとりましょう。ヘタの部分と先端部分では糖度が3度ほども違うので、ヘタの部分からたべると最後までおいしく食べられます。1パックを一人で食べきるのは大変なので、そんな場合は、ラップに包んで野菜室に入れておけば2~3日持ちます。洗って水気を切って、ヘタを取ってから容器に入れてつぶれないようにして冷凍すればもう少し持ちます。
美味しいイチゴを選ぶには、ふっくらとして、粒粒がしっかりしているもの。同じ品種の場合はより濃い色をしているもの。そしてヘタくるんと反り返っているものほど甘みがあるそうです。

Strawberry Forest / Focx Photography
中医学的にイチゴを見る
イチゴは涼性で余分な熱をとる力があり、冷え性の方は食べ過ぎ注意ですが、潤いを補い熱をとる力があるので、熱がこもって火照ってしまう人、血圧高めの人にはおすすめの食材です。その他、胃腸を元気にし、消化を助ける力があるとされているので、慢性的な下痢にもおすすめです。喉を潤してくれるので、のどの痛みを伴う発熱や空咳などにもおススメ。
今ではハウス栽培が主体となりほぼ通年でイチゴは食べられますが、5-6月の初夏が本来の旬です。果物の少ない春先のビタミン補給にはピッタリだったんですね。自然の時計に狂いはありませんね。クリスマスに向けてイチゴの需要は増えていきますが、一般的に価格も手ごろになってくる1月~2月頃。しっかり自然の恩恵にあずかりましょう!