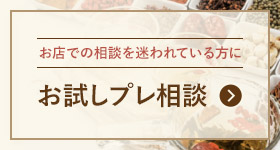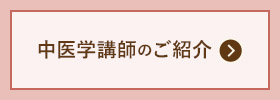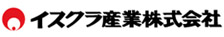漢方の得意分野の一つに婦人科があります。当店のお客様も7,8割が女性です。女性は一生を通じて初潮、妊娠、出産などいくつものステージを経て、ご体調ご体質がダイナミックに変化し、それに伴い、様々な心身のお悩みが生じてきます。病院に行ってみてもらうほどの症状ではないけれど、やはり辛い、もしくは病院に行っても対応してもらえない、そんなお悩みを抱えていらっしゃる女性も多いのではないでしょうか? 今回はそんな …
続きを読む中医学を学ぼう!
- 美容から症状別まで役に立つ中医学についてご紹介。
女性と漢方薬|悩みや症状別におすすめの種類を紹介
漢方薬の効果について|民間薬との違いや副作用についても
大変嬉しいことに、最近漢方薬を身近な存在に感じて下さる方が増えてきました。反面、漢方薬の定義や、効能効果についてご存じの方は少ないかもしれません。自己判断で市販の漢方薬をネットで購入して服用される方も多いと聞きます。今回は漢方をより身近に感じて頂けるよう、そして適正に服用いただけるよう、漢方薬のご紹介をさせて頂きます。 漢方薬とは? 古代中国から継承され、体系化された医学理論および臨床的な治療法が …
続きを読む漢方薬と西洋薬の違い|メリット・デメリットや併用についても
同じ“薬”と名がついていても、漢方薬と西洋薬ではそれぞれ特徴があり、違いがあります。今回は、その特徴と違い、それぞれのメリット・デメリットや両者を併用される際の注意点などもご紹介いたします。 漢方薬と西洋薬の違い まずは漢方薬と西洋薬の違いについて解説します。 漢方薬は複数の生薬の組み合わせ 漢方薬は、数種類の生薬を組み合わせたものです。生薬は、植物・動物・鉱物などを乾燥させたり、酒に漬けたり、蒸 …
続きを読む漢方薬の適切な飲み方|飲みやすくする方法も
漢方薬は基本的には煎じた液を服用するものですが、毎日飲む量を煎じなくてはいけないので、忙しい現代では難しいことかもしれません。最近では煎じ液を加工したエキス剤や錠剤など、手軽に利用できる漢方薬が出回っています。実は、漢方薬も西洋薬と同様、適切なの飲み方というものがあります。たとえ体質体調に合わせた処方を出されても、もしも飲み方が間違っていたら、その効果も半減してしまいますのでこんなにもったいないこ …
続きを読む女性ホルモンの調節作用のある漢方薬|女性特有の悩みを解消
女性は一生を通じて、様々な体の不調に悩まされます。病院に行っても『女性ホルモンのバランスが乱れている』と言われることが多いかと思います。では、この女性ホルモンを整えるには何をしたらよいのでしょうか?中医学では、女性ホルモンと関係が深い五臓六腑は『腎』『肝』と考えます。 『腎』は腎臓も含む生殖機能、泌尿器系と密接な関係のある機能であり、『肝』は肝臓そのものと、自律神経、内分泌系と密接な関係のある機能 …
続きを読む「腎」の病理
腎は生命の源 「腎」は、生命活動を維持する物質(=精)を蓄えるところと考えられてきました。 ・ 腎は精を蔵す ・ 腎は水をつかさどる ・ 腎は納気をつかさどる ・ 腎は骨をつかさどり、髄を生じ、脳を満たす ・ 腎は 裏 、膀胱は表 具体的に定義すると、泌尿器系、生殖器系、ホルモン系、中枢神経系お…
続きを読む「腎」の生理
腎の働きを知ろう 五臓の生理についてもいよいよ最終回。今回は中医学で生命の源ともされる「腎」のお話です。 西洋医学での「腎臓」の働きはみなさんご存知かと思います。簡単にいえば、体液から不要な物質を濾し取り、尿として排泄する役割を持ちます。この「腎臓」の機能が衰えてしまうと、体に老廃物が残ってしまい、…
続きを読む「胃」について
今回の「中医学基礎講座」は「胃」についてのお話です。「胃」は六腑の一つであり、五臓の「脾」と表裏の関係にあるとされます。「脾胃」とまとめて呼ばれることも多く、食物を消化し「気」を生み出すための非常に大切な器官です。
続きを読む銀翹解毒散(ぎんぎょうげどくさん)
毎年、秋口から冬にかけて乾燥する時期になりますと、カゼがはやってきます。最近、薬局でもカゼ薬を買いに来られるお客様が増えています。 実は、カゼにもタイプがあって、漢方では、そのタイプを見極め、お薬を使い分けます。漢方のカゼ薬といえば『葛根湯』がよく知られていますが、実は、合わない場合もございます。赤い顔をしていたり、のどの痛みが強いときに、『葛根湯』はおすすめできません。葛根湯は、ゾクゾクと寒気が …
続きを読む「気」について【気滞】
まずはもう一度、「気」についての復習を‥ 中医学でいう「気」を簡単に言えば、「体を動かすエネルギー」。パワーの源です。この「気」には様々な働きがあります。 ・ 温煦(おんくさよう)作用‥体を温める働き ・ 推動(すいどうさよう)作用‥ものを動かす働き ・ 営養(えいよう)作用‥栄養にかかわる働き そ…
続きを読む