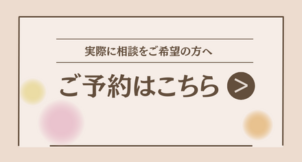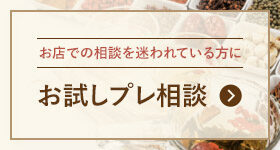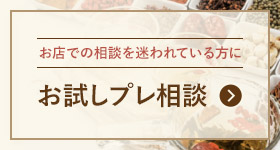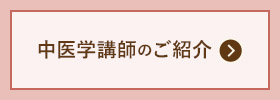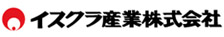月経の量は、1回目でお話しましたように、生理学的には全量20-140 mlという正常範囲があり、その範囲内で、出血している量を個人的に少ないと感じていると思われます。
中医学では、月経血(経血)の量は、月経の状況やその人の体質を知る大切な事柄になります。
経血は、五臓六腑(東洋医学的な臓器)にある血や、全体的に血を調節している血海という所が満たされることで産生されると考えられています。
経血量が少ない場合は、その血海が満たされていないために起こります。
満たされない理由には、血を作る機能が弱い場合、五臓六腑や子宮などに血を動かす経脈の流れが悪い場合があります。
血を作る機能は五臓六腑の機能が十分であることが必要になります。
それは、食事から栄養を吸収して血を作る、そしてその血を五臓六腑に配り、貯蔵するという機能になります。
食事をすることは生活の一部であり、当たり前の事のようになっておりますが、
皆さまの生活では、いかがでしょうか。
食事の量に変化はありませんか。

食事の量が減ると、関連して血をつくる量が減り、五臓六腑に貯蔵する血の量が減り、血海が満たされなくなります。
次の食事までにおなかが空かないのは、食事を消化する機能が落ちています。
消化の機能が落ちると、食事から栄養を吸収するのに時間がかかり、食事の量や食事の回数も下がってきます。
また、体質的に消化機能が弱い場合もあります。
こういう場合は、長い間、機能が弱いので、血を作る機能自体が徐々に弱くなり、
五臓六腑の血や血海が満たされなくなった期間も長くなります。
もう一つの理由に、経脈という考え方です。経脈の中でも、腹部の中から始まり体の中央前を上がり、
月経や妊娠にも関与する経脈があります。この経脈は冷えなどがあると、
腹部や消化に携わる所が滞るようになります。
経血量が少ないことは、体の他の部位の血も少なくなります。顔色がやや黄色みがかったり、皮膚や髪につやがなくなったりすることが見られます。もう少し、症状が長くなると、めまいを感じたり、目がかすみやすくなったり、
ふらっとたちくらみを感じたりします。

まず、お食事が美味しく食べられているかどうか、食後に胃もたれがあるか、外食で一人前食べれなくて残すことがあるかどうかなど、ご自身でご確認してみてください。
そして、冷えやすい環境にいる時間が長いかどうか、婦人科のお病気があるかどうか、これらもご確認してみてください。