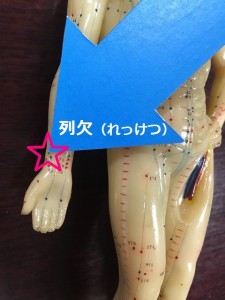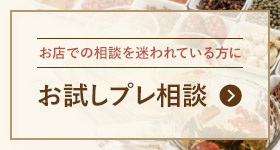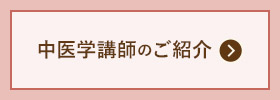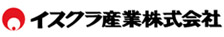ブログ日記BLOG
薬膳・養生・季節の対策 の記事一覧
ツボでかぜ予防をしよう ~実践的な『ツボ』の話~
2016/11/05
眠れないのは誰のせい?&精子アプリ「Seem」その後
「眠れないのは誰のせい?」
…こんなパンフレットがございます。
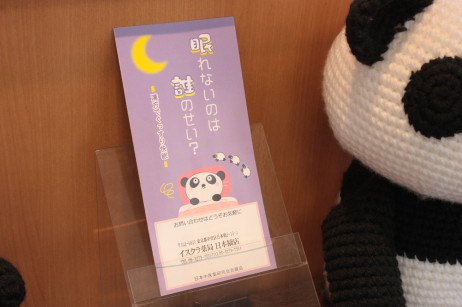
今まで、「しっかり漢方飲んで、養生守ってる私には不眠なんて無縁だわ〜(^-^)」
と上から目線だった、杉村敦子![]() でございますm(_ _)m
でございますm(_ _)m
ところが…ですよ、5月末の、とある夜
いつものように「早く寝なくっちゃ良い卵育たなくなっちゃう(^^;;」
との大義名分のもと
家事もそこそこに、23:30にベッドに潜り込んだ私。
はい、いつものように「スンナリ眠って、スッキリお目覚めセット」もしっかり飲んで!
なのですが…
横になった途端に、その日にあった事があれこれ頭に浮かんできて
…(*^^*)……>_<……( ̄^ ̄)ゞ…!(◎_◎;)…(°_°)…
(嬉しい事、悲しい事、腹が立つ事、情けない事、困った事etc…)
1日のうちにいろいろな感情山盛りとなったせいか、目を瞑っているのに目が爛々!(◎_◎;)
「明日の仕事に差し障っても…」と焦り出し
24:30…ミンハオ追加(ついでに軽くヨガポーズ)
25:30…奥の手の西洋薬(!?)
26:30…ブランデー少々(薬剤師にあるまじき(^^;;)
「とにかく早く寝なくっちゃ!」とばかりにアレコレもがいて
夜中の3時過ぎにやっと眠りに落ちたようでした…
きっと日々眠れない方のお悩みは、こんなもんじゃないでしょう…>_<…
でもお気持ち、少しだけ共有させて頂けたように思います。
交感神経の興奮過剰は、もがくほどに悪化します。
時には眠れない事を諦めて、眠気がくるまで雑用もいいのかも知れません。
(でも、ネットは禁物ですよ。ブルーライトは脳を刺激しますのでますます不眠に)
翌日からは日々の漢方見直して、早期に辛い体験を脱出した私ですが、
「不眠が認知症の第一歩!」と言う論文もございます。
「睡眠薬に頼らない自然な眠り」
を目指して漢方をお役立ていただければ幸いです。
そして前回ブログのその後です!
イスクラ新人スタッフ君の…精子アプリ《seem》結果ご報告‼️
御年30歳!
濃度 184.0×106/mL
運動率 34.6%
「さすがだね!」「良かったね〜」などと結果を讃えつつも…
「これじゃ、ビフォアー&アフターの 検証出来ないじゃん-_-b」
と、内心ちょっと残念でもある、悪い心を持った杉村でした;^_^A
そして、
日本橋ブログまでもご覧下さっている「あっ晴れ」のお客様
いつも温かいコメントと応援、有難うございますm(_ _)m
今日も日本橋で頑張りまーす(*^_^*)

2016/07/13
冬にジンギスカンがおすすめな理由
こんにちは、櫻井です。
寒い日が続いてますが、皆様いかがお過ごしですか?
私の地元、北海道の北見市では、北見極寒焼肉まつりという無茶な大会が有ります。-10℃以下の野外で焼き肉をするんですが、これが意外に冷えない。まぁ寒くないといえば嘘になりますが、牛肉には身体を温めてくれる力があるからではないかと思っています。
でも牛肉以上に温める力が強いのが羊肉なんです。
羊肉料理といえば私は真っ先にジンギスカンを思い浮かびますが、皆様はいかがでしょうか。北海道育ちの私はこれで育ったといっても過言ではないぐらい、小さいころに沢山他食べた料理です。ホームセンターではジンギスカン用の使い捨て鍋が当時100円で売ってましたし、とにかくみんなが集まればジンギスカンでした。
安くて、おいしくて、野菜も一杯食べられます。いや~思い出しただけで生唾ものです。小さい頃から食べているので、何がくさいのやら全く気になりませんが、慣れていない人にとってはどうしても気になってしまう臭いのなんでしょうねぇ。今日はそんな「ジンギスカン」のお話です。
「ジンギスカン」って?
私が知ってる「ジンギスカン」はマトンの肉をタレに漬け込んだもので、もやしやキャベツと一緒に焼いて食べるもの。最後にはそのタレでうどんを食べる料理です。いまは随分と小洒落たというか、臭みのない生ラムなんかをつかったものもありますね。ちなみにこの「ジンギスカン」っていう料理名の由来は、私が小さいころ聞いた話では、「モンゴル帝国を築いた、ジンギス・カン(チンギス・ハン)が遠征の際に兵士に食べさせたもの。丸い鍋は兜をつかっていた名残。」と言われていました。今の今までそれを信じて疑わなかったのですが、調べてみると、実はジンギスカンとチンギス・ハンはまったく関係ないそうです。え??そうなの??
どういう風に生まれたかというと、、、
そもそも羊肉が日本で食されるようになったのは明治以降。それも軍や警察、鉄道員の制服に使う羊毛が大量に必要になったため、綿羊の飼育を奨励し増産を図るためと、農家の収入を上げるために羊肉の消費を伸ばそうとした政策が背景にありました。
しかし当時は羊肉を食べる食文化は無く、まったく定着しませんでした。そこで、農商省(今の農林水産省)は日本人の舌にも合う羊肉料理を研究し始め、その開発を、お茶の水女子大学の前身、東京女子高等師範学校に委託したそうです。そして、1920年ごろに原型ができたと言われています。
初期のころの「ジンギスカン」は、といってもまだこのころは「ジンギスカン」という名前もなかったんですが、ただ羊肉を焼いてタレをつけて食べるという、中国、満州地方の清真料理、「カオヤンロウ」をヒントに作られものでした。でもやっぱりそう簡単には定着しなかったそうです。
普及は戦後の食糧難・衣料不足から
ジンギスカンが本格的に普及し始めるのは、第二次大戦後。戦後の食糧不足や衣料不足を背景として、羊肉消費促進を政府はさらに推し進めます。その運動の中心が、羊毛用の羊が多く飼育されていた北海道だったと言われています。当時は喜んで食べたというより、必要に迫られてしぶしぶだったんでしょうね。
北海道では、高価な牛肉にくらべ、羊肉が安価で手に入り、輸送時間も短く、新鮮なうちに食べることができたため、臭みがさほど強くなく受け入れられやすかったということも、今のように北海道でジンギスカンが定着した理由かもしれません。その後、つけダレに浸して臭みを消したり、リンゴなどを入れて硬いマトン肉を柔らかくしたりなど改良が施され現在の「ジンギスカン」になります。
ジンギスカンには、たれに付け込んだ「味付け」と、たれにつけない「生」の2パターンあり、醤油ベースの果実や香味野菜などで作ったたれにつけた味付けジンギスカンは、においとコクが強いマトンが多いイメージでしたが、ラム肉、マトンともどちらでもあります。
「マトン」とは、生後1年以上(厳密にはメスまたは去勢されたオスのうち永久門歯が2本以上のもの)、ラムはそれ未満のものです。
中医学的にみると
羊肉は温熱性で、温める力がとても強いとされています。北京でも羊肉のしゃぶしゃぶは冬の風物詩と言えるほど。冷え性への養生で必ず挙げられるのも羊肉です。胃腸も元気にしてくれるので、食欲不振や痩せ、冷え症にはもってこいで、産後の養生や乳汁の分泌促進にも効果があるといわれていいます。
加えて、エネルギーを補い、心の安定をはかり動悸を鎮めてくれる力や、足腰の冷えを癒し、痛みを緩和し、体力の回復にも役立つ素晴らしい肉です。しかも羊肉に含まれるL-カルニチンは、食べても脂肪が付きにくいという何ともうれしい効果も持ち合わせています。
結局なぜ「ジンギスカン」は「ジンギスカン」なのか?
ジンギスカンは、実際のモンゴル料理とはまったくかけ離れた中華料理を元に考え出されましたが、名前はモンゴルのイメージだそうです。満州国初代総務長官の駒井徳三さんがモンゴルでも食べられていた羊肉からイメージでつけたという説が有力だそうです。「羊肉?モンゴル?チンギスハン? じゃあジンギスカンでいいじゃん。」とかなんとか。。
余談ですが、北海道のおじいちゃんおばあちゃんは、羊を「メンヨー」と呼んでいました。私はてっきり北海道の方言だと思っていましたが、漢字があったんですね。乳牛と同じ意味合いで、綿をとる羊で「綿羊」なんですね。
中医学的に見て、身体を温める力が強い羊肉は、寒い冬には是非摂りたい食材です。肉類の中で一番温める力が強いので、冷え性の人には是非試して頂きたい食材です。スーパーでは余り見かけませんが、今はネットでも買えますしね。夏よりも冬に是非食べて頂きたいです。上記の写真のように最近話題のパクチーと炒めても美味しいそうですよ。
今では流通事情も当時に比べて断然よくなっていますし、臭いなんて気にならない羊肉も手に入ります。是非皆さんもジンギスカン、食べてみてくださいね!
2016/01/27
スーパーで買える食材こそ『スーパーフード』だ!
安くて美味しい”スーパー(の)フード”
こんにちは。櫻井です。健康といえば、スーパーフードなどというものが近頃取りざたされることもありますが、健康的な食品は何も都会のおしゃれなお店に売ってるものばかりではありません。スーパーで一番安くなっている旬の野菜たちも、素晴らしい力を秘めています。
1月に食べごろを迎える野菜はたくさんありますが、今日はその中でも春菊、ブロッコリー、小松菜と普段目立たないけど、素晴らしいポテンシャルを持った野菜たちにスポットを当てたいと思います。
春菊の栄養
春菊はビタミン、カルシウム、葉緑素が豊富で、β-カロテンの含有量はほうれんそうやこまつなより上の100g当たりなんと4500mg。これは、ビタミンAで換算すると成人女性が一日に必要とする量の2/3と言われています。その他、ビタミンB2、C、カルシウム、カリウム、鉄分も多く含まれています。春菊のあの独特の香りは13種類の精油成分によるもので。それらの香りが胃腸を動かし、食欲増進とともに、腸を潤し便をでやすくるする作用もあると言われています。春菊の緑色の色素成分は、コレステロール値を低くし、血栓を予防する効果があります。「葉緑素」ともいわれる栄養成分で、発がん抑制にも効果があります
働き・・・食欲増進、便通を良くする、高コレステロールに、血栓の予防に、抗癌、美肌効果。
中医学でみる「春菊」
春菊は実に様々な効能を持ち、古くから漢方薬の原料として使われ「食べる風邪薬」の異名を持つほどです。性味は寒熱の偏りがない平性で、脾、胃、心、肺、肝に通じると言われ、気滞、痰飲、瘀血を改善します。あの独特の香りで気を巡らせるので、月経前の感情の乱れにもおすすめの食材です。胃腸の働きを良くし、胃もたれやお腹のはり、食欲不振を改善する作用もあるとされています。また血液を流れやすくする力や、痰を切れやすくする力、そしてたっぷりと含まれるベータカロチンやカルシウム、ビタミンCのおかげで美肌対策にも効果的です。
働き・・・精神を安定させる、月経前の気分の不調に、胃腸の働きを良くする、胃もたれ・お腹の張りを良くする、食欲増進、血流を良くする、痰を切れやすくする

春菊ばくだん。 at ビストロ カルネジーオ http://miil.me/p/40k8q / JaggyBoss
ブロッコリーの栄養
ビタミンC、βカロチンが豊富な美容食品
ブロッコリーはとっても栄養価が高い食品です。生のブロッコリーに含まれるビタミンCはなんとレモンの約2倍!キャベツと比べると約3~5倍も含まれています。その他、βカロチン、ビタミンB1、B2、カリウム、リン、食物繊維なども豊富に含む、栄養満点の野菜です。
ビタミンCの効果は数えきれないほど沢山ありますが、今回その中でも注目したいのは、免疫力の強化と、シミやそばかすの予防効果。ビタミンCは非常に色素沈着予防効果が高いビタミンで、某化粧品会社さんのシミ対策化粧品の中身は、濃度の濃いビタミンCだというのを聞いたことがあります。美白化粧品として使用できるほど、ビタミンCの色素沈着予防の力は高いのです。
そしてこちらもブロッコリーには多分に含まれるβカロチン。粘膜を強化し、カゼなどの感染を予防する働きがあります。空気が乾燥し、カゼが流行るこの時期にはうってつけですし、粘膜を保護するということは、もちろんお肌にも良いので、ブロッコリーも先日の小松菜と同じく、食べる美容サプリといえます。
働き・・・カゼの予防、粘膜強化、シミやそばかすの改善、美肌効果
抗がん作用にも注目!
近年、ブロッコリーがもつ抗がん作用に注目が集まっています。ビタミンCなどによる活性酸素の除去はもちろんですが、ブロッコリーには癌を引き起こす原因となる突然変異を抑える物質、メチルメタンチオスルホネート(MMTS)という物質が含まれているそうです。しかしこの、MMTSはゆでて食べるだけでは簡単に摂取できないそうで、細かく刻んだり、水と一緒にすりつぶすことで初めて生まれる物質なんだそうです。抗がん作用を狙うなら、ブロッコリーをミキサーにかけてジュースにして飲むのがおススメです。注意いただきたいのは、時間がたつと変質してしまうので、ジュースにしたら新鮮な間に素早く飲むようにししましょう。ブロッコリーはその他にも、スルホラファンという発がん性物質の作用を抑え、ピロリ菌抑制効果もある物質も含んでおり、健康管理のためには最高の野菜の一つといえます。
さらにさらに、ブロッコリーは葉酸の含有率がとっても高い食材でもあります。葉酸は、細胞が増えていく時や赤血球が増えるときに必要不可欠なビタミンで、貧血の予防や動脈硬化の予防に効果があるほか、妊娠中やべビ待ちの方にも必ず取ってほしいビタミンですし、離乳食としてもおすすめです。
働き・・・抗癌作用、葉酸が豊富
中医学的にみると
ブロッコリーは平性なので、毎日食べても冷えたり火照ったりすることがありません。中医学的効能では、五臓を養い調整し、関節を強く丈夫にして、気を巡らせ、動きを滑らかにするとあります。また、虚弱体質を改善し、胃腸を元気にして、身体に元気を与える食材で、胃腸機能低下時やお年寄りにもおすすめの食材です。中医学でもガンを抑制する「制癌」という力を認めている食材でもあります。潤し、便通を良くする作用があるので、お腹が冷える、または下痢気味の場合は食べ過ぎないようにしましょう。
働き・・・虚弱体質改善、胃腸を元気にする、便通を良くする、がんを抑える
小松菜は【食べる美容サプリ】
小松菜は、カルシウム、ビタミンA、ビタミンC、鉄、カリウム、食物繊維を沢山含んでいます。ほうれんそうと栄養価は似ていますが、カルシウムはなんと5倍で、野菜の中でもトップクラス。生長盛りのお子さんや骨粗しょう症の予防には勿論のこと、イライラを鎮める力もカルシウムにはあります。さらに細胞内の保水成分を働かせているのもカルシウムです。カルシウムが不足するとシワや乾燥の原因となるので、透明感とはりのある肌を作るにはカルシウムは欠かせません。しかも小松菜には、コーラゲンの主原料である「プロリン」というアミノ酸が豊富に含まれており、しっかり食べることでお肌ぷるぷる効果も期待できます。さらにビタミンAとビタミンCは小松菜100gを食べると一日の必要量を補えるほどたっぷりと含まれています。ビタミンCは天然の美白成分としても有名ですよね。こうしてみると、栄養豊富な小松菜は食べる美肌マルチサプリといえます。食物繊維も豊富で、便通を良くし、高血圧の予防や、大腸がんのリスク軽減など、優れた解毒効果も発揮します。βカロチンも多く含んでいるので、抗酸化作用、カゼ予防、美容効果や老化防止などにも好影響です。
働き・・・苛々を鎮める、カゼの予防、骨を丈夫にする、美肌
中医学・栄養学的に見る「小松菜」
小松菜は平性で寒熱の偏りがなく、たくさん食べても冷えたり火照ったりすることがないため、毎日たべていただきたい食材です。小松菜は気を巡らせ、ストレスを和らげ、胃腸を良く動かし、余分な熱をとり、潤いを補ってくれます。
おススメレシピは気を巡らせる春菊と、潤いを補う胡麻とあえた【小松菜と春菊の胡麻和え】。ストレスにも便秘にも、お肌にも良いスーパー小鉢です。小松菜は灰汁が少なく、さっとゆでるだけで食べられます。下ゆでも、水にさらす必要もなく、生のままでも食べられます。βカロチンは油と相性が良いので、炒め物にもおすすめですが、ビタミンCは熱に弱いので、できるだけ調理は短時間で行いましょう。
働き・・・ストレス緩和、胃腸を元気にする、のぼせやほてりを鎮める、潤いを補う、便通を良くする
『スーパーフード』というのは、日本スーパーフード協会によると、「有効成分を突出して多く含む食品」ということらしいです。突出の基準がどれだけかは定かではありませんが、個々に上げた春菊やブロッコリーや小松菜も十分にたっぷりと栄養を含んでいます。身体は日々の食事からつくられるので、見つけにくい、手に入りにくい、毎日の食卓にあげにくいでは意味がありません。そして何よりも経済的な負担となるような食材は、健康とは言いがたいとおもいます。
旬の食材と言うのは、安くて旨くて、その時期を健康的に乗り切るための自然からの恵みです。是非その恵みを最大限享受してくださいね!
2016/01/20
咳と喉のトラブルには、温かい梨のデザートが”効く”!
こんにちは櫻井です。
ずっと続いた雨が開けたら、秋、来ましたね。今年は確かに暑かったですが、なんだか残暑も厳しくなく、拍子抜けした感があります。最近は朝夕は若干肌寒くなってきましたね。お店でも咳や喉の痛みのお悩みが増える頃です。ということで、去年からこのブログを御覧頂いている方にはもうおなじみ、梨の季節がやってまいりました^^
では今年も、肺によく、咳に良い【梨のはちみつを使った薬膳デザート】をご紹介します。
【梨とはちみつの潤肺デザート 氷糖燉梨子】
① ヘタの部分を蓋になるように切っておく。
② 実の部分の芯をスプーンでくりぬき、はちみつ(大1)とお水(大1)、生姜スライスを1かけ入れる。
③ ①の蓋をして、お皿に入れて蒸し器で40~50分蒸す。柔らかくなり皮にヒビがはいってきたら完成。
*カゼの初期で若干肌寒さを感じる場合は、生姜がいいです。味付けにシナモンや棗、レーズンを入れてもおいしいです。シナモンは大熱といって温める力が強いので、喉トラブル時は避けて、それ以外ではスパイス程度に極小量にしましょう。
*蜂蜜の代わりに氷砂糖(3つぐらい)も良いです。本来の薬膳は氷砂糖でつくります。氷砂糖には余分な炎症の熱を沈める力があります。喉のトラブル解消としての効果を重視するなら、氷砂糖がオススメ。
**氷砂糖の代わりに【板藍のど飴】を入れてみると更に良いと思います!
潤いたっぷりでこれは喉によいですよ~~
あつあつで食べてくださいね。ジュースもしっかり飲みましょう。これはジュースというより咳止めシロップです。のどにとってもよいですよ。私も早速、家に帰って作ってみました。切ってくりぬいてはちみつと水を入れて蒸すだけ!すっごく簡単!
梨とはちみつの中医学的効能
梨
【性味/帰経】
寒、甘、微酸/肺、胃
【働き】
生津潤燥:潤いを生み、渇きを癒す。
清熱化痰:余分な熱をとり、痰をなくす。
除消渇:渇きを改善する。糖尿様の症状(渇き)を改善する。
【注意】
胃腸機能低下時や軟便、下痢傾向の方、妊娠中の方、小児、高齢者では、冷やす性質の梨は生のままたくさん食べないようにしましょう。
はちみつ
【性味/帰経】
平、甘/肺、脾、大腸
【働き】
補中:胃腸を元気にする。
潤燥:保湿作用で乾燥を防ぐ。
止痛:痛み(主に胃腸)を止める
解毒:毒を消す
【注意】
胃腸機能低下時や軟便、下痢傾向は控えてください。
Honey / Siona Karen
氷砂糖
【性味/帰経】
平性~涼性/脾肺
【働き】
補肺潤燥:鼻、気管支、皮膚などに潤いを与える
化痰止咳:咳を止めて痰を無くす
降濁解毒:解毒する

Demerara sugar crystals / Ervins Strauhmanis
薬膳とはちょっと離れてしまいますが、洋ナシをオーブンで焼いたものもおいしいですよ。
【洋梨とはちみつ洋ナシ・洋風バージョン】
用意するもの
洋ナシ:4つ、ブランデー:60ml、はちみつ:大匙3杯、水:大匙3杯、無塩バター:大匙2杯 賽の目切り、シナモン:1本、クローブ:4つ。
①洋ナシは縦に半分に切って芯をとる。
②オーブンを400℃に熱しておく。
③オーブン皿に切った面を下にしておく。
④オーブン皿に、ブランデー、無塩バター、シナモンスティックとクローブを加える
⑤400℃のオーブンで5-10分焼く。

Baked Pears with Honeyed cinnamon and brandy / CGehlen
去年紹介したら沢山の方から作った報告を頂きました。温かい梨というのは、なんとも不思議な味と触感になりますが、これが意外と美味しいんです。ぜひお試しください。
2015/09/15