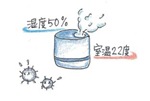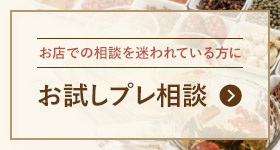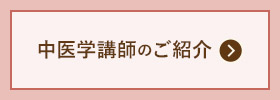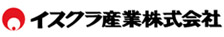ようやく厳しい寒さを乗り越えて、気持ちのよい季節になってきましたね♪
ですが、油断は禁物!この時期訳もなくイライラしてしまう、胸がつかえる、目が赤くなる、生理前の胸張り、お腹の張りがひどくなる方はいませんか?
そのような症状を中医学では“ 肝”の機能の失調からくるものと考えます。
“ 肝”は肝臓だけではなく、情緒、ストレス、自律神経などと深く関わる機能としての意味があり、春になるとその機能にトラブルを起こしやすいのです。そして情緒不安定になったり、肝と関わりの深い目のトラブルや、肝の経絡の走行している部位である胸や下腹部の気の欝滞による張りなどの症状となって現れます。
そのようなトラブル予防に、この季節は気の巡りを良くする食べ物を積極的に摂るようにしましょう!
例えば柑橘系の果物はその香りにも理気作用(気の巡りを良くする作用)が含まれ、香り、味の相乗効果が期待できます。
今回の薬膳はその柑橘系の生薬である仏手、陳皮
(今回の漢方百科この陳皮のご紹介をしています)や、レモンの皮、シークワーサーとみかん果汁をケーキに加えたものです。レシピは近頃流行のホットケーキミックス(HMと書くようです)のレシピ本を参考にさせていただきました。HMベースなので作るのも簡単、スティック状なので持ち運びも食べるのも便利♪なのでこれからの季節、屋外でのピクニックのデザートなどにも如何でしょうか?
~材料~
【 20 ㎝ ×25 ㎝のパット一台分 】
HM:150g
バター:120g
きび砂糖:70g
卵:3 個
レモンの皮のすり下ろし:一個分
粉糖:100g
シークワーサーとみかん果汁:大さじ2
養生茶(仏手・橘香茶):合わせて4g
~作り方~
1.バターを室温に戻して柔らかくし、砂糖を加えてホイッパーで
なめらかになるまですり混ぜる。
2.卵を溶いて、半量を少しずつ加えてその都度よく混ぜる。
3. HMを半量加えて混ぜ合わせる
4.卵の残り半量を少しずつ加え、HMの残り半量、レモンの皮、
養生茶を加えて混ぜ合わせる
5.パットにオーブンシートを敷いて生地を流し入れ、平らになら
し、2,3 回下に落とし、空気を抜く。
6.170℃のオーブンで20 ~ 30 分焼いてあら熱を取っておく。
7. 粉糖とシークワーサーとみかん果汁を混ぜてアイシングを作る。
8.あら熱が取れた生地にアイシングをかけ、アイシングが固まっ
~食材分析メモ( 性 味/帰 経/効 能 )~
仏手柑:辛苦酸・温/肝脾肺胃/舒肝和胃・行気止痛
陳 皮:辛苦・温/脾肺/理気健脾/燥湿化痰
レモン(皮):理気
シークワーサー:甘酸・涼/肝腎/理気・健胃・生津
小麦粉:甘・涼/心脾腎/養心・安神・清熱・止渇・補腎
バター:甘・微寒/肝脾肺腎/大・小腸/補五臓・補気・補血・潤燥・止渇
砂 糖:甘・涼/脾/潤燥・止渇・補中・補気
卵 :甘・平/肺脾胃心肝腎/滋陰・潤燥・補血・安胎







 パンダ来日の出来事をきっかけに、私は中国の人々に日々“ 感謝”しなければならないことを強く感じています。そして上野にはるばるやってきた2頭に、ぜひ一度会いに行きたいです。
パンダ来日の出来事をきっかけに、私は中国の人々に日々“ 感謝”しなければならないことを強く感じています。そして上野にはるばるやってきた2頭に、ぜひ一度会いに行きたいです。