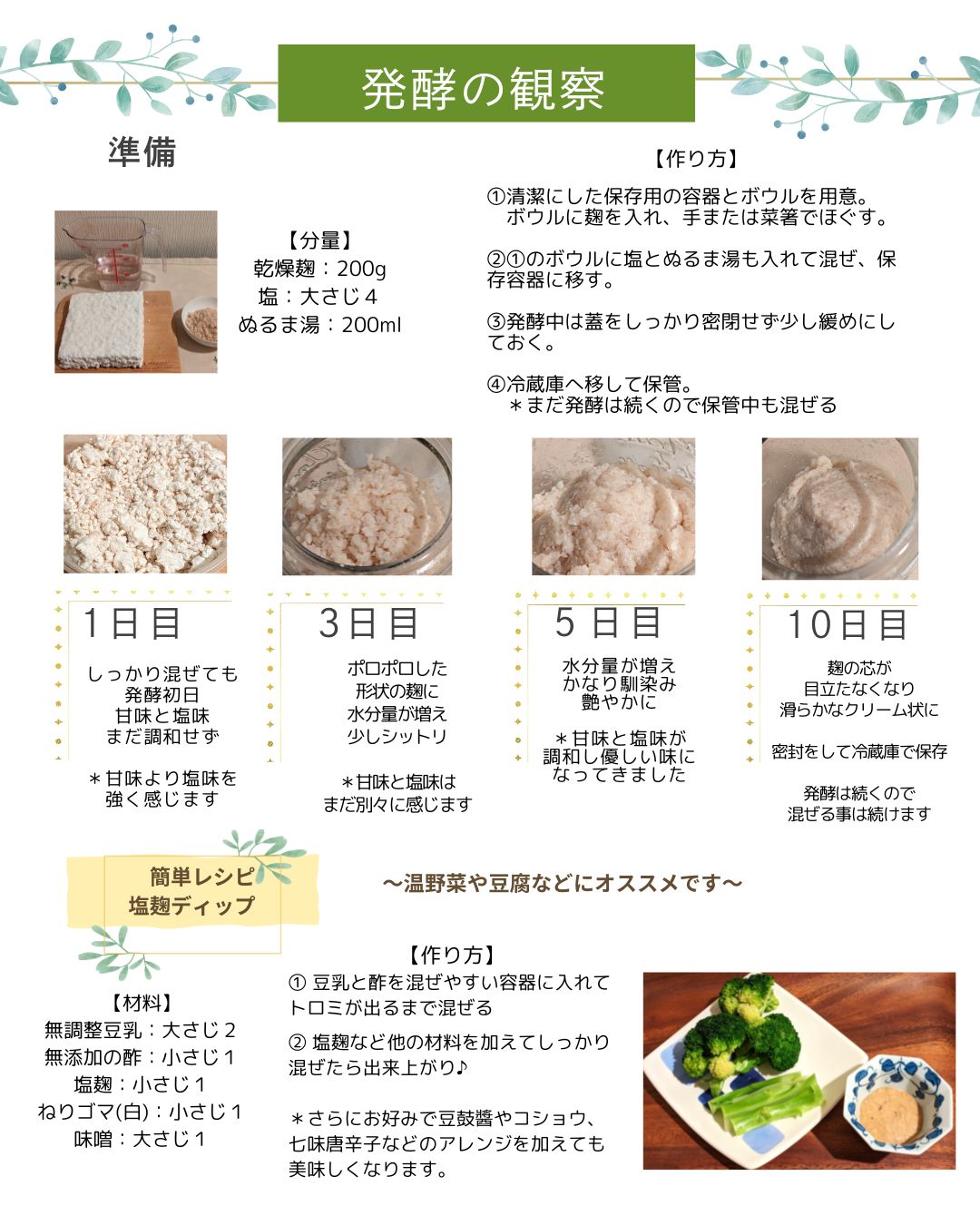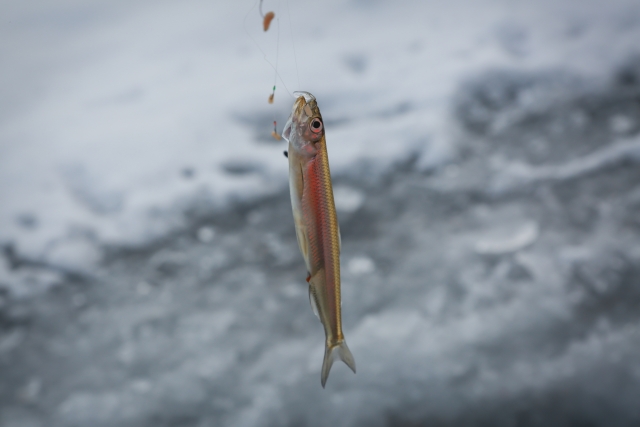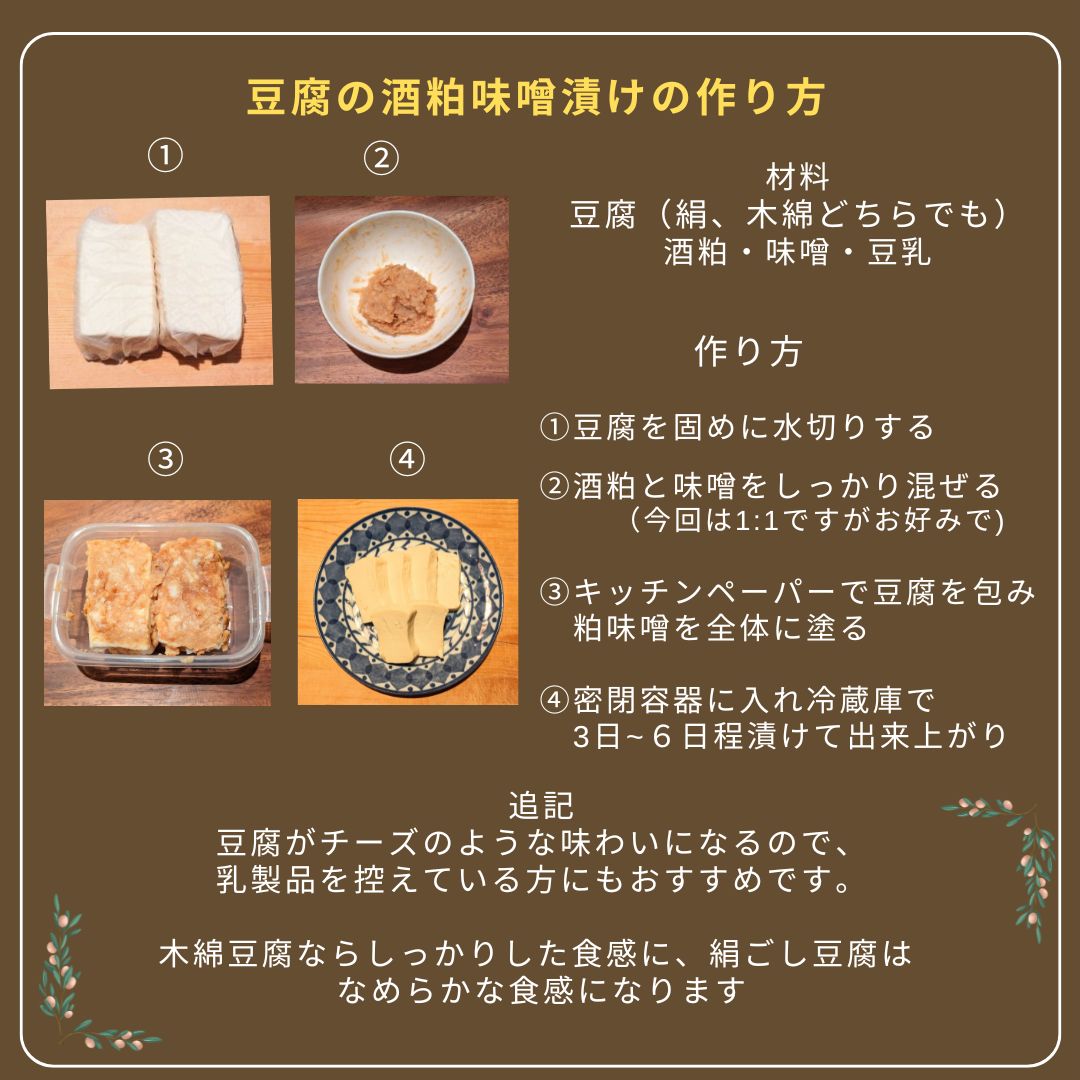こんにちは、金村です。
先日、自宅のレモンを収穫しました。3年前にいただいたレモンの木には、レモンと言って良いのか悩む程丸くて大きな実がなります。
柑橘類には、「隔年結果」という一年おきに豊作と不作を繰り返す現象があるそうです。
初めて収穫した昨年は、色味が微妙なものが2個のみでしたが、今年はしっかりとした大きな実が4個でき、一番大きいものでは直径15㎝もありました。(品種はいまだに不明です。)
自宅で収穫したレモンです⇓(通常サイズのレモン3個分に相当します)
通年手に入るレモンですが、国産レモンの旬は秋~冬頃です。レモンは、家庭でも育てやすく、私の実家では一つの木(プランターで育てています)から、今年は通常サイズのレモンが30個も収穫できました。
スーパーで無農薬のレモンを買うと結構な値段がするので、自宅で採れたレモンを料理に使う時は、とても得したようで嬉しくなります。
たくさん採れた場合に困るのは保存方法ですが、レモンは一か月程冷凍保存が可能です。丸ごと冷凍もできますし、輪切りやくし切りにして冷凍しても重宝します。
レモンの木の害虫
育てやすい植物といっても、やはり害虫はいます。
レモンの木をいただいてからしばらくすると、自宅のテラスでアゲハ蝶を見かけるようになりました。
最初の頃は、美しいアゲハ蝶の訪問を喜んでいましたが、しばらくしてレモンの葉に異変が起こり始めました。
虫食いの葉が多発し、一部茎のみになっている箇所が!
害虫の正体は、レモンに植え付けられた卵から孵化したアゲハの幼虫でした。
葉っぱが食い尽くされないよう、1匹だけを残し、あとは申し訳ないと思いながらも...
それ以降も薬剤などは使わず、水やりの際、毎回新たな幼虫が増えていないか確認し対処しました。
薬膳的効能
レモンは、潤いを生み出し、食欲を高め、消化を助けてくれます。
皮の部分は気の巡りを良くし、胃の機能を高めてくれます。
※胃酸過多の方は摂りすぎないようご注意ください。
レモンとショウガのはちみつ漬け
今回はレモンの爽やかさを生かしつつ、冬に飲みたいレモンとショウガのはちみつ漬けをご紹介します。
ショウガは温性が強く、胃腸を温めてくれる冬に最適の食材です。
漢方薬にも生姜や乾姜(蒸して乾燥したもの)としてよく使用されています。
ショウガが苦手な方は、ショウガを入れずレモンのはちみつ漬けにしても構いませんが、レモンの性質は涼性のため、冷え性の方やこれからの時期はホットドリンクにするのがおすすめです。
中医学では、酸味のものと甘味のものを合わせて陰(潤い)を生み出すことを「酸甘化陰」といい、レモンの酸味とハチミツの甘味は相性◎です。
<材料>
レモン 通常サイズ3個 輪切り
ショウガ 1個 スライス
はちみつ 200-300g

<作り方>
・レモン→ショウガ→はちみつの順に繰り返し層を重ねます。
・はちみつの量は目安で記載しましたが、レモンとショウガがはちみつに浸っていれ ば問題ありません。
・ショウガの量や皮を剥くか等もお好みで加減ください。
・冷蔵庫で2晩置いたら完成です。

前回記事:薬膳ガーデニングのススメ~ミニトマト~