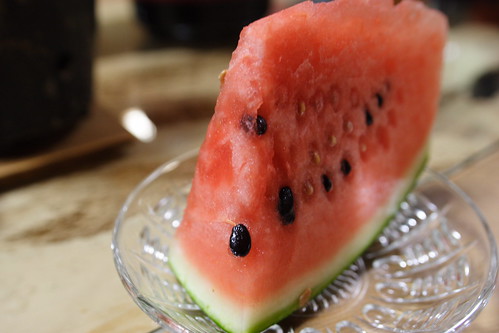毎日毎日暑いですね。梅雨はいずこへ??っと思っていたら、明日からようやく関東地方も雨が続くようできっと雨を待っていた紫陽花も喜ぶでしょう。まぁそうなったらそうなったで、うっとおしいんですがね。私の地元、北海道では連日35度越えと、日本で一番暑い場所となっております。いやはや、最近の天気はまったくわけがわかりません。
この時期スーパーの野菜コーナーでは、ソラマメが大量に並び、スイカ、ナス、胡瓜など夏の野菜たちで飾られています。その中でもうず高く積まれ、毎年気になってはいるけど、まだ手が出せていないのが「梅」です。
三毒を断つ「梅」の力
梅の原産地は中国の四川省から湖北省あたりとされ、日本には奈良時代に持ち込まれたと考えられています。日本にも、もともと自生していた梅もあったようで、古事記や日本書紀、万葉集などにも登場しており、古くから栽培されていたことがわかります。
古くから梅は健康維持に欠かせない食材でした。戦国時代には、携帯食料として、また、泥水を飲んだ時の感染症の予防として、梅干しの果肉を粒状にしたものがつくられ重宝されていたようです。
「梅は三毒を断つ」と言われ(三毒とは、食べ物、血、水の毒の事)、解毒効果、血行促進効果、生水の食あたりを消してくれる効果があります。日の丸弁当しかり、梅のおにぎりしかり、ただおいしくて食欲増進になるだけでなく、殺菌作用も兼ねて、古くから私たちの体を守ってきた食品です。
疲労回復、殺菌、解毒、梅の栄養
梅の特徴は、なんと言ってもあの独特な酸味。梅と聞くだけで唾液がでてきますよね。あの酸味の主成分はクエン酸を含む有機酸です。特に一番多いクエン酸は、エネルギー代謝に関わり、疲労回復に役立つ他、殺菌作用も強いので、防腐効果や食中毒の予防にも効果があります。クエン酸の他にも、リンゴ酸、コハク酸、酒石酸、などの有機酸を多く含んでおり、これらにも疲労回復や殺菌などの力があります。また整腸効果もあり、新陳代謝を上げてお肌もきれいにしてくれます。
栄養面では、カルシウム、カリウム、リン、鉄、亜鉛などのミネラルも豊富に含んでいます。たとえばリンゴに比べて、梅に含まれるカルシウムは4倍、鉄は6倍も含まれてます。カリウムも身体に溜まった余分な水分を体の外に出してくれる働きもあります。
また、ビタミンA、C、B1、B2も豊富なので、こちらも、疲労回復にはとても有効です。また、これらビタミン類は、紫外線の強い夏場にお肌を守るためにとても重要な役割を担っており、是非取り入れておきたい栄養素です。
そして梅は、代表的なアルカリ性食品です。近年、私たちが口にする食品は、野菜や海藻を中心とした和食から、インスタント食品や加工食品、パンや肉など洋食中心の食生活へと変わってきています。これらは「酸性食品」と呼ばれており、私たちの体を流れる体液を酸性化してしまいます。酸性化された体液は、排泄障害や、内臓機能低下などを起こす原因となることが近年の研究でわかっており、人間の体が健康であるためには、体液が弱アルカリ性に保たれている必要があるとされています。梅干しは、酸性に傾いた体液を中和し、弱アルカリ性に傾けてくれる助けをしてくれます。
中医学から見た梅の力
梅の東洋医学的効能は、唾液を分泌し、口の渇きを止め、肺の機能を回復させて空咳を鎮め、腸の機能を回復させて下痢を止め、虫下しをしてくれます。寒熱は平で、冷え症でもほてりの方も食べられます。酸味には収斂作用といって、出過ぎる汗を抑えてくれる力がある反面、寒気を伴うカゼを引いたときなどは、汗を抑えてしまい、治りにくくしてしまいますので、汗をかきにくい方で寒気を伴うカゼを引いた時は、梅干しよりも、ショウガやネギを食べるようにしましょう。
また、梅を焼いて炭にして、すり潰して患部に張りつけることで、傷口の回復が良くなるほか、様々な止血作用があると古典には書かれています。
梅は、胃腸への刺激がなかなか強い食材でもありますので、夏場、冷たいものを摂りすぎた時や、冷え症の方、小児では控えめに食べるようにしましょう。また、梅の殺菌作用は、生のままより、梅酒や梅干しにするほうが優れています。しかし、梅干しは塩分が多いので高血圧の方は1日2個までにしておいてくださいね。
夏場の食欲低下時、私がおすすめしたいのは、お粥と梅干しです。お米を炊いて多めの水分で薄く延ばしたお粥に梅干しを加えると、それだけで夏場の潤い補給にはもってこいの食事が出来上がります。お米の糖質が体のエネルギーになり、梅干しの塩分が汗で失うミネラルを補給し、酸味が潤いを生んでくれます。また、クエン酸も豊富で、夏バテの予防や、疲労回復にも効果的です。是非、夏バテ時には、冷たい素麺より、温かいお粥と梅干しを思い出してくださいね。