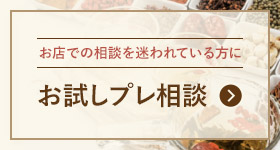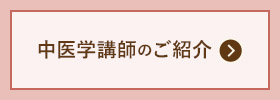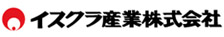のどの違和感や詰まった感じはありませんか?この症状の原因となるものは色々とありますが、今回は”梅核気”に焦点を当てみたいと思います。 “梅核気”とはどういった症状? ・のどの辺りになにかが詰まっているような異物感 ・口から出そうとしても出てこないし、飲み込もうとしても無くならない ・締め付けられるような梗塞感など違和感 ・ヒリヒリすることもある ちょうど梅の種くらいの大きさ …
続きを読む中医学を学ぼう!
- 美容から症状別まで役に立つ中医学についてご紹介。
のどの違和感を感じたら「梅核気(ばいかくき)」かも!
陰と陽
中医学では全ての物事を陰陽に分けてとらえるため、陰と陽のそれぞれには役割があり、そのどちらが欠けても人体にとってバランスを失った状態になってしまうと考えるのです。
では、陰陽の分類について例を挙げてみましょう。
八綱弁証
八綱弁証とは‥ 中医学では漢方の理論に沿って患者さんの状態を判定することを、「弁証する」と言います。普通、病院では 「診断し、病名をつけ」ますよね。しかし中医学では「診断し、証をたてる」のです。この証をもとにお薬が選ばれますから、 この診断が非常に重要となります。そして、この証のたて方として八綱弁証…
続きを読む「肝」の生理
まずは臓腑弁証について 前回までは「気」「血」「津液(水)」をご説明してきました。これら 3 つが私達の体を巡り巡って体の機能を正常に維持しています。 一般的にはなかなかつかみにくい概念かもしれませんが、お分かりになりましたでしょうか。 それに加えて以前ご説明した「八綱弁証」を組み合わせていくことで…
続きを読む「心」の生理
心の働きを知ろう 私たちは普段「心(しん)」と聞けばすぐに「心臓」を思い浮かべます。「心臓」 が止まった時こそ生命が終わりを告げる時であり、他の臓器と比べ、より重要な器官として認識される傾向があるように思います。 中医学でも「神の居」と言われ、生命活動の中心を担うとされます。とはいえあくまで五臓の一…
続きを読む「肺」の生理
一般的な「肺」の機能については非常に良く知られています。そう、呼吸機能ですね。中医学でいう「肺」も同じ意味合いがありますが、合わせて免疫機能のような働きがあったり、皮膚の状態と関係していたりと、世間一般でいわれる「肺」よりもさらに広い役割を担うとされます。 「呼吸」は酸素を取り入れて、二酸化炭素を出…
続きを読む「脾」の生理
脾の働きを知ろう みなさんは「脾臓」をご存知ですか?何となく聞いたことはあっても、あまりなじみはありませんよね。 西洋医学的には「脾臓」は造血機能や免疫機能を担う臓器とされており、胃の裏側に位置します。 ただし人体にとってそれほど大きな役割は無いとされ、仮に取り除いてしまっても生存には影響がないとも…
続きを読む「肝」の病理
肝からくる症状を見分けよう 前回までで五臓の生理のお話は終わりました。この捉え方をもとに、 起こっている症状がどの臓腑からくるものなのかを見分け、さらにこれまでに学んだ寒熱(かんねつ)、虚実(きょじつ)、陰陽(いんよう)、気血津液(きけつしんえき)の状態を明らかにする方法を「臓腑弁証(ぞうふべんしょ…
続きを読む「心」の病理
心の乱れによって引き起こされる症状とは 心には 血脈を主る 神志を主る などの生理機能があるとされます。よってこの働きが損なわれると血流に関係する障害や精神面の症状が表れやすくなります。具体的には ・ 動悸(狭心症) ・ 血圧 の異常 ・ イライラ又は鬱 ・ 睡眠障害 などが挙げられます。 心は…
続きを読む「脾」の病理
脾胃のトラブル 「脾の生理」でご説明しましたように、脾には ・ 運化機能 ・ 統血作用 ・ 昇清機能 といった生理機能があります。脾に何らかのトラブルが起こると、これらの作用に影響し、 ・ 消化機能低下 ・ 不正出血 ・ 内臓下垂 などの症状がみられるようになります。 脾は「土」の行に属し、体の資本…
続きを読む