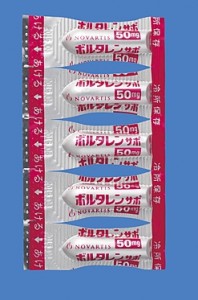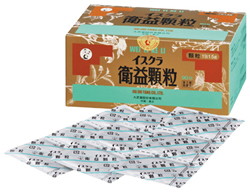こんにちは。店長の櫻井です。桜、きれいですよね。当店の近くのミッドタウンの横のさくら通りも満開で今が見ごろです。木に花だけってなんかやっぱりきれいですよね。桜は染めに使われたり、生薬としても使われたり、桜と日本文化とは長く、そして深いつながりがあります。今日はそんな桜にまつわるお話を少し。

国花ではないが・・・
日本人は本当に桜が大好きですね。桜は昔から和を表すモチーフとして使われ、今でも日本を代表する花としてそのデザインがたくさんの場所で使われているのを目にします。100円玉の裏や、警察官の徽章にも桜のデザインがあしらわれています。一気に咲いてさっと散る、そのはかなさや潔さなんていうのも、日本人の美学に合うんでしょうね。江戸時代には武士道のたとえとしても使われていたようです。

いくつ知ってる?桜の種類
公益財団法人日本花の会によると、桜は2月から種類によっては5月頃まで咲くものがあるそうです。昔から咲き方や花びらの数や色など様々な品種改良がされ、花の形も、一重、半八重、八重、菊咲などのものが作り出されていて、なんと現在登録されているもので、380種もあるそうです。桜と言えばソメイヨシノや八重桜ぐらいしか知らない私はそれだけでびっくりです。八重桜っていうのは、品種ではなく咲きかたっていうことも今の今まで知りませんでした。

道明寺?長命寺??
桜、勿論お花も大好きですが、甘いもの好きの私はやっぱり「桜餅」が外せません。関西生まれの私にとって桜餅とは、″道明寺″のこと。道明寺とは、大阪の藤井寺市にある道明寺というお寺で作られていた、蒸したもち米を乾かして荒く砕いた保存食の事をさすそうです。これを使って和菓子が桜餅、または道明寺と言われているそうです。もう一つ、関東で桜餅と言えば、小麦粉に上新粉などを混ぜたもので餡をクレープ状に包んだものもあります。こちらは関東風(江戸風)の桜餅で″長命寺″とも呼ばれています。関西では道明寺粉を使ったものが一般的で、長命寺は目にすることはなかったように記憶しています。どちらも、塩漬けにした桜の葉っぱで包むという点は同じですね。

桜餅♪ / hm7hm7
抗酸化作用のある桜の葉
桜の葉で包むのは、桜の葉の防腐効果を狙ったためだと思いますが、塩漬けにされた桜の葉には何とも言えない風味がありますね。でも生の桜の葉の臭いを嗅いでもあの香りはしないんです。あれは、長い間塩漬けにする間に生まれる「クマリン」というなんともかわいい香り成分のせいだそうです。クマリンは乾燥させたり、砕いたり、塩漬けにすることで生まれるそうです。クマリンは抗酸化物質のポリフェノールに分類されている香り成分で、抗菌作用、抗血液凝固などが知られていて、血栓防止薬として利用されています。この抗菌作用のあるクマリンで桜餅は守らているんですね。
塩漬けにされた桜の葉を食べないという人もいますが、もったいないですね。老化を防止してくれる抗酸化物質はいくらとっても足りないぐらいですから。

桜の樹皮の漢方薬「桜皮」とは?
中医学ではあまり使われることは少ないですが、桜の皮は「桜皮(おうひ)」と呼ばれる解毒や咳止めなどに使われる漢方生薬の一つです。湿疹や肌の炎症に対する外用薬としても使われているようです。市販の咳止めにも桜皮抽出エキスが使われています。
サクランボと桜
桜の実は、みなさんご存知サクランボです。厳密には桜の一種の、桜桃(おうとう)と呼ばれる種類のもので、観賞用の桜とサクランボがなる桜は種類が違うので、花がきれいな桜を植えてもサクランボはとれませんし、サクランボの種を植えても、きれいな桜はみられません。
リラックスアロマ効果も
桜の香りには、リラックス効果もあるそうですよ。もし手に入れば桜の花びらを浮かべた桜風呂なんても粋で、素敵すね。桜の花を浮かべた桜茶や、焼酎に八重桜を付けた桜酒なんてもいうのもあるそうですので、是非お試しください。
桜は、美しく咲き誇って、潔く散る。そんな瞬間の美。たまゆらの美とでも言いましょうか。そんな美しさに魅了されます。そして桜は散り方も美しいですね。そんな生き方、できたらいいですね~