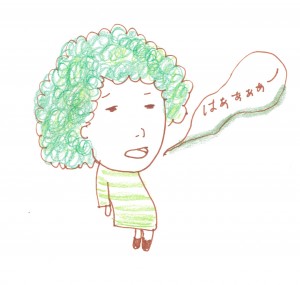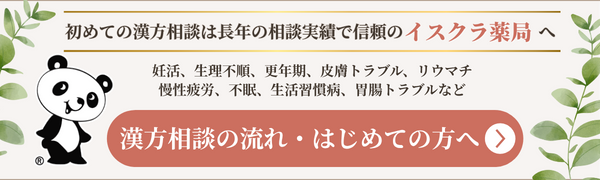こんにちは。櫻井です。梨とハチミツの潤肺薬膳レシピや、簡単リンゴの薬膳レシピが異常な人気を誇ってしまい、なぜか「次はいったいどんなレシピを考案すれば喜んでもらえるんだろうか??」とわけのわからないプレッシャーを感じておりまして、そのことをTwitterで告白すると、心温かい皆様からいろんなアイディアをいただいたので、今日はその一つ「柿」に乗っかってみたいとおもいます。(とりまめ様、ありがとうございます!)

japanese persimmon / 柿 kaki / [puamelia]
「柿が赤くなれば、医者が青くなる」
柿の歴史は古く、弥生時代に中国から渡ってきたとされています。しかし、私たちが今食べている「甘い柿」っと言うのは日本独自に品種改良の末生み出したものだそうで、学名にも「Diopyros kaki」と「Kaki」という文字が入っているなんてご存知でしたでしょうか。
この柿ですが、実は昔から「柿が赤くなれば、医者が青くなる」といわれ、便秘を改善したり、二日酔いにもよいほか、ビタミンCも豊富で(大き目の柿なら一日分のビタミンCを補えます)、その他、止血をする際に働くビタミンK、粘膜やお肌を強くするビタミンA(βカロチン)やB1・B2、抗酸化酵素を活性化させるミネラル(特にカリウム)、食物繊維なども豊富なので、天然のマルチビタミン剤ともいえる食べ物なんだそうです。

break time / japanese persimmon / [puamelia]
体の中から潤し、喉を癒す
中医学から見ると、柿は余分な熱を取る性質と、体内の潤いを増やす性質をもっていますので、イガイガ喉や咳などのトラブル、口の渇き、口内炎、コロコロとした便秘など、乾燥の秋にはピッタリの食材です。また酒の毒をとる力もあるため、二日酔いや飲みすぎにも効果的ですし、「あれ?喉おかしいな?」、なんて時には柿はピッタリです。発熱時にもおすすめですよ。
中医学から見た柿
柿
【性味/帰経】
寒性、甘味、渋味/心、肺、大腸
【働き】
・清熱潤肺:肺を潤し咳を収め、便秘を改善する。咳に交じる血を止める。
・生津止渇:胃に溜まった熱を鎮め、異常な食欲を抑える。口の渇きや口内炎にも。
・解酒熱毒:二日酔いや酒の飲みすぎに。酒毒を取る。
【禁忌】
・カキはカニと合わせるとお腹を壊して下痢をします
・空腹時は食べ過ぎに注意しましょう。
・冷やす性質があるので、胃腸が弱っているかた、小児、高齢者、下痢気味の方、妊娠中は食べ過ぎに注意です。

I heart persimmon / watashiwani
温かくて甘~い、焼き柿レシピ
柿はもちろんそのまま食べてもおいしいですが、冷凍すると甘味が増すそうです。
ここでは珍しい食べ方、「焼き柿」をご紹介します。
【材料】
柿・・・食べるだけ
ハチミツ・・・適量
お好みでバニラアイス
【レシピ オーブン編】
1. 柿を冷凍します。そうすることで甘味が増すそうです。
2. 200℃にしたオーブンで30分ほど焼きます。皮が割れてきたら食べごろです。
3. 皮は剥いて、適当に4等分にでもして食べてください。
*お好みではちみつやバニラアイス、または両方をかけてもおいしいです。
【レシピ トースター編】
1. 指で押してちょっとへこむぐらいの半熟柿のへたから1センチ~2センチぐらいを切り取ります。(梨のレシピみたいな感じ)
2. 皮と実の間と実に、軽く切れ込みを入れます。そうすると火が通りやすく、食べやすくなります。
3. 10分ほど焼いて、皮がパリッとして、焼き色がうっすらついたら完成です。*皮は食べません。
4. お好みでハチミツやバニラアイス、水切りヨーグルト等をかけてお召し上がりください。
【もっと 簡単な 焼き柿バリエーション】
*皮をむいて薄切りにしてしまえば簡単に焼けます。
*皮をむいてスライスした柿を、バターを載せたパンに載せて焼いてももおいしいです。
*皮をむいてスライスした柿を深めの皿に入れて、白ワインをさっとかけてラップをしてレンジで1~2分!とろとろデザートになります。
*皮をむいて角切りにして、ハチミツ(砂糖でも可)、レモン汁をふってラップをしてレンジで3分。その後10分蒸らして、シナモンを振ればコンポートの出来上がり。

Premium / kimubert
秋に旬を迎える梨やリンゴ、柿などはどれも潤いを生んで、喉や呼吸器、肌や粘膜を護ってくれる食べ物達です。季節はさらに乾燥する冬に向かうので、旬を迎えたくさん食べられるこの季節にたっぷり潤いを蓄えておきましょう。
柿は寒性のため、冷やす性質があります。これから寒くなってくるので、そのまま食べるときも、冷やし過ぎに注意しできれば常温で食べるようにしましょう。冷え症の方には、上記の焼き柿がおすすめです。焼くことで寒性が柔らかくなり、胃腸への負担がかるくなります。ただ、寒性であることは変わらないので、食べ過ぎには十分注意してくださいね。温かくした柿は、お子様の発熱時の水分補給と熱、咳対策にもおすすめです。冷たいものを食べるより断然いいです。ぜひお試しください^^