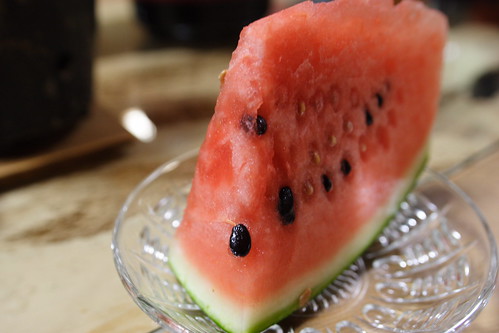こんにちは。六本木店長櫻井です。気象庁から3か月天気予報が出されました。エルニーニョ現象の影響から梅雨明けが遅くなり、冷夏が予想されていましたが、その心配はどうやら無くなったみたいで、今年も暑い夏がやってくるようです。特に西日本は猛暑の予報ですので、熱中症対策はしっかりとしておきたいですね。(暑い日の食と養生方はこちら)
暑くなってくると、やっぱり冷たいビールがおいしいですよね。中医学的には、脾胃は冷たいものや水分を嫌うので、キンキンに冷えたビールは天敵なのですが、夏の暑い日に外で飲むビールは何とも格別の喜びを感じられます。でも、やっぱり体調も気になりますよね。そんなときには是非おつまみを活用して養生してください。
今日はそんな定番ビールのおつまみ、「枝豆」のお話をしたいとおもいますが、実は枝豆はビールのお供に最適だったなんてみなさんご存知でした??
実は「大豆」
枝豆、っというと、鞘に入ったあの緑色の豆ですが、枝豆は実は大豆だということを知らない人も多いのではないでしょうか。枝豆を成熟させると大豆になり、未成熟の段階に収穫したものが枝豆なんだそうです。成熟させて大豆にするか、途中で収穫して枝豆にするか、どちらにするか適した種類というのはあるそうです。

Edamame / Carrie Frizzlechicken
中国からやってきた「枝付きの豆」
枝豆のルーツは中国の北部地方で、日本には約2千年ほど前に持ち込まれたとされています。枝豆として食べられたいたことがわかっているのは、平安の時代ごろから。江戸時代になると、豆腐売りならぬ、「枝豆売り」の姿も見られたそうで、今も昔も夏の訪れを知らせてくれる定番おつまみであることに変わりなかったようです。当時は、枝についたまま売らており、歩きながらそのままちぎって食べていたようで、そこから「枝付き豆」と呼ばれ、略して「枝豆」と呼ばれるようになったそうです。その昔は田んぼの畔などにも植えられていたようで、「畔豆」と呼ばれていた時期もあったそうです。
むくみ、便秘、美肌によい!そして悪酔いや二日酔い予防にも良い!
枝豆はなんといっても畑の肉ともいわれる大豆ですから、良質なタンパク質が豊富です。さらに糖質や脂質、そしてカルシウムや鉄分、疲労回復やお肌をきれいにしてくれるビタミンB1、B2、そして大豆には含まれていないビタミンCも豊富なのも特筆すべき特徴でしょう。ビタミンCとタンパク質はコラーゲンの元を作ってくれるので、他のビタミンとも相まって、枝豆単体で美肌効果も期待できます。葉酸も豊富なので、貧血の気味のかたや妊婦のかたも摂っておきたい食材ですね。
枝豆の中に含まれるたんぱく質の中には、メチオニンというアルコールを分解してくれる成分が入っていますし、前出のビタミンB1にもアルコールの代謝を促進させる力があります。さらに肝臓の働きを固めてくれるコリンも豊富で、二日酔いや悪酔いの予防も最適です。イソフラボンという大豆に含まれているポリフェノールの一種や、そのイソフラボンの一種のダイゼンには、女性ホルモン様作用があるので、更年期特有ののぼせの緩和や、骨粗しょう症の予防や改善、そして、がんの抑制作用、免疫機能を高める作用がなどが確認されており、今後の研究に期待です。
さらにサポニンとレシチンも含まれており、コレステロールを下げて中性脂肪を減らしてくれるので、他のおつまみが脂っこくても対処してくれますし、高脂血症予防効果も期待できます。枝豆にはビタミンCや食物繊維も豊富なので、便秘の解消にも一役買ってくれますし、カリウムもたっぷり含まれているので、体に溜まった余分な水分を外に出してくれる働きもあり、むくみも改善してくれます。さらにビタミンB1が疲労回復にも働いてくれ、まさに夏にぴったりの食材なんです。
中医学で見る枝豆
枝豆は甘味で平性。寒熱の偏りがなく、どんな方でも食べられます。胃腸の働きを助けて、腸を整え、血やエネルギーを与えてくれて、必要なだけ胃腸を潤し、余分な水分は排出してくれて、膿を排除して毒を消してくれます。中医学的にみても、夏バテや食あたり、下痢やむくみによいなど、とにかく夏にぴったりの食材です。
古典には、「食べ過ぎると気が詰まり、痰を生じて体が重くなる」とあるそうです。確かに豆は消化しにくいので、食べ過ぎると胃腸の負担になってしまいます。美味しいから身体に良いからといって食べ過ぎないように注意しましょう。

Soban Restaurant Whitecourt Alberta Edamame / elsie.hui
まとめると、枝豆は、、、
胃腸を元気にして身体に気力を補ってくれ、
利水作用で身体の余分な水分を出してくれて、
アルコールの分解を助けてくれる!!
あつらえたかのように夏に、そしてビールにぴったりの食材ですね。
枝豆の選びかた・保存法
美味しい枝豆を選ぶには、さやの色が濃く鮮やかで、うぶ毛がまんべんなくついていて、枝が付いているものなら、さやがたくさんついていて密集していて、葉や茎の色が鮮やかなものを選びましょう。枝豆は鮮度が落ちやすく、時間がたつごとに甘味が減っていきます。できれば買ってきたその日のうちに食べてしまいましょう。保存する場合は、硬めにゆでて、さやに入ったまま冷凍してください。食べるときは自然解凍したのち、さっと熱湯に通して食べてくださいね。
今や枝豆は世界中で食べられているおつまみです。昨年Googleで検索された和食キーワードで1位の「寿司」に次いで多かったのが、「えだまめ」だったそうです。胃腸の働きを促進して、利尿作用もある枝豆。ビールのお供にはとても合理的な組み合わせですね。でもやっぱり冷たいものは飲みすぎないようにしてくださいね。