こんにちは、一週間に2日六本木店に勤務しております太田です。
今日は、桜が散ってしまっていないかドキドキしながら六本木店に出勤いたしました。昨日雨が降りましたが、今日は快晴、お花見日和で六本木ミッドタウンの側の桜並木も多くの方で賑わっておりました。
そんな中、カメラを手に持ち、カメラ小僧になりきり写真を撮ってまいりました。今の六本木ミッドタウン側の桜の開花状況はこんな感じです♪
私はソメイヨシノよりも、山桜のような桜が好きですが、みなさんはいかがですか?
イスクラ薬局(東京)
中医学 の記事一覧
こんにちは、一週間に2日六本木店に勤務しております太田です。
今日は、桜が散ってしまっていないかドキドキしながら六本木店に出勤いたしました。昨日雨が降りましたが、今日は快晴、お花見日和で六本木ミッドタウンの側の桜並木も多くの方で賑わっておりました。
そんな中、カメラを手に持ち、カメラ小僧になりきり写真を撮ってまいりました。今の六本木ミッドタウン側の桜の開花状況はこんな感じです♪
私はソメイヨシノよりも、山桜のような桜が好きですが、みなさんはいかがですか?
2015/04/02
今週の東京は暖かい日が多く、ずーっとこの天気が続けばいいのに…と思っている太田です。
暖かいのは良いのですがお天気が安定せず、普段からめまいや頭痛にお悩みの方は、体調が振り回された一週間だったのではないでしょうか。
このように、春は体調や気持ちが安定しない時期でもありますよね。中医学での春の養生は自律神経を整えることが重要になると考えます。
たとえば最近、こんな症状思い当たりませんか?
イライラ・ためいき・不眠…

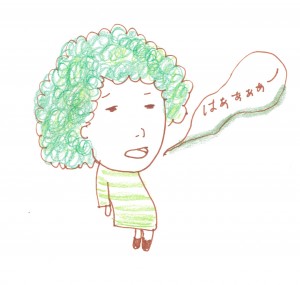

私は最近、ためいきがとまらないのですが、なるべく香りの良いお茶(ミントや菊のお花を混ぜたものやジャスミンなど)を飲んだり、いつもより早く就寝すること、携帯電話をベッドに持ち込まない、などリラックスできるように気を付けてみると、やはり体が楽だなあと感じます。そしてもちろん、お気に入りの漢方薬を飲んだりしています。
まさに「春の天敵はストレス」です。私の場合は天気の変動が大きいことがストレスの1つでしょう。
春になるといつも調子が悪いなあ、という方、リラックスできる環境を作ると共にぜひ一度、漢方薬をお試しになってみませんか?
そして最後に。
桜の開花予想が発表され、そろそろ桜が咲く時期だなあと嬉しくなりますね。そんな訳で、お花見セットをご用意致しました!まだ店頭には出しておりませんが、準備はしておりますので、中身はなんだろう~、と気になる方、是非スタッフまでお声がけください。
2015/03/20
こんにちは。太田です。
今日は寒い一日でしたが、花粉は飛んでいるようですね~。
暦では今日から「啓蟄」(けいちつ)で、冬籠りの虫が土から這い出てくる頃と言われています。
私は小学生の頃サワガニを飼っていて、水槽の中に落ち葉を入れて冬眠させてたカニを起こす日が「啓蟄」でした。
落ち葉のふくよかな香りを嗅ぎながらカサコソとカニを探し、カニが生きていた時はホッと胸をなでおろしたものでした。
そんな思い出もあり、「啓蟄」と聞けば落ち葉の香りを思い浮かべます。
「血流」とは良く使われる言葉ですが、実際にご自身の血流がどうなのか…。定期的に病院で採血されている方以外は、あまり測る機会はないかもしれませんね。
中医学では、「不通(ふつう)なれば則ち痛む」という考え方があります。つまり血の巡りが滞っていることが、痛みに繋がるという考え方です。
この様な症状が思い当たり、「慣れてしまってあまり気になってなかったなあ」という方、当店で血流を測ってみませんか?頂戴するお時間は5分程度、無料で測定できます。
「コロトコフ音」という動脈をカフで締め付けた時に発生する音を記録する機械で測定いたします。
ご予約不要ですので、ご興味のある方は是非お気軽にいらしてください♪
2015/03/06
本日2月19日は旧正月。中国で言うところの「春節」(しゅんせつ)です。今日は日差しも戻り、うれしいですね。
「春節」については、過去の六本木店のブログもどうぞ。
この春節を祝う大きなお祭りは、日本ではどこで楽しめるのだろう~♪と調べてみたところ、日本全国5か所で開催。
名古屋(1月30~31日、2月1日)・新潟(2月14~15日):終了
神戸(2月19~22日)・横浜((2月19日~3月5日)・長崎(2月19日~3月5日):開催中
ここ数日寒い日が続いており、気持ちまでふさぎ込んでしまいそうになりますが、お祭り♪美味しいものが食べられる♪と聞けば、そんなくさくさした気分も吹き飛びますね!とはいえ、人混みが苦手な私、太田はお祭りにも行かず、くさくさした気分のまま春を待つのかもしれません。春よ来い。という訳でここで一句、万葉集より。
正月(むつき)立ち 春の来たらば かくしこそ 梅を招(お)きつつ 楽しき終(を)へめ
-大弐紀卿 万葉集―
意味; 睦月(1月)となり春がやって来たなら このように梅を招き迎えて 楽しい日を過ごしましょう
この歌は、天平2年(730年)正月13日、大宰帥大伴旅人邸で「梅花の宴」が催され、九州管内諸国の官人32名が中国渡来の梅を題材に歌を詠み春の一日を楽しんだ際、宴の開始にあたり、主賓の大弐紀卿(だいにきのきゃう)の挨拶として詠まれた、とされているようです。天平2年正月13日は、現在のグレゴリオ暦に当てはめると730年2月8日。
今から1285年前(! )、当時は珍しかったであろう梅の花を、歌を詠みながら楽しんでいたのだなあと想像すると、なんだか面白いですね。今週末のお天気は今一つのようですが、梅の花を探しにちょいとお散歩へ出かけるのもいいかもしれませんね。
さて、睦月は旧暦で一月を指しますが、この言葉の由来は諸説あり、一番有力なのが親類知人と会い、仲睦まじくするため「睦月」となった説の様です。
次に話は変わり、中医学の根本となっている「陰陽五行」(いんようごぎょう)に当てはめて「一月」を見てみましょう。
「陰陽五行」は中国の古い哲学が根本となっているのですが、実は現代の私たちの生活にも深く根ざしているものなのです。そのひとつの例が「子丑寅卯…」と数える十二支です。
十二支は、実は年だけでなく、月や日・時刻・方位にも割り振られており、旧暦の1月は「寅」。つまり今日から「寅」月になります。
この「寅」は、もともと「螾」(いん:「動く」の意味)と書き、春が来て草木が生ずる状態を表していましたが、後に動物の「寅」が当てはめられたそうです。
そして「寅月」の事を指して、「禮記」(らいき・儒学者がまとめた礼に関する書物)に「是の月や、天気下降し、地気上騰し、天地和同し、草木萌動(ぼうどう)す」と記載されているようです。天の陽気が下がり、地の陰気が上がり、陰陽がうまく交わって、草木が芽を出し始める、という意味になります。
(参照図書:「陰陽五行と日本の民俗」吉野祐子著 )
陰陽が交わり新しい生命が萌える、このように儒学者たちは捉えていた様ですね。
更に、本日は旧正月であると同時に、二十四節気では立春から「雨水」(うすい)に変わります。この「雨水」は、まだ寒さが残っているけれども、雪より雨が降り、積もった雪も溶けるようになる時期を指します。
二十四節気とは、1844年(171年前)に最新の天文学の知識による改良を加え、1年の太陽の黄道上の動きを視黄経(視黄経は春分を0°とし、雨水は330°にあたる)の15度ごとに24等分するように決められました。もともとは約2600年前の中国の黄河地方の気候に基づき徐々に作られた暦を、日本の風土に合わせて改良し、農耕で主に使用されるようになり、現在に至るようです。
現在のグレゴリオ暦(433年前にローマ教皇が制定・142年前に日本に導入)に暮らす私たちにとっても、この二十四節気の言い回しや言葉は何だか季節を身近に感じられてしっくりくるなあと、思うのです。
万葉集・陰陽五行・二十四節気と、話はあちらこちらへ飛んでしまいましたが、つまりは草木が萌え出す春はすぐそこに。雪が降る季節は徐々に過ぎ去り、春の息吹もそろそろ感じられそうな季節となってきたようです。
皆様、少しは春を感じられましたでしょうか?
2015/02/19
こんにちは。六本木店より、太田です。
今日の六本木は朝は雪がちらつき、現在は雨。寒くて、道行く方々も速足で通り過ぎてゆきます。
さて、毎年恒例の花粉情報がニュースでも出てきましたね。今年は例年の2倍!という噂も。
花粉が本番を迎えたら、次に来るのは春! あとちょっと、寒さと花粉に耐えて春を待つべし!
…とはいえ、花粉症の辛さといったら…。目・鼻・口の中はかゆくなるし、鼻水はダラダラとクシャミは止まらず…。
中医学では、花粉症の主な症状を下記のように考えます。
目・鼻・口がむず痒い:侵入した邪気(じゃき=花粉)と、自分の正気(せいき=免疫)が戦っている。
クシャミ:邪気を体から追い出そうとしている反応。
鼻水:水分の正常な排出ができない状態。
以上のことをふまえ、漢方薬で行う花粉症対策を大まかに3つに分けてみます。
①自分の正気(免疫)のバランスをとる。
②身体が冷えている症状がある方(例えば、透明で水っぽい鼻水・寒気・くしゃみなど)は温め、身体に熱がこもっている症状がある方(例えば、黄色い鼻水・鼻づまり・目の充血など)は余分な熱を冷ますなど、寒熱のバランスを整える。
③余分な水分を排出させるはたらきを整える。
このほかにも、日々の生活の中で気をつけたいことは、「肥厚甘味」(味付けの濃い物・脂っぽい物・甘い物)を避ける、新鮮な温野菜をたっぷり摂る、質の良い睡眠をとる、外出時はマスク・メガネで身体をしっかり守り室内には花粉を入れないようにする、などなど。
その他去年の六本木店のブログ「花粉症に良い」と言われる食べ物を検証してみたもよろしければご覧くださいませ。
 ri ra regenbogen / Daniel Wehner
ri ra regenbogen / Daniel Wehner
さて、こちらは昨日完成した六本木店の花粉症のディスプレイ。 黄色い花粉、リアルさを追求しました。あまりにパンダが辛そうだったためか、通りすがりの小学生がジッとこちらのディスプレイを凝視していたとかいないとか。
どうぞこちらのパンダちゃんを目印にいらしてみてください。
最後に表題の「シュヌップフェン」。勢いが良くてなんとなく好きな単語なんです。
私が1年だけ滞在したドイツの言葉でder schnupfen(シュヌップフェン)は鼻かぜの事。
「花粉症」という言葉を日独辞書でひくと、「heuschnupfen」(ホイ シュヌップフェン)とでてきます。直訳すると「heu」(ホイ)=牛小屋などに敷き詰める干し草、つまり干し草による鼻かぜです。国が変われば、言葉上のアレルゲンも花粉から干し草へと変わるのだなあとしみじみ実感した単語でした。(ドイツでも、実は花粉によるアレルギーはあるのですが。)
ちなみに私は牛小屋で働いていたことがあり、毎日干し草まみれになっておりました。そして文字通りホイ シュヌップフェンになってしまったのでした。しかし、大量の干し草の上でゴロゴロと転がる気持ちよさは都会では味わえない贅沢なものでした。
最後はそのお世話をしていた可愛い牛たちの写真をどうぞ。


2015/02/17