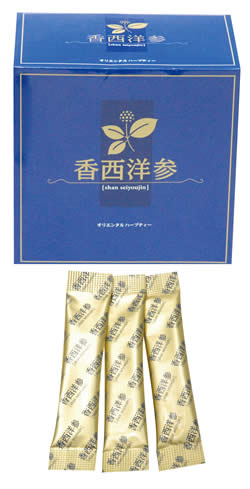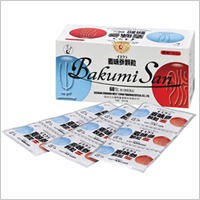先日シンポジウムで拝見させていただいた、栃木中医薬研究会様が制作された、
【生活養生30箇条】が素晴らしいので、シェアさせていただきたいと思います。
生活養生30箇条
【健康づくりのために達成したい生活と食事の30の目標】
監修: 劉桂平 制作: 栃木中医薬研究会
その1:早寝早起き。就寝は夜12時を超えない。深夜の仕事は早朝に回して睡眠を先にとる。深い休養と元気な活動に適した自然な人間の生活で、若々しい身体や肌を蘇らせる「陰」や生命活動を支える「精」を蓄える。
その2:優しい日光を浴びる習慣を。心身のリズムを自然のリズムに合わせることで日常生活を支える「気」の流れを良くし、精神を活性化し身体を強固にする。
その3:適度な運動の習慣をつける。軽く汗をかく程度の、走る・歩く・動き回るなど、無理なく続けられる自分に合った運動が、精神と身体の健康の条件を整えます。
その4:1日3食の時間帯を決めた規則正しい食習慣を。朝食は便通のリズムをつけ、しっかり活動態勢に。昼食は午後の活動のエネルギー源に。夕食はあまり遅くならない時間にゆったり休養態勢に
その5:食量は「腹八分目」が目安。各人の適切な食量は経験的に知る事。中医学的な「脾」を中心にした消化器系に負担をかけないための基本。苦しくならない、重だるくならない、ねむくならない。
その6:穀類と野菜を主体にした食事を。「脾」を健やかにする植物性食材で体内に余計な「湿」や「熱」を増やさない。食材の8割を穀物、豆、根菜、葉菜、海藻にする。植物性食材のみの精進料理は和食の基本の一つ
その7:主食4割、野菜4割、動物生食材2割に。身体に負担をかけない和食的な構成に。質実剛健的な武士の精神から生み出された本膳料理が和食の構成の原型に。健康的かつ実質的。
その8:多種類の食材を少量ずつ取り入れて。旬の食材を優先。各栄養素を偏りなく摂取できるように、出来合いの総菜や冷凍食品も料理の材料にうまく組み合わせて食べ過ぎないように工夫。
その9:朝食は簡素な軽食に。できれば消化に良い温かなものを。胃腸の負担にならない量と内容で毎朝欠かさないよう努める。
その10:昼食は、時間がゆっくり取れなければ、揚げ物や脂っこい料理などの消化に悪いものは避ける。午後の仕事の支障となる重い食事にならないように。
その11:夕食は好きなものをたっぷり。ゆっくり噛んで楽しみ、葉野菜を主にした野菜を多く摂る。葉野菜は消化に良く、栄養豊富で胃腸を強化。最低30回は噛む習慣を。
その12:野菜は、胃腸に負担をかけずビタミンを多く摂るため温かい汁物・煮物・湯で物・炒め物で多く食べる。繊維で閉じ込められた栄養を吸収しやすくする。和食の調理法は精進料理や懐石料理などの野菜中心の食材構成で栄養を十分にとるため工夫され、煮物やあえ物が発達。
その13:具だくさんの味噌汁やスープなどで野菜を先に主食と食べることで、満足感を得ながら過食を防ぐ。温かい汁で葉野菜をたっぷり。でんぷん質をしっかり。豊富な旬の野菜と、油脂をあまり使わない調理法は、水が豊かな日本ならでは。代謝機能に負担をかけない食事になります
その14:低塩分・低脂肪・低糖分になるよう食材・調理法・調味料を工夫する。濃厚な味にマヒした食生活から脱却する。食材本来の美味しさ・味わいの再発見が健康をもたらす。
その15:蛋白源として植物性食材(大豆製品)と、動物性食材(肉・魚・卵)のバランスを考える。どちらも適度に摂る。
その16:揚げ物や肉料理は消化能力の状態に配慮して献立を決め、あるいは量を加減する。多いと、吸収と代謝機能の負担になって体に有害な「湿」や「熱」が溜まりやすいためです。
その17:消化不良や体が受け付けない反応を起こしやすい食材(魚介類、牛乳、卵など)には注意する。胃腸や体の負担になるものが拒絶反応を引き起こす。
その18:乳製品が体に合わない人は、大豆製品・野菜・小魚からカルシウムの摂取を心がける。牛乳がいくらカルシウム豊富でも有効に摂取できなければ無意味
その19:生のもの(野菜・刺身・果物)は旬を選び、あまり大量に食べることは避ける。大量の生のものは消化と代謝を障害し「湿」を増やします。
その20:辛いもの(香辛料・辛味野菜)を必要以上に多量に使うのは避ける。少量なら消化と代謝の促進に役立つが、多量では「熱」となる。
その21:ファストフードを日常的な食事として取り入れない。食欲をそそるための過剰な味付けや添加物で栄養のバランスを崩します。
その22:食欲がない時や、飲食物がもたれているときは、無理に食べない。あるいは軽く済ます。惰性的に食事をせず、たまには抜いたりするのも健康に良い。
その23:食後などに、緑茶・紅茶(あるいは湯・水)を飲むことを習慣に。食後の温かい飲み物は胃腸を保護し消化を助ける。白湯一杯でもよい。
その24:間食としては、野菜ジュース・果物・豆乳など自然のままの甘みと栄養を選ぶようにする。おやつの楽しみも健康に役立つものを。
その25:砂糖を多く使った菓子・ケーキ・デザート・アイスクリーム・清涼飲料水を避ける。甘味(できれば白糖は避ける)は適量なら栄養と休養に役立つが、過剰になれば肥満の原因になるか体内の働きに負担をかけて「湿」として有害化し病気のもとに。
その26:冷たいもの(飲み物、食べ物)を避ける。胃腸の働きを弱め「湿」を増やします。
その27:コーヒーを飲みすぎない。目を覚ますためにコーヒーに頼りすぎない。日内リズムに悪影響。
その28:アルコールを飲みすぎない。アルコールの摂りすぎは生活リズムを崩し、栄養素の代謝を障害し、体内の有毒物を増やす
その29:たばこはやめる。もとより毒性があり、過剰な栄養素の有害化をさらに助長して多くの病気を悪化させる。たばこ依存の生活から脱却を。
その30!!:生活養生は自分の身体と自然を愛する気持ちで健康づくりの楽しみとして毎日取り組む。繰り返し考え直し評価し直すことが大事
まずは現時点の達成度を確認してみて、それから明日からでも達成できそうなものは是非実践してみてくださいね。1ヶ月後、1年後と是非達成項目を増やしてくださいね!