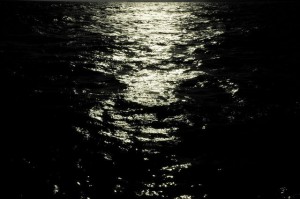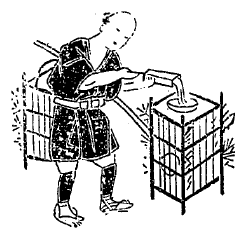こんにちは櫻井です。
一つの疑問を調べていくと、それがどんどん広がりをみせて、思わぬことに突き当ったりすることってありませんか?
先日、ふと訪れたお寺の境内に、「身近な仏教用語~カルピス~」と題した紙が置いてありました。
お寺とは似ても似つかない、カルピスの文字。何となく流してしまいそうだったのですが、「え??カルピス??」っと思わず二度見。これは同じ名前のなんか違うものかと思い手に取ってみると、やっぱりあの“カルピス”のお話です。読んでみると、“「カルピス」という商品名は、お経に出てくる「サルピルマンタ(醍醐味)」に由来するそうです。”と書いてあります。いや、まさか。そこで、wikipediaを見てみると、もうちょっと詳しく載っていました。
“「カルシウム」とサンスクリットの「サルピス」(सर्पिस्, sarpis, 漢訳:熟酥(じゅくそ))を合わせたものである。サンスクリット「サルピル・マンダ」(sarpir-maṇḍa, 漢訳:醍醐)を使用し、「サルピス」・「カルピル」とする案もあった。同社では重要なことを決める際には、その道の第一人者を訪ねる「日本一主義」があり、音楽の第一人者の山田に社名について相談したところ、「カルピス」が最も響きが良いということで現行社名・商品名になったという。”
実際には、サルピルマンタではなく、サルピスとカルシウムを合わせた言葉なんですね。それにしても、まさか「カルピス」と仏教がつながるなんて思ってもいなかったのでびっくりです。
そうしてカルピスと仏教の繋がりの謎がとけたところで気になってくるのは、この「サルピス」。漢訳で熟酥(じゅくそ)というらしいですが、「熟酥とは何ぞや?」と言う新たな疑問がわき出てきました。そこで調べてみると、これがまた面白い話にぶちあたります。熟酥を説明するには、なんと、『醍醐味(だいごみ)』の説明から始めないといけません。
醍醐味とは、物事の面白さや味わいなどをさしていいますが、冒頭にも出てきたように、これもまた仏教用語です。仏教の大乗経典『大般涅槃経』(だいはつねはんきょう)の中に、牛乳から生成される、“おいしいもの”として順に、乳→酪→生酥→熟酥→醍醐となり、一番美味しいものとして、『醍醐』になるようです。醍醐味の醍醐とは、カッテージチーズのような乳製品だったことがわかりました。で、醍醐味とは、その最高の醍醐の味のことをさしていて、最高の味という意味だそうです。何とチーズが仏教が定める最高の味なんだそうです。これもびっくりです。ちなみに乳味、酪味、生酥味、熟酥味、醍醐味というのは、仏教の五味だそうです。中医学の五味(酸味、甘味、辛味、苦味、鹹味)とはまた違いますね。
ここにきてやっと、熟酥(じゅくそ)の話になるのですが、熟酥とは、醍醐の原料となる乳製品のことなんだそうです。これも「とてもおいしい味」として熟酥味(じゅくそみ)と表現されています。熟酥は生酥(しょうそ)という乳製品から作られるのですが、この生酥や熟酥の酥(そ)は、別名、蘇(そ)と書いて、醍醐を作り出す前段階の乳製品です。蘇は平安時代に、税金の代わりとして治められていたほど貴重な品だったそうです。
中医学でも牛乳やチーズは血を増やす食材として扱われています。古代中国でも乳牛が飼われていたんですねぇ。当時は高貴な人々の口にしか入らなかった品物だったとおもいますが、平安時代から日本人が乳製品を食べていたということには驚かされました。醍醐や蘇の製造方法は、古代中国から秦氏によって持ち込まれたと考えられています。秦氏の入植によりその名がついたと言われる、神奈川県秦野市には、「からこさんは、中国からおいでになり、 大磯の浜辺から秦野に移住した」という伝説があり、秦氏が定着した土地は“乳牛(ちゅうし)”と呼ばれ、乳牛を飼うことを教えたそうです。そうなると乳製品は平安時代よりも前から日本人に食べられていたことも考えられますね。いや~驚きです。
食べ物は奥が深いです。いや、すべての物事には奥深い物語が隠れているんでしょうね。まさかカルピスがこんなところに繋がってくるとは思ってもみませんでした。普段何ともおもっていない事を調べてみると、びっくりするほど面白いことに突き当るものです。お試しあれ。