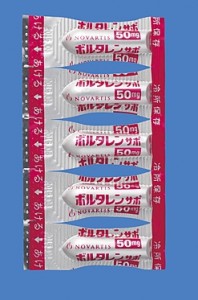>>>昨年7月に上げた記事を加筆して再アップしました<<<
少しお休みをいただいていたら、今日の夢で子宝漢方相談をして、婦宝当帰膠と参茸補血丸をお勧めしていた櫻井です。加味逍遙散の注意事項に頭を悩ませていたのはなんだったのか記憶はあいまいです。こんにちは。唐突ですが、蝉も鳴きはじめ、夏もそろそろ本番となってきたので、ちょっとだけスキンケアのお話を。
暑い一日、肌も大変なストレスにさらされています。私たちが汗をかきすぎて脱水を起こすように、肌も脱水状態です。水分を含まない物はすぐ発火するように、肌も潤いが少ないとすぐに焼けて荒れてしまいます。まずはしっかり水分補給してあげることがこの季節に一番肝心なスキンケアです。
しかし、肌は強固な生体バリアーなので、そう簡単に潤いは外から肌に浸透してくれません。殆どの化粧水は肌の表面、死んだ細胞が層になって付着している角質層を潤しているだけです。それでは本来の『肌の弾力性』は回復できません。もちろん、外からの潤い補給は大切ですが、それには限界があります。
では、どうするかと言うと、中から補給するのです。
この「中から補給」の説明でよく使われるのは「コラーゲン」ですが、コラーゲンは肉や大豆と同じタンパク質なので、食べると一度アミノ酸に分解されます。分解されたアミノ酸はまた同じくコラーゲンになるとは限りません。「コラーゲンを食べれば翌朝お肌ぷるぷる☆」など、そうは簡単にはいかないようです。
肌を潤すものは血や津液という潤いの元。
まずはこ血や津液(しんえき・水分)を補う食生活を心がけましょう。血が足りない方は、肌がしろく、冷えがあり、便秘、もしくは胃腸虚弱の傾向がある方が多く見られます。黒色のものや色の濃い緑黄色野菜をたくさん摂りましょう。黒豆、黒米、プルーン、黒きくらげ、黒ゴマ、枝豆、ホウレンソウ、ちんげんさい、にんじん、ぶどう、くり、イワシ、カキ、イカ、黒砂糖、紅茶など。女性は生理があるので血が不足しがちです。サラダやパスタばかりの食事など、食の偏りや無理なダイエットなどには注意が必要です。
津液(潤い)が足りない方は、ほてりがあったり、肌が赤かったり、肌や喉、口が乾燥したり、唇がまっかだったりします。寝汗をかく方もいらっしゃいます。白ごま、豆腐、白きくらげ、大根、白菜、山芋、なし、リンゴ、カニなどや昆布、豚にく、卵、はちみつなどを毎日の食事に摂りいれましょう。辛いもの、薬味などはできるだけ避けましょう。果物など、自然な酸味と甘味の組み合わせは「酸甘化陰」といって、潤い(陰)を生みます。陰の時間の夜に身体をしっかり補うことも大切なので、早寝もとっても大切です。
スキンケアで大事なことは、
肌に熱をこもらせないことと、しっかり解毒すること
熱のこもりや肌荒れの原因となる便秘はお肌の大敵です。そのためには、葉野菜をたっぷり摂りましょう。胃腸に負担をかけないように火を通してたっぷり食べることをお勧めします。夏はどうしても冷たいものを摂りがちですが、胃腸機能低下から便秘や下痢を招かないためにも、夏こそあったかいものを食べてしっかり発汗しましょう。
睡眠不足はお肌の大敵です
睡眠は、肌の機能調整を整えるホルモンが分泌される時間です。そして細胞の新陳代謝は寝ている間にこそ活性化されます。睡眠不足は、肌が再生し回復するために必要な時間を奪います。睡眠は、量より質です。お肌にとって最適な睡眠時間は10時から2時。この時間帯にできるだけ身体を横にして、脳に血流を増やし、休憩態勢に入ったことを認識させ、しっかり修復させましょう。
次はスキンケア対策を見直してみましょう
特に乾燥がひどい人はコットンなどを使って化粧水をつけるのもNGです。手でつけるようにしましょう。その時はくれぐれもパンパン叩かないように!ぎゅっと浸透させるように肌の上からかるく抑えて入れます。クレンジングもごしごしこすると乾燥で弱った肌をさらに傷つけます。ニキビがあっても決してごしごしこすらないよう気をつけてください。
乾燥には洗顔方法を変える事が一番効果的です。メイク、洗顔のしすぎ、すすぎ過ぎなどはとにかく避けましょう。水に近いぬるま湯でTゾーンの部分をメインに優しく洗いましょう。人間の肌は汚れが落ちるようにできていますので、メイクしていないなら、本来はぬるま湯洗いだけで十分汚れは落ちます。
とにかく肌に負担をかけないように
メイクも日焼け止め以外は出来るだけしないほうがイイでしょう。クレンジングも、どうしてもメイクをしなくてはいけない時だけにしましょう。特にオイルクレンジングは必要な皮脂まで洗い流してしまうので、使用は最小限にしましょう。しみる化粧水はやめてください。そして化粧水をアレコレ変えるのも、肌の回復をまってからの方が賢明です。
洗顔後に残ってみえるふやけた肌は、ちょっと日焼けみたいにぽろぽろカサカサがふやけてはがれやすくなってますが、絶対につめなどではがさないようにしましょう。ただでさえ弱っている肌にさらに傷がつきます。
乾燥が特にひどい人は石鹸や洗顔料などを使わない、ぬるま湯の素洗いを心がけましょう。シャワーを直接かけるのも禁物です。手に掬ってからお肌を洗うようにしましょう。
しみやくすみの原因にもなるので、肌にはとにかくやさしくする事が大事です。やさしく、やさしく。絶対こすらないように!!
早速今日から、外と中から素肌ケア実践してみてくださいね。
まずは、睡眠から始められませんか?
☆あわせてよみたい☆
さらにニキビにはこちらもチェック→『ニキビのタイプと対処方法』