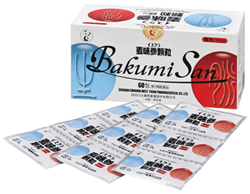月経前になるとイライラする!というご相談を良く耳にします。
こんにちは。櫻井です。
今日は月経前のイライラ、いわゆるPMS(月経前症候群)と胸の張りについてのお話です。
月経前にイライラするという方の多くに、「生理前に胸が張り、痛い」とおっしゃるかたがいらっしゃいます。生理前の胸の張りは、ホルモンの影響により、乳腺がはるためにおこる痛みですが、順調に生理が来る方でもまったく痛くならない方もいらっしゃいますし、先月は痛みがあったのに、今月はないという場合もあります。その差はなんなのかというのは、現代医学ではまだ解明できていないようです。
中医学では、この生理前の胸の張りと痛みは、【気滞(きたい)】といって、気の巡りが悪くなった状態と考えられています。私たちの身体の中では、絶えずリンパ液や血液、そしてエネルギーが巡っていますが、巡りが悪くなり詰まってしまうと、痛みが起こります。胸が張って痛むというのはその象徴ですが、普段でもわき腹のあたりをさすってみると気持ちよく感じる場合などは、巡りが悪くなっていると考えられます。
気滞の主な原因は精神的なストレスです。
ストレスは「怒り・いらいら」と認識され、肝の「疏泄(そせつ)」という機能を失調させます。肝の疏泄機能とは、気や血を体に必要部位に必要な量流れるように調節する働きです。「怒」は、七情(しちじょう*)という正常な情志変化の一つですが、強く感じたり、長期間にわたって感じていたりすると、病気を引き起こす主要な原因となります。この怒は肝の疏泄機能に影響を及ぼし、体の上部に気を昇らせてしまい(気の逆上)頭痛や顔面の紅潮、目がちばしるなどの症状を引き起こします。これらは瞬間的な「頭に血が昇る」という状態ですが、長期的にストレスを受け、イライラが溜まると、気の全体的な巡りに影響し、一部の症状として、「胸の張りや痛み」を感じるようになります。よって、胸の張りや痛みを感じる方は、ストレスが溜まった状態と言い換えることが出来ます。
(*七情はほかに喜・思・憂・悲・恐・驚があります)
ストレス緩和が大切です。
胸を張りにくくするためには、その原因であるストレスを取り除くことが一番の解決策ですが、ストレスの根本は性格が大きく影響しているため、なかなか簡単には改善できませんので、ため込んでしまう前に吐き出すことが大切です。ストレスの解決法として、私がおすすめしたいのは、瞑想によって心を落ち着ける方法です。瞑想法に関しては過去のブログをご参照ください。
気滞を引き起こす原因は、精神的ストレスが主な原因ですが、偏った食事、とくに辛いもの、油っこいものなども原因となると考えられています。ビタミン、ミネラルを適切な量摂ることも良いとされています。そして、緑色野菜に多く含まれる非ヘム鉄の摂取が少ないと生理前の不調が出やすいという研究結果もあります。海藻類などは最もたるものですので、野菜たっぷりのお味噌汁なんておすすめです。
中医学では、気を巡らせるには、香味野菜を積極的に摂るように進めています。香りの野菜は香りが飛んでしまうので、加熱を少な目にすることもポイントです。肝の機能をよくする酸味の食べ物も良いでしょう。熱性や辛味の強いものを避けましょう。お酒の飲みすぎも肝を傷つけます。
おすすめ食材は、
パセリ、梅干し、ジャスミン、カモミール、レバー、黒酢、キャベツ、レモン、ブドウ、クコの実、ローズ、ゆず、グレープフルーツ、セリ、金針菜、ラベンダー、三つ葉など。(赤字は温める食材、青字は冷ます食材、黒字はどちらでもない)
ストレスを蓄積してしまうことが気滞を引き起こす大きな原因です。忙しい中でもゆとりを持つことを忘れないでください。たまにはすべてを忘れて、緑の公園を散歩したり、映画を見たり、音楽を聴いてみたり、親しい仲間同士でわらいあったりなど、リラックスしたひと時を設けて上手に気分転換しましょう。
あわせて読みたい!
ストレスを受けやすいタイプのお話
ストレスって何?